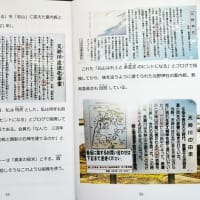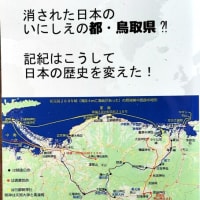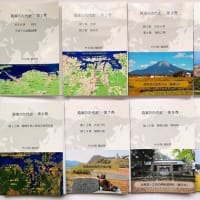1 四王寺山周辺の遺跡



鳥取県の遺跡・古墳の数は奈良県・兵庫県と比較されるほど多い。その中でも、鳥取県中部は県内の遺跡総数の3分の2を占め、特に四王寺山周辺は多い。おそらく、遺跡・古墳の密度は全国1位である。それはそうでしょう。蜘ヶ家山の島には縄文前期から猿田彦一族がおり、四王寺山には神倭磐余彦4兄弟がいたのだから。四王寺山の土塁上から紀元前100年頃(神武元年は紀元前60年)の鉄矛(国内最長)や住居跡が出土している。
上神古墳群を見ると蜘ヶ家山(葛城山)に上がっているので黄泉平坂は蜘ヶ家山(葛城山)に上がっていたと推測できる。上神から男坂(急な坂)になる。不入岡から上神までが女坂(緩やかな坂)であった。遺跡・古墳の時代はご自分でお調べください。旧石器時代から古墳時代まであります。
2 主に奈良時代以降の遺跡

法華寺畑遺跡と伯耆国分寺と伯耆国庁は同じ頃(741年頃)に倭国(鳥取県中部)を乗っ取った亡命百済王朝(日本)によって造られた。法華寺畑遺跡は発掘された建物の規模と配置からすれば国分尼寺ではなく「国庁に関連した役所」とされる。公的見解は「全国に類例がなく何のための役所だったか判らない」とする。私見は「銘のない多くの墓がそばにあり処刑場跡」とする。
上から下を通っているのは県道倉吉東伯線(151号線)である。県道151号線は倉吉から琴浦町伊勢野に通じている。天武天皇の大来皇女は泊瀬の斎宮(倉吉市駄経寺町の大御堂廃寺)から伊勢神宮(琴浦町伊勢野)まで行くのにこの県道151号線を通っている。亀谷集落から邇邇芸の御所(上種の大宮神社)に行くこともできる。県道151号線は古代の幹線道路であった。
上から下を通っているのは県道倉吉東伯線(151号線)である。県道151号線は倉吉から琴浦町伊勢野に通じている。天武天皇の大来皇女は泊瀬の斎宮(倉吉市駄経寺町の大御堂廃寺)から伊勢神宮(琴浦町伊勢野)まで行くのにこの県道151号線を通っている。亀谷集落から邇邇芸の御所(上種の大宮神社)に行くこともできる。県道151号線は古代の幹線道路であった。
3 四王寺山より大谷集落を俯瞰


土塁を通り抜けた先が法華寺畑遺跡になる。その右が伯耆国庁跡になる。このように四王寺山を意識して国庁・付属の役所が建っていた。
四王寺山の麓に登山口を分からないように大谷集落をつくり、大谷集落を守るように3~4mの高さの土塁を造ったのは9世紀の四天王を祀る四王寺を守るためではなかった。四王寺山の大谷集落から出ている道路はまっすぐに福光集落に通じていた。その上に法華寺畑遺跡を造っている。従って大谷集落を外から判らないように守っている構造はまっすぐな道路とセットで、奈良時代以前から造られていた。
後記ー土塁の上から紀元前100年頃(神武元年は紀元前60年)の鉄矛(国内最長)や住居跡が出土した。四王寺山全体の構造(北面と大谷の2集落からしか上がれないようにしてある構造)自体が紀元前100年頃すでに造られていた。
大谷集落やその構造は奈良時代に藤原氏が造ったのではなく、倭国の彦火火出見(山幸彦)の宮として造られていた。また土塁は神倭磐余彦4兄弟を倉吉市富海にいた海幸彦(長髄彦=出雲族=準王一族)から守るために造られた。県道151号線を挟んで倭国と日本(亡命百済王朝)の遺跡に分かれる。
以前は、彦火火出見と鵜草葺不合の二人は北栄町上種の邇邇芸の宮(大宮神社)に居候していたと思っていたが、鵜草葺不合(由緒・伝承がほとんど残っていない)は彦火火出見のあだ名であり、彦火火出見(山幸彦)は3年間、海幸彦から辰韓に逃げていたがまた帰ってきて四王寺山に宮を築いた。そして神倭磐余彦4兄弟(しおうじ)を生み育てた。
藤原氏は同族の出雲族には寛容だが伯耆国にいた天皇の伝承は消し去ったので、大谷集落の誰も神倭磐余彦4兄弟について言う者はいない。藤原氏は鳥取県中部の多くの集落に本当の歴史を否定する者を有力者として配置している。
「4人の王子がいたかもしれない」という大谷集落の若者はいたが、歴史に詳しいといわれる大谷集落の長老はそれを否定して「四天王を祀る四王寺があるから四王寺山という」といわれを述べた。