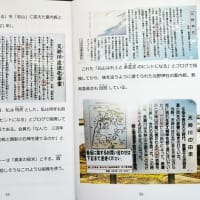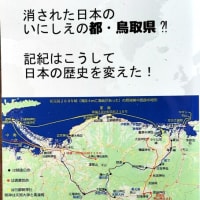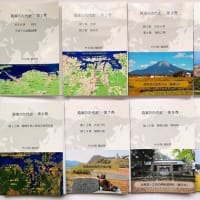1 日本書紀・神武天皇・宮殿造営に「見ればかの畝傍山の東南の橿原の地は、思うに国の奥深く安住に適した地である。ここで治めるべきである、と令を下された。」とある。原文には「國之墺區」とある。これは厳密には「国の奥深く安住に適した地」と解釈するそうである。私見では倉吉市大宮は歴代31人の天皇の皇居の中で一番山奥に位置する。
「橿原の地」とあるが、これは奈良ではなく倉吉市大宮であった。倉吉市大宮に宮殿を造営し、倉吉市大宮で初代天皇として即位した。紀元前60年のことである。倉吉市大宮は倭国(鳥取県中部)では「国の奥深く安住に適した地」である。第2代天皇からはニニギ命がいと良き地と言った笠沙之御前の周辺に皇居を造ったが、神武天皇は倉吉市大宮に宮殿を造営した。この倉吉市大宮は四王寺山から見れば、東南になる。
「かの畝傍山」とは四王子が生まれ育ったところだから、「かの」とつけたのである。日本書紀を作っているときには「四王寺山」の麓に伯耆国庁を造って山上憶良に調べさせている。不比等たちはそれほど「四王寺山」を重視していたようである。特に百済を滅ぼした新羅の建国者である稲飯命が生まれ育った地ということは脅威であった。
2 橿原即位に「天皇は論功行賞を行われた。大来目を畝傍山の西、川辺の地におらしめられた。」とある。
四王寺山の西の丘陵地を久米ヶ原という。大来目たちは久米ヶ原にいて皇軍を組織した。久米ヶ原には久米中学や久米支所などの名前が残っている。
3 「畝傍山の東北の陵に葬った。」とある。
四王寺山の東北は寺谷古墳群・土下古墳群など数百の古墳があるので、その中にあるはずである。


4 このように3か所の方角が合うので日本書紀にいう「畝傍山」とは神武天皇たち四兄弟がいた倉吉市「四王寺山」のことである。神武天皇も橿原宮(倉吉市大宮)で即位してから、今の小鴨神社の地で畝傍山(四王寺山)をことあるごとに眺めていた。
5 奈良県橿原市大谷町と倉吉市大谷集落との写真比較

奈良県橿原市大谷町 上は畝傍山

倉吉市大谷集落 上は四王寺山
どちらも大谷(王谷)だし、どちらも山の入山口を塞いでいるし、どちらかが真似をしているようです。倉吉市大谷集落の入り口には3mくらいの高さの土手がある。この土手の東側から紀元前100年頃の遺跡(中尾遺跡)が発掘された。東には不入岡(岡に入るべからず)という集落がある。土下山(天の香久山=鳥見の白庭山)にいた青銅器文化の一族(出雲神族)から守るために、外から大谷集落は見えないようにしてある。トンネルのような入り口を入っても真っ直ぐに行けば中腹の寺に突き当たり行き止まりである。そこまで行かずに途中で右に折れ200mくらい行ったところが入山口である。そこから上がってすぐのところに右に小屋でも建っていたような広場があり、今度は反対にバックするように、左にうねうね道を頂上まであがって行くことになる。まるで道教の橋を想像させる。奈良県橿原市大谷町は開放的で大谷町を隠す土手などまるでない。大事な4人の皇子を育てるとすれば、集落ごと隠す構造にする。奈良の畝傍山の大谷町は倉吉市大谷集落を真似て造っているが本物ではない。
どちらも大谷(王谷)だし、どちらも山の入山口を塞いでいるし、どちらかが真似をしているようです。倉吉市大谷集落の入り口には3mくらいの高さの土手がある。この土手の東側から紀元前100年頃の遺跡(中尾遺跡)が発掘された。東には不入岡(岡に入るべからず)という集落がある。土下山(天の香久山=鳥見の白庭山)にいた青銅器文化の一族(出雲神族)から守るために、外から大谷集落は見えないようにしてある。トンネルのような入り口を入っても真っ直ぐに行けば中腹の寺に突き当たり行き止まりである。そこまで行かずに途中で右に折れ200mくらい行ったところが入山口である。そこから上がってすぐのところに右に小屋でも建っていたような広場があり、今度は反対にバックするように、左にうねうね道を頂上まであがって行くことになる。まるで道教の橋を想像させる。奈良県橿原市大谷町は開放的で大谷町を隠す土手などまるでない。大事な4人の皇子を育てるとすれば、集落ごと隠す構造にする。奈良の畝傍山の大谷町は倉吉市大谷集落を真似て造っているが本物ではない。