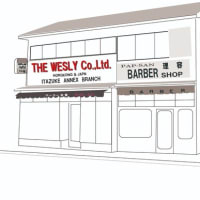「笹野才蔵」信仰の分布は福岡市博物館のいう
江戸期の「博多写し」文化圏と重なります。
このことから信仰の発信元は博多のようです。
信仰の始まりをうかがい知ることのできる逸話が
博多市小路の医師が書いた地誌『石城志』(1765 年)に記されています。
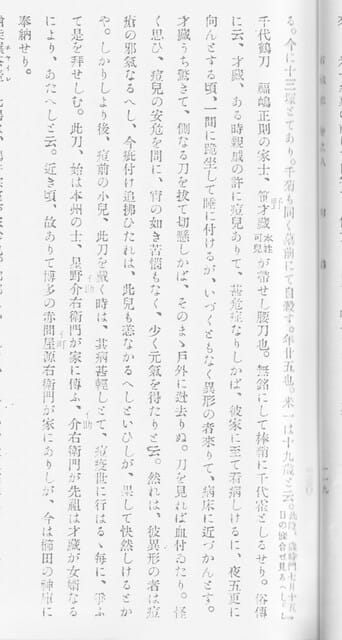
『石城志』巻之八付録 千代鶴刀
ここには「笹野才蔵」が疱瘡にかかった親戚の子どもの看病をしていたある夜、
異形のものの気配を愛用の刀で斬りはらったところ、それが疫病の邪気で、
その後は子どもの病が快癒したことから、疫病にかかった際には
この刀を拝して頂く習慣が博多で広がり、刀が櫛田神社に奉納された後
も疫病が流行すると、神社から度々この刀が貸し出され、人々は争ってこの刀を拝した
と書かれています。
『石城志』が書かれた 1765 年頃はまだお札や人形のことは書かれておらず、
広く民衆に才蔵信仰が広がっている段階ではありません。
このことから「笹野才蔵」信仰の発信地は櫛田神社で
その信仰の根源は才蔵の刀「千代鶴刀」(千代鶴国安作)であったと考えられます。
山笠行事が疫病退散を祈願する行事であることから、
神社にとっては才蔵の刀を伝承することは重要なことであったと考えられます。
現在、櫛田神社境内にある歴史館ではちょうどこの刀を展示中です。

17番ソラリア山笠周りの解説版
江戸期の「博多写し」文化圏と重なります。
このことから信仰の発信元は博多のようです。
信仰の始まりをうかがい知ることのできる逸話が
博多市小路の医師が書いた地誌『石城志』(1765 年)に記されています。
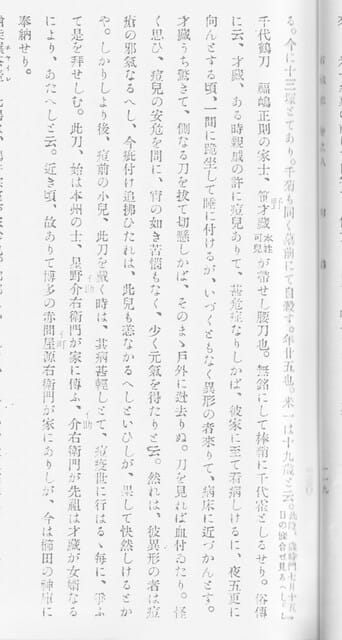
『石城志』巻之八付録 千代鶴刀
ここには「笹野才蔵」が疱瘡にかかった親戚の子どもの看病をしていたある夜、
異形のものの気配を愛用の刀で斬りはらったところ、それが疫病の邪気で、
その後は子どもの病が快癒したことから、疫病にかかった際には
この刀を拝して頂く習慣が博多で広がり、刀が櫛田神社に奉納された後
も疫病が流行すると、神社から度々この刀が貸し出され、人々は争ってこの刀を拝した
と書かれています。
『石城志』が書かれた 1765 年頃はまだお札や人形のことは書かれておらず、
広く民衆に才蔵信仰が広がっている段階ではありません。
このことから「笹野才蔵」信仰の発信地は櫛田神社で
その信仰の根源は才蔵の刀「千代鶴刀」(千代鶴国安作)であったと考えられます。
山笠行事が疫病退散を祈願する行事であることから、
神社にとっては才蔵の刀を伝承することは重要なことであったと考えられます。
現在、櫛田神社境内にある歴史館ではちょうどこの刀を展示中です。

17番ソラリア山笠周りの解説版