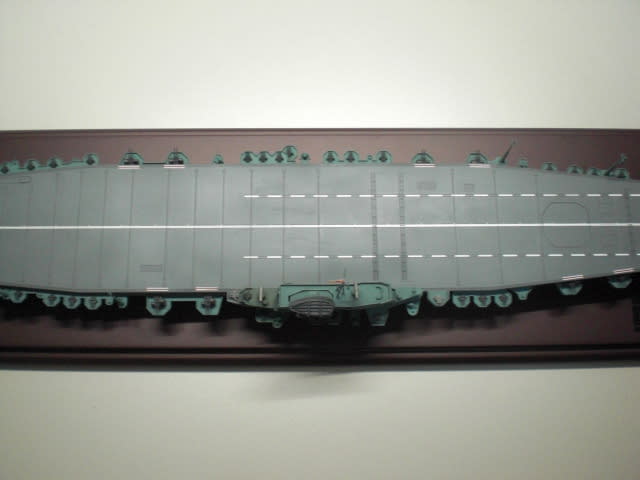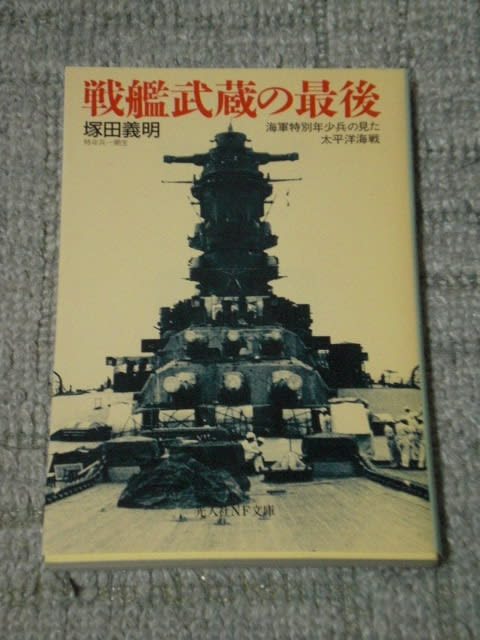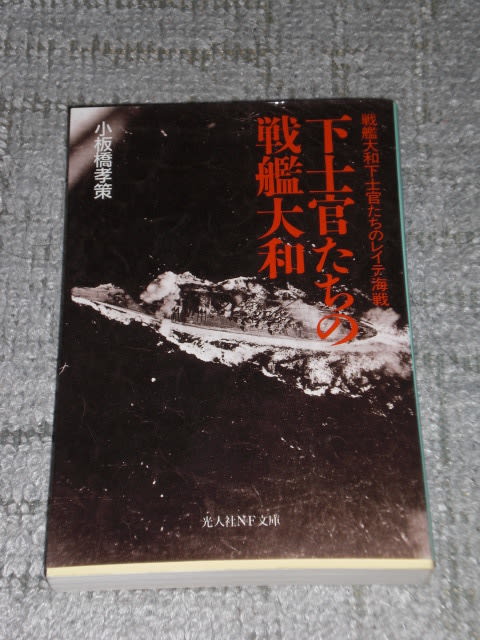4月18日は日本で初めて観艦式が行われた日です!
観艦式とは、国際親善や防衛交流を促進するために行われる軍事パレードの一種で、国家の祝典の際や海軍の記念行事の際に軍艦を並べて壮行する式のことです。
かつては、味方の艦隊を観閲することにより、軍の士気を高め、国民や友好勢力には、精強さをアピールすると共に、敵勢力に対する示威行為とすることでありましたが、現在では、他国からの艦艇を招き、国際親善や防衛交流を促進することや、自国民の海軍に対する理解を深めることが主要な目的です。
この観艦式は、1341年の英仏百年戦争の時に、イングランドの国王だったエドワード3世が自ら艦隊を観閲し、士気を鼓舞したのが始まりとされています。 また、現在各国で行なわれている観艦式の様式は、1897(明治30)、イギリスのビクトリア女王即位60年祝賀の際に挙行されたものが基となっています。
日本で最初の観艦式は、1868(明治元)年4月18日に大阪湾の天保山沖において、明治天皇が陸上から観閲の下、明治新政府に帰順した日本の軍艦6隻とフランス海軍の軍艦1隻の計7隻で行われました。
この時の参加艦艇は、「電流丸=肥前藩鍋島家所有、300トン」、「萬里丸=熊本藩細川家所有」、「千歳丸=久留米藩有馬家所有、459トン」、「三邦丸=薩摩藩島津家所有」、「華陽丸=長州藩毛利家所有、413トン」、「萬年丸=広島藩浅野家所有」の6隻と「デュプレクス、1173トン」というフランスの1隻で、総指揮官の石井忠亮海軍中佐は旗艦の電流丸で指揮を執りました。
太平洋戦争前には、この第1回から1940(昭和15)年の特別観艦式まで合計18回の観艦式が行われましたが、1905(明治38)年10月23日に115隻の軍艦が参加して行われた東京湾凱旋観艦式(日露戦争凱旋観艦式)と、1928(昭和3)年12月4日に186隻の軍艦と130機の航空機が参加して行われた御大礼特別観艦式は、特に盛大な観艦式でした。
戦後、観艦式は、海上自衛隊の創設に伴って1957(昭和32)年10月1日に東京湾で再開されました。 その後、1973(昭和48)年までは毎年行われていましたが、オイルショックによる中断を経て、現在は3年に1回、自衛隊記念日である11月1日前後に記念行事の一環として行われています。

今日もご訪問有難うございます