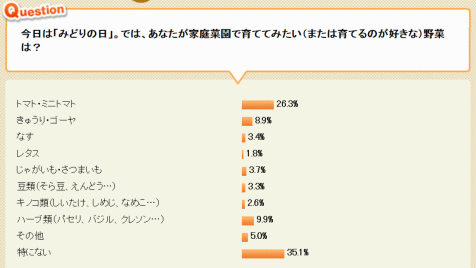【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 5月3日 コーヒーは胃を荒らすという都市伝説は正しいのか?
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
「文章を書くことは、脳の活性化に繋がる」ということを聞いたことがあります。
それを信じて、毎日複数回、つぶやきとしてSNSに書くことにしています。
老いぼれコンサルタントが、心も頭も老いぼれないように願って・・・

■ コーヒーは胃を荒らすという都市伝説は正しいのか?
日本のコーヒー消費量は年間15万トンにも上り、緑茶の10万トンをはるかにしのぐほどの身近な飲み物となっています
都市伝説的に言われることとして、コーヒーは「胃に悪い」と言われます。しかし、アラビアの文献では、コーヒーは、「胃に効く薬」として紹介されています。
イギリスのコーヒー科学情報センター(CoSIC)は、コーヒーと健康に関する科学情報の膨大なデータベースを保有しています。
同センターでは、コーヒーの飲用と胃潰瘍の発生には関係がないと発表しました。胸焼けについてもコーヒーと関係づけることはできなかったそうです。
近年の研究から、胃液の分泌を盛んにして消化を助けることもわかってきました。エネルギー消費や脂肪の分解を促すなどのダイエット効果もあるという女性には嬉しい情報もあります。
近年の研究では、コーヒーは“善玉コレステロール”(HDLコレステロール)を増やして動脈硬化を防ぐということが発表されています。また、直腸がんのリスクを減らす効果も調査結果として報告されています。
日本疫学会では、コーヒーを1日1杯以上飲む人は、肝がんになるリスクが、全く飲まない人の6割程度に低下するという調査結果を発表しています。
コーヒーに含まれるカフェインには覚醒作用があるといわれています。頭をすっきりと冴えさせてくれます。利尿作用についてもよく知られています。
糖尿病の予防効果も、欧米を中心に数多い研究が行われています。
ただし、ダイエットや病気予防に対するコーヒーの効果は、飲む量や飲み方、飲むタイミングによっても変わってくるので注意が必要です。
例えば、コーヒーを飲んでほっと一息といった「リラックス効果」は、実はコーヒー豆の種類によって、違いがあることが分かっています。
また、体脂肪の分解を効率的に進めるためには、運動をする20~30分前にコーヒーを飲むのが最も効果的とされています。
これからは健康飲料としての楽しみ方も考えてみてはいかがでしょうか。
〔参考文献〕全日本コーヒー協会 : コーヒーのことからだのこと.
一方で、コーヒーの飲み過ぎには注意が必要です。
コーヒーには、カフェインが含まれていますので、多量に飲みすぎますと副作用が出て来ることがわかっています。
一説のよりますと、一日に5杯以上飲む人に副作用が多く出るそうです。
カフェインは、交感神経を刺激しますので、睡眠時に必要な副交感神経の働きを弱め、眠れなくなることはよく知られています。利尿作用もありますので、高齢者が、夜コーヒーを飲むことは控えるべきです。
頭痛がある時にコーヒーを飲みますと、頭痛が和らぐことを体験している人は多いでしょう。ところが、カフェインを取り過ぎると、逆に、カフェインによる血管拡張作用で頭痛がひどくなったり、頭痛がないのに頭痛が発生してしまうことがあるそうです。
疲れている時も、コーヒー一杯で至福の時を過ごす人も多いでしょう。私も、そのひとりです。カフェインには、疲労解消の効果があるといわれています。しかし、人によっては、逆に疲労感が残ることがあるそうです。「疲労感が低下した」ように感じるのは、カフェインに含まれるアデノシンという成分に覚醒作用があるからだそうです。
コーヒーには、ポリフェノールが含まれていますので、血圧を下げる効果があります。ところが、高血圧で、肝機能が弱っている人は、カフェインを摂り過ぎますと、高血圧のリスクが高まることがわかっています。心拍数も上がりますので、心臓への負荷も増えます。
あまり知られてはいませんが、利尿作用によってカルシウムが尿中に多く排出されてしまいますので、カルシウム不足気味の人がコーヒーを多量に飲むと骨粗鬆症にかかってしまうそうです。
血中のカルシウムだけではなく、カリウムも排出します。多量に飲むことにより低カリウム血症になりやすいのです。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】などをご紹介します。
ttps://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
◆ 語感と幼児性
近年、語感がかなり狂ってきているように思えます。
マーケティングの専門用語に「差別化」という言葉があります。一方で、「差別された」などと「差別」という言葉はマイナスのニュアンスが強い言葉です。それにもかかわらず、「差別化」という表現に奇異感を感ずる人が少ないです。
マーケティングの専門用語であり、専門家も「差別化」という言葉を用いていますから、そのまま使っているということが大半なのでしょう。
私は半世紀以上前に、アメリカに駐在員として派遣され、5年間ニューヨークで仕事をしていました。その間、「黄色人種」「日本人」という理由で差別されたことがなんどかあります。その体験もあり、「差別」という言葉のニュアンスに過敏になりすぎていることは否めないかも知れません。
自称は「私」であるというのは、学生時代に何かの本で学びました。新入社員研修でも、おなじことを学びました。ところが、近年、ビジネスパーソンが「僕」という言葉を平気で使っています。それどころか、TVを視ていますと、社会的立場のある人が並記で僕と自称しています。これも上述のように語感低下の表れといえます。
「僕」は、男性の謙称で、もともとは、「男の召し使い」を指しています。子供言葉なのです。母親のことを、こどもが「おかあちゃん」と呼ぶのと同じ幼児語なのです。
それだけではありません。「僕」は、男性が用いる言葉であり、女性向けの対語は「妾(ショウ)」です。「僕妾」は、「しもべ」と「めかけ」、下男下女という意味です。自訴が自分のことを「妾(ショウ)」と呼ぶことを聞いたことがありません。それにもかかわらず、男性が「僕」を使うことに奇異感を持たない人が多いのです。
あるマナー書を見ていましたら、「僕」は近年ではフォーマルな場でも使えると記述されていました。私にとっては、語感が低下していると言わざるを得ません。
ちなみに「私」は、「わたし」ではなく、「わたくし」です。
■ 基本的な法律は理解しておきたいですね 426
日本の法律は、ドイツから学ぶところが多かったようです。
こんにちの会社法の基本ともなりました商法ですが、日本の旧商法はドイツの商法がもととなっています。
商法に関連する法律が、会社法以外にもいくつかありますが、ご自身のビジネスに関連する法律は一通り知っておく必要がありますね。
代表的な商法関連法法規を列挙しておきました。
お恥ずかしながら、私は法律を暗記するのが苦手で、もっぱら専門家に任せてしまっています。

■【小説】 竹根好助の経営コンサルタント起業
「【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記」から独立して、最初から発信していたします。
私は、経営コンサルタント業で生涯現役を貫こうと思って、半世紀ほどになります。しかし、近年は心身ともに思う様にならなくなり、創業以来、右腕として私を支えてくれた竹根好助(たけねよしすけ)に、後継者として会社を任せて数年になります。
竹根は、業務報告に毎日のように私を訪れてくれます。二人とも下戸ですので、酒を酌み交わしながらではありませんが、昔話に時間を忘れて陥ってしまいます。それを私の友人が、書き下ろしで小説風に文章にしてくれています。
原稿ができた分を、原則として、毎週金曜日に皆様にお届けします。
【これまでのあらすじ】
竹根好助は、私の会社の後継者で、ベテランの経営コンサルタントでもあります。
その竹根が経営コンサルタントに転身する前、どのような状況で、どの様な心情で、なぜ経営コンサルタントとして再スタートを切ったのかというお話です。
1ドルが360円の時代、すなわち1970年のことでした。入社して、まだ1年半にも満たないときに、福田商事が、アメリカ駐在事務所を開設するという重大発表がありました。
角菊貿易事業部長の推薦する佐藤ではなく、初代駐在所長に竹根が選ばれました。それを面白く思わない人もいる中で、竹根はニューヨークに赴任します。慣れない市場、おぼつかないビジネス経験の竹根は、日常業務に加え、商社マンの業務の一つであるアテンドというなれない業務もあります。苦闘の連続の竹根には、次々と難問が押し寄せてくるのです。
4 迷いの始まり 4-9 竹根にとっての営業活動
<最新版> 毎週金曜日正午頃発信
■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。
明細リストからだけではなく、下記の総合URLからもご覧いただけます。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17
>> もっと見る
■バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a8e7a72e1eada198f474d86d7aaf43db