上野千鶴子
「誰も答えたことのない問いを立ててごらんなさい」(毎日新聞、2023年12月16日)

いま、世の中はAI の働きの話題でいっぱいだ。課題を投げかければ、並の人間にはできないような言い回しの答えが短時間で帰ってくる。僕は使ってないが、これは個人に属していた文化の所属を非人称化するかに見える。ヒトの終焉につながるかもしれないと言われるのも宜なるかな。しかし僕がAIがいまだ苦手だろうと思うことがある。それは問題の発見である。
僕は高校の頃から70年近く数学の問題作りに励んできた。そういう経験から問題作成について思っていることを書き連ねてみる。僕は難問を作っては友人に解かせていた。友人にはなかなか解けなかった。では数学が抜群にできたかというと全然そうではない。計算が遅く不正確なのだ。したがって僕の模擬試験での数学はひどく波があった。文系のできる友人は、僕が数学のプロになった後も「数学ならお前には負けなんだなあ」などと言われた。入試も数学が散々で浪人したほどだ。最近聞いた友人の実験では、現在のところChat-GPTも分数の計算のようなことでもミスをよくやるらしい。計算ミスをしやすいということがどういう頭の働きによるか解明の一助となるかもしれない。
浪人のときは、自宅浪人だったから、友人がほとんど京都に下宿して予備校に通っていた。代わりに難問の雑誌「大学への数学」をとり勉強していた。この雑誌はすこぶる難しいと言う定評のあったものだが、のちに数学のノーベル賞級、あるいはそれ以上と言われるフィールズ賞を獲得した森重文さんはこの雑誌の添削問題で繰り返し満点を取っていたそうだ。僕は新作問題を作って応募していた。何題か採用されている。大学のサークルもアルバイトを兼ねて添削グループに入り、大学院のときは難問で鳴らした塾で問題作成を行っている。近大に勤めてからは、毎年多くの学部の出題をやらされ、教室の数学コンクールの出題も行っている。このコンクールは、中学生から熟年者までいるマニアには有名なものだ。参加者には数学オリンピックという国際的なコンクールのゴールドメダリストが並ぶ。灘高生は流石に優秀だし、ときどき研究者も参加する。そういう人たちを喜ばせ惹きつける問題を作ることはそう易しくはない。
一般に問題作成法には簡単な方法がある。既成の問題の数値などを変えるだけで済む。しかしそういううものを入試問題に並べれば、丸暗記する人を優遇することになるし、大学の威信にかかわる。コンクール問題では未知なところを開拓しないと人を呼べない。それでも既知の知識を組み合わせて解かれることを想定している。だが専門の研究ではむろん、どこかで全く未知のことを扱わねばならない。主張のオリジナリティすなわち初めて論じられたという原初性が不可欠である。
さて僕は就職、冬ではなく夏の時代で、まったく成果を挙げぬうちに就職できた。いや当時は「一流大学」の教授でも、論文は最低数の人がざらにいたのだが。(その人達に何かで優れた人が何人もいたのも事実。先輩の教授の嗅覚で見つけていたのだろう。)就職して困ったことは、やはり技の習得が苦手なことだ。数学には大道具と言われるような大きな技術がある。九九を知らなければ算数はできないが、算数における九九のように定番の技術が、数学の大抵の分野にはある。だが数学の技術は九九よりも複雑である。例えば一つのアルファベットに4個ほどの数字が添字としてくっついているような記号を、いくつも操作しなければならないなど。覚えてなくても、最低そういうものがどういう関係にあるかを呑込まなばならない。その関係は抽象的な概念を束ねてさらに抽象するようなことを重ねている。すると記憶力がないことが響いてくる。それでも時代の研究水準をマスターしなければ、新しい結果は出せない。これで助手の数年間とても苦しんだ。友人たち、いや後輩たちも、次々論文を仕上げて巣立っていく。数学の論文というのは出版できればほぼ世界水準と言ってよい。ただしそういうものであっても、「純粋数学」であれば、大研究グループに属してない限り、身近な研究者以外の読者が10人を超えることもなかなか難しい。その代わり、優れたものは100年後でもビビッドに蘇ることがあるのはたしかにある。
既成の技術の習得が難しいとすれば、そういうものが必要でない問題を考えればよい。問題が新しければ解く方法も自分で作らねばならない。自分で作った方法は流石に頭にしっかり入るというわけだ。でも問題を見つけ出すことはさらに難しい。いろいろな分野をあれこれかじっても、いい問題にはたどり着けなかった。友人たちは大先生に食いつきやすい問題を頂いているからうまくいくのではないか、などとひがんだ。僕の親分も大先生で、数学のアイデアは豊富にあったと聞くが、それよりもいわば行政的な関心が強く、そういう活動のためか教室にもあまり現れない人であったから。
仕方がないので流行の数学を追うことを諦め、自分の実感のある易しい微積分などから素朴な問題を探すことにした。すると「特異点における関数の位数」という基本問題が見つかった。基本と言っても、どの分野の人も殆ど扱っていない問題である。この問題を得てはじめて、それまでにいろいろ齧ったことが生きてきた。それから長い年月をかけることによってこの問題を解決した。自己流と言っても、理解できぬことでも関心があれば聞くことだけはやめなかった。前に書いたように、それで初めて解決することができたのだ。
数学にはいろいろな予想があり、長い間解かれない。未だ未解決なものもある。そうした著名な難しい問題を解くことは素晴らしいことは言うまでもないが、そういう問題を発見することも優るとも劣らぬ大切なことであると思う。
広中平祐先生が似たことを言っておられる:
「AI(人工知能)やロボットが急速に進化、普及する新時代を迎えようとしています。そんな時代に人がやるべきこと、考えることは何か。それは問題をいかに早く、理路整然と解けるかではなく、面白い問題をどう作るかではないか。「問題作りのテスト」なんて面白いかもと思ったんです。」
「世の中には、天才や秀才と呼ばれる人がいますが、ほんの数パーセント。でも、社会を作っているのは、むしろそういう人たち以外の人々です。新時代を切り開いていく創造力は、知識だけから生まれるものでも、経験が豊富な人にだけ生まれるものでもない。自分の特性を発見し、じっくり育み、自分なりの形にしようと努める人が「創才」。誰もやったことのない事業やイベント、商い、問題を考えていく人づくりにつながる。」
([AI時代 人の強みは「発問力」] 2017/10/01付 西日本新聞朝刊)
AIで現在代表的なGPTは、ウィキペディアによると「生成可能な事前学習済み変換器」である。この事前学習は、ネットにある膨大な情報の学習である。問いかけがあれば、その情報をとても適切なコンテキストで並べて解答とする。適切なコンテキストで並べることにおいては、初期から並の大学生のレベルを超えているそうだ。ある先生曰く
「こんな文章、うちの学生にかけるはずがない。AIに決まってる。」
しかも普通の質問なら、あっという間に答えを出す。ただ学習した資料が最新とは限らないから out of date ということもあるようだ。
「大阪の住人ですが、東北のひなびた温泉を列車で3泊で回るプランを教えてください」
「膝の下に大きな瘤ができて、痛くはないのですがどうすればいいでしょうか」
なんて問いかけには、すぐそれなりの答えが出てくるだろう。ただ僕の数学に劣らぬ初等的なミスを犯すようだ。しかし一番の問題は、問題には答えるが、自ら良い問題を投げかけることができないのではないだろうか。そして思考法自体を反省したり、考察することはなおさら困難であろう。テレビで人気の物知り、パズル解きのようなものだ。言い回しが丁寧で適切でも、世知に長けているだけでは魅力がない。問題をつくるにせよ、解くにせよ、個々の事実に関する物知り知識はコンピュータに任せて、必要に応じて関係する知識や方法は、どういう方面に蓄えられているかという見取り図を持っていることが大切だと思う。
ところで自分が年を取って思うのだが、研究者に野生に富んだ人がやや少なくなったような気がする。広中さんも言っておられるし、僕の見てきた経験でも、本当は馬鹿なことを言えることが創造的人間の必要条件ではないか。よくできる研究者は、しばしば的外れたことを堂々と質問し、提案する。越境することをためらわない。数学と異なる実験系でも「失敗が斬新なアイデアをもたらす」というようなことが言われるが似たようなことだ。FBFの垂水さんの話を引用しよう。
垂水 源之介
《馬鹿な質問の効用について〜♪ (Facebook 2016年4月28日)》より引用:
僕は、医学研究科修士課程の第二期生だが、途中でドロップアウトした旧帝大の著名な物理学教室の出身の同級生が神経生理学かなにかの授業のなかで質問した「鯨は海に棲んでいるのになぜ塩辛く感じないのか?」という質問が忘れられない。僕は動物生態学を修めた理学士だったから、そんな疑問を想像したことがなかった。なんという馬鹿なんだという見下した気分だった。しかし、40年ちかくたって、その教授がどのような当意即妙な返事をしたのかという記憶がない。つまりきちんと応接できなくて、たぶん授業を先に進んだのだろう。つまりこの教訓は、物理学履修の学生の質問の奇矯さではなく、それにうまく応えられなかった教授の頓智や学問的想像力のなさだろう。いま、前者ではなく後者の業務を日々こなすなかで、そんなオモロイ質問をする奴もいなくなった。それゆにこそ、教授もほうも頓智応接のOJTに長けていない。学生の(一見)馬鹿な質問は、想像力を駆使する教授の商売に必要不可欠なアイディアと刺激の源泉だったのだ。それが失われた現在、今日の教授の新たな使命は、馬鹿でもいいので質問をしまくる学生の育成と、頓智とユーモアに満ちた教員の創成であることは謂うまでもない。
(引用ここまで)
ところでなぜ野生が薄れたのだろうか。僕が思う原因はこうだ。研究者の採用や昇格は平等でなければならない。そして異論が唱えられないためには、客観的尺度が必要になる。それが業績である。インパクト・ファクターの高い雑誌に何本の論文をのせたか。どれだけ引用されたか。そして揺るぎない知識や、確定した方法の適用の能力が計られる。こうしたことは正確になった。結果として、なんでも知っている、問題なく、すぐデキルことが重視されるようになった。でも、実際は守備範囲を逸脱し、驚いたり、疑問を感じたり、類似性を見出したりすることが新しい飛躍に導くのだ。
近大数学コンテストの話に戻るが、近年大学院生や学部生が上位を占めるようになってきたような気がする。初期には中学生がトップに立つなど、教育課程と成績がかなり独立していた。これは教育機関から見ると健全な現象であるが、秩序・序列ができるということはやはり気になることでもある。原因の一つは問題の性格が普通になったのではないかということ。もう一つは、大学生、大学院生には、問題解決型が増えているのではないかということが考えられる。
何処も、合理的選抜法や人事採用法が、AI的な能力を期待するようになってしまっていないだろうか。むろん馬鹿なことを言う人がかならず成功する訳では無いが、そういう人も生かしていかないと、整然とした味気ない世界になってしまう。この重要な馬鹿さというのは、現段階のAIの犯す幼稚なミスのようなものではない。条件を無視した思考法の拡大適用と言った「ごついアホ」でなければならない。類推がそういう思考拡大である。理の当然としてでてくる問題ではなく、人が呆れるような問題提起に飛躍の鍵がある。その価値を評価することも大切だ。
結論、問題発見や問題創作というのは、思考範囲を限定しないことによって可能になるのである。頭に嵌ったタガを外さないといけない。人間にもなかなかできないが、博識に頼るAIには原理的に難しそうに思う。problem solver というのは大事なことであるが、その前に problem finder が重要なのだ。今はますますそう思っている。 problem maker = trouble maker として敬遠されているのだろうが。














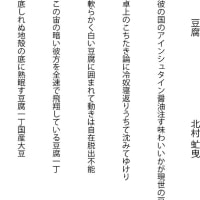
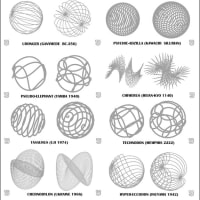












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます