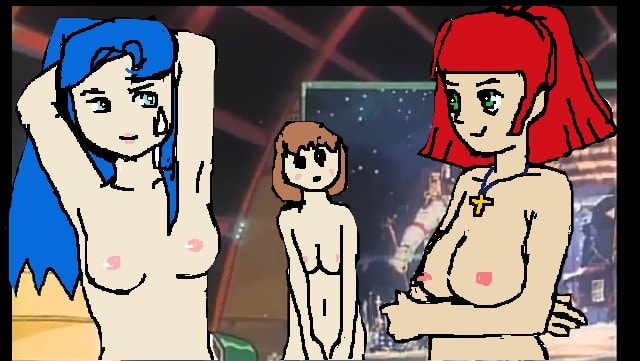
「トップをねらえ!(1988年)」あらためて全話見直したがやっぱり凄いや。この俺ですら、コレについて書き出すと何ギガバイトあっても足りない、印象深い作品だ。
今観ると確かに多量のおっぱい流出は苦笑せざるを得ないが、理由があることは明白であるし、それによって作品の質を計ることにはそぐわない。
今回はおっぱいの寡多による作品の評価の在り様について考えてみようと思う。
この作品が発表された当時、バブル景気は始まっていた。経済と共にエロもインフレーション(エロスパイラル)を起こし、その中の突出した現象として、おっぱいバブルがはじまった。よりパブリックな媒体であるべきテレビジョン放送がこれを先導し、どのチャンネルを回してもおっぱいおっぱいおっぱいと、おっぱいを文字どおり垂れ流した。これはエロビデオの普及に脅威を感じたテレビジョン放送がエロに迎合したこと、エロこそナウい、と考える層が作り手、受け手側に蔓延したことが原因である。
そんなエロスパイラルの真っ只中、この作品は発表された。
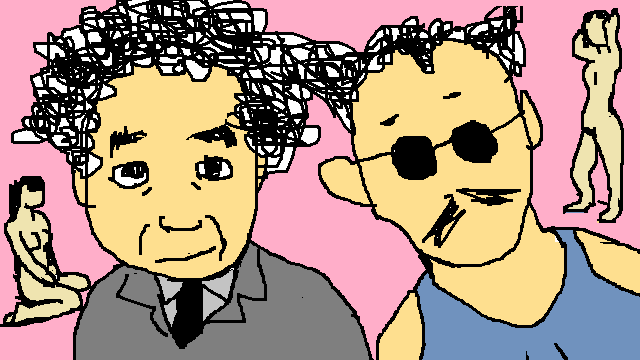
エロスパイラルを語るとき、メガネチョビヒゲが80年代前半から「写真時代」に掲載した一連の作品郡があったことも忘れてはならない。これらは猥褻と美の表現という古くて新しいテーマをナマのまま提示した。すぐに亜流が産まれ、追随者達がより過激なエロスを追求し、女体の神秘を探ることと芸術を極めることは同義であるというエロい考え方があらわれた。
その後、もじゃもじゃ頭が陰毛写真を手がけ、遂に国民的美少女タレントの「サンタフェ(1991年)」で、陰毛写真が国民から正式に認知されたのである(しかしながら陰毛バブルとでも呼ぶべきこのムーヴメントはココを頂点にゆるやかに収束してゆく)。
もじゃもじゃ頭は芸術家としての権威が高く、女性にもファンが多かった。そのため陰毛写真は女性陣から特に反発もされず、むしろ積極的に受け入れられた。おっぱいも陰毛も含めての女性らしさは人間らしさである、とゆうテーゼが確立され、エロと芸術の垣根は取り払われた。このとき男性陣はただ「おっぱいより凄いモノが出てきた」と無邪気に喜んだだけである。
当局はコレを黙認した。
これにより「女性らしさ」がエロい方向に拡大解釈される風潮は高まり、それは現在まで続いている(エロ可愛い、などとゆう価値観に昇華したのは記憶に新しいところである)。
この一連の騒動により「ビラビラしてなければお咎め無し」のお墨付きをマスコミは得、世論はこれを歓迎した。
当局が黙認せざるを得なかったのは、前述したメガネチョビヒゲが道をつけていたことと、当局自体が例外をいくつも認めていて、逆行することがすでに出来なくなっていたからである。それはサイレントマジョリティーをふくめた民意が得た勝利を意味していた。
つまりおっぱいバブルは「人間性という性を表現する」価値観、あるいは手法が変化していくエロい時代に起こるべくして起きた必然であり、時代の欲求であったといえる(世紀末的ルネッサンス)。
さて、そんなエロい最中に製作された「トップをねらえ!」へ立ち戻って考えてみる。YouTubeでの若いファンのコメントの多くもおっぱいにたいする幼児じみた感想でいっぱいであるが、間違いであると言わざるを得ない。それは乳首の露見が多いからそう感じるだけなのである。
より下である陰毛がフューチャーされていた当時、陰毛に拮抗するキャラとして、乳首はどうしても必要であった。
価値観の変換が行われる渦中にあり、新進の志のある「トップをねらえ!」の作画スタッフには、先っぽがアンバーに塗られたおっぱいが必須であったし、まだ公にはご法度であった陰毛さえも表現しようとした(読者の目で確かめてほしい)のは当たり前といえる。
おっぱいバブルは急激に膨らんだ、という意味ではバブルであったが、はじけるシャボンであったという意味ではない。今日おっぱいのレートは、おっぱいおっぱい言わなくても充足している状態で推移している。
おっぱいバブルはあるが、見えなくなっているだけなのである。あるいはバブルという単語がそぐわないほど成熟し、おっぱい信仰とも呼べる状況下にあるのが現在である。もし崩壊したと言うなら、おっぱいバブルの中の乳首バブルというイチ側面だけに限ってのことなのである。陰毛バブルがはじけた現在、あえて乳首を強調する必要はなくなった。現在の目で見てTooMachな感覚を受けるとすればそのためである。
しかしながら、より大きな房への欲求はむしろ高まっていることは説明の必要はないと思われる。
最先端のアニメであってもおっぱいに対する信望は厚い。あなたの好きな最先端アニメを思い出してみてほしい。その作品はおっぱい抜きで成り立ちますか?おっぱいの取り扱いだけをみて時代遅れの作品であると思うのは浅はかな考えなのである。むしろ、アニメーション作品において、おっぱいぷるーんぷるんのパイオニアとして長く記憶されるべき記念碑的作品、文字どおりの不朽の名作なのが本作品である。










