
今日は鉄道の話は少しお休みして、献血のお話など。
実は、今日はお仕事を休んで、お医者さんに行ってきました。
4月に痛めた左足が、未だに腫れが引かないのです、捻挫だと思うのですが少し不安に・・・・
足は、いためると辛いですね、今でも悲しいかな階段を下りる時は手すりがないと不安です。上りは大丈夫なんですけどね、それとエレベータも一人だとどうも遠慮してしまって。それが、余計に治りにくい原因なのかもしれませんが・・・・。汗
さてさて、肝心のお話なんですけど、京橋駅に降り立つと、京橋の駅前に献血のバスが止まっていました。
ふと、献血してみようかなと思ったのですが、以前献血したのが4月10日、400ML献血だったので、まだ無理。
横目で見ながら、すり抜けてきました。
家に帰ってから、献血の歴史などに興味があって、幣サイトを久々に更新するついでに調べてしまいました。笑
ということで、今日は鉄道とは全く関係ないけど、献血の話など。
献血以前
日本で献血制度が確立したのは、ずっと遅く、昭和39年8月だったそうな。
その発端はというと、医療関係者の方なら常識でしょうが、ライシャワー米国駐日大使刺傷事件(昭和39年3月24日)が発端となったわけで、この時に日本のお粗末な血液に関する実態などが暴露されたことが発端になったそうです。
それまでは、日本の血液は、売血という制度で支えられていたそうで、これは自身の血液を売って、それを金に換えていたそうで、文字通り命を削って・・・そんな表現がぴったりだったそうです。
ただし、血液といえば「赤い」というのが常識ですが、実際には赤いのは、「赤血球」の色素による色であり、血液には血小板、血漿、白血球で構成されていることは小学校か中学校で習ったことがあるので皆さんもよくご存知だと思います。
そのなかで、赤血球は一番戻るまでに時間がかかり、そのために400ML献血した場合は最低でも2ヶ月は空けないといけないそうです。
この辺は、献血センターの看護師さんたちからの受け売りなんですけどね。汗
当然、1回血を売っても2ヶ月以上たって売血すればさほど問題ではないのでしょうが、実際には売血を繰り返すといった事例が後を絶たなかったようです。
当然、赤血球が十分に戻らないままですから、血自体が黄色っぽくなるので「黄色い血液」として社会問題になったりしたそうです。
売血自体はよくないことなのですが、こうしなければ生活が出来ないそんな人たちもいたのです。
その辺は、明日以降にでも書いて行きたいと思います。
ちなみに、昭和39年3月 大阪環状線の西九条駅付近の高架が完成し、変則運転が解消したり、近鉄湯の山線が改軌(いずれも、ライシャワー事件の前日に当たる3/23)
等の記録が残されています。
実は、今日はお仕事を休んで、お医者さんに行ってきました。
4月に痛めた左足が、未だに腫れが引かないのです、捻挫だと思うのですが少し不安に・・・・
足は、いためると辛いですね、今でも悲しいかな階段を下りる時は手すりがないと不安です。上りは大丈夫なんですけどね、それとエレベータも一人だとどうも遠慮してしまって。それが、余計に治りにくい原因なのかもしれませんが・・・・。汗
さてさて、肝心のお話なんですけど、京橋駅に降り立つと、京橋の駅前に献血のバスが止まっていました。
ふと、献血してみようかなと思ったのですが、以前献血したのが4月10日、400ML献血だったので、まだ無理。
横目で見ながら、すり抜けてきました。
家に帰ってから、献血の歴史などに興味があって、幣サイトを久々に更新するついでに調べてしまいました。笑
ということで、今日は鉄道とは全く関係ないけど、献血の話など。
献血以前
日本で献血制度が確立したのは、ずっと遅く、昭和39年8月だったそうな。
その発端はというと、医療関係者の方なら常識でしょうが、ライシャワー米国駐日大使刺傷事件(昭和39年3月24日)が発端となったわけで、この時に日本のお粗末な血液に関する実態などが暴露されたことが発端になったそうです。
それまでは、日本の血液は、売血という制度で支えられていたそうで、これは自身の血液を売って、それを金に換えていたそうで、文字通り命を削って・・・そんな表現がぴったりだったそうです。
ただし、血液といえば「赤い」というのが常識ですが、実際には赤いのは、「赤血球」の色素による色であり、血液には血小板、血漿、白血球で構成されていることは小学校か中学校で習ったことがあるので皆さんもよくご存知だと思います。
そのなかで、赤血球は一番戻るまでに時間がかかり、そのために400ML献血した場合は最低でも2ヶ月は空けないといけないそうです。
この辺は、献血センターの看護師さんたちからの受け売りなんですけどね。汗
当然、1回血を売っても2ヶ月以上たって売血すればさほど問題ではないのでしょうが、実際には売血を繰り返すといった事例が後を絶たなかったようです。
当然、赤血球が十分に戻らないままですから、血自体が黄色っぽくなるので「黄色い血液」として社会問題になったりしたそうです。
売血自体はよくないことなのですが、こうしなければ生活が出来ないそんな人たちもいたのです。
その辺は、明日以降にでも書いて行きたいと思います。
ちなみに、昭和39年3月 大阪環状線の西九条駅付近の高架が完成し、変則運転が解消したり、近鉄湯の山線が改軌(いずれも、ライシャワー事件の前日に当たる3/23)
等の記録が残されています。










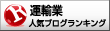
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます