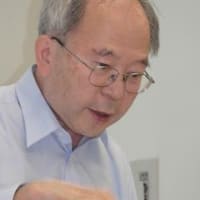写真: 北京で11、12日に行われた日朝協議で、北朝鮮側が日本人拉致問題の再調査を約束した=13日、政府の説明を受けた後、会見する拉致被害者家族会の飯塚繁雄代表(左)ら
参考資料として、記録
拉致問題解決へ2つの提言(中)
左右の対話の基礎は整っている--FujiSankei Business i. 2008/6/18
荒木和博氏(特定失踪(しっそう)者問題調査会代表・拓殖大学教授)は、なぜ拉致救出活動と政府は一体化すべきでないと主張するのであろうか。政府は抽象的存在ではなく、官僚と与党政治家によって運営されている。外交交渉を始めると、政府は「交渉をまとめたい」という欲望に取りつかれる。そのために国民の利益に照らして、不必要な過剰な譲歩をする可能性がある。
荒木氏は〈拉致問題は官僚には絶対に解決できない。もちろん、拉致問題を本気で解決しようとしている人は何人もいるが、官僚機構自体には根本的な方向性、真理とか道理というものがほとんど存在しない。省庁、あるいは官僚機構全体の中での整合性を維持しようとする動きがあるだけである。逆に言えば政治が明確な決断をすれば、官僚機構はそれに従って動くのである/その政治を動かすのは世論であり、運動体の目的はその世論を形成していくことにある〉(『諸君!』7月号)と述べる。筆者も荒木氏の認識が正しいと考える。
特に最近、日朝交渉が再び動き始めている状況で、世論形成の問題は死活的に重要だ。〈政府は13日、北京で11、12の両日行われた日朝の外務省実務者公式協議で、北朝鮮側が日本人拉致問題の再調査を約束し、日航機「よど号」ハイジャック事件関係者の日本への引き渡しに向けて調整することで合意したと発表した。日本側は見返りとして制裁を一部緩和し、人的交流やチャーター便の往来などを認める〉(6月13日asahi.com)。
日本政府が北朝鮮との本格的交渉に踏み切ろうとしていることは、間違いない。外務省は、このような状況において、世論の反応を注意深く観察する。その上で、どの程度の妥協が可能であるかの胸算用をするのだ。〈政府との間では建設的緊張関係を維持し、何よりその基本方針を「北朝鮮自身が拉致問題の解決に向けて具体的な行動を取るように求めていく」から「日本国政府の責務として拉致被害者を救出する」へと変えさせねばならない〉という荒木氏の戦略は正しい。繰り返しになるが、拉致問題は日本人の人権と日本国家の国権が侵害された事案で、これを解決できないようでは日本国家が存在する意味がない。
さて、『世界』7月号の「共同提言 対北対策の転換を」は、荒木氏の提言とは別の方向で、拉致問題の解決を図ろうとする。この「共同提言」を行った和田春樹東京大学名誉教授、高崎宗司津田塾大学教授、山口二郎北海道大学教授らは、北朝鮮に対して融和的で、拉致問題解決に不熱心であるという印象を右翼や保守陣営の一部から持たれているが、これは誤解である。「共同提案」では、拉致問題が北朝鮮による〈許されない事態〉であるという認識を明確にしている。
〈拉致問題などの犯罪 敵対と緊張の関係の中では不正常な、許されない事態が生じた。北朝鮮は日本の領海に工作船を送り込み、工作員を日本に侵入させ、情報収集をおこなった。工作船は正規のルートでは購入も販売もできない物資を調達し、持ち込むのにも使われた。そして1970年代の後半から80年代初めにかけては、韓国民主化運動の中に工作員をおくりこむために、必要な日本語教師の獲得、日本人名義のパスポートの取得、北朝鮮長期定住外国人のための伴侶(はんりょ)の獲得などの目的で、北朝鮮は日本で日本市民の拉致を行った。このような不祥事は停止され、謝罪がなされ、回復できる損害はすべて回復されなければならない。2002年北朝鮮の指導者は首脳会談の席上、日本の総理に対して、拉致と工作船の派遣の事実を認め、謝罪した。日朝平壌宣言には、「朝鮮民主主義人民共和国側は、日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な措置をとることを確認した」と述べられた。5人の原状回復が実現し、北朝鮮で生まれた家族も渡日した。拉致問題のなおのこる未解決な部分の解決が求められている〉(『世界』7月号)
過去のしがらみを超え、〈拉致問題のなおのこる未解決な部分の解決〉に向けてオールジャパンでの取り組みをすることが重要と思う。
「共同提言」では、〈2002年9月の平壌首脳会談で北朝鮮の指導者がおこない、13人を拉致し、うち8人が死亡し、5人が生存していると伝えた。さらに北朝鮮側は死亡したとされる8人については、2度の調査を行い、報告を日本側に提出した。しかし、この報告に対して日本側は多くの疑問を提起し、満足できる回答をえていない〉としつつも〈拉致問題の解決のために北朝鮮側はすでに基本的な認識、謝罪、将来への誓約をおこなっていることを認めなければならない〉という認識を示している。この認識には当然異論もあるだろう。それでも北朝鮮問題、拉致問題について左右の対話の基礎は十分整っていると筆者は考える。
参考資料として、記録
拉致問題解決へ2つの提言(中)
左右の対話の基礎は整っている--FujiSankei Business i. 2008/6/18
荒木和博氏(特定失踪(しっそう)者問題調査会代表・拓殖大学教授)は、なぜ拉致救出活動と政府は一体化すべきでないと主張するのであろうか。政府は抽象的存在ではなく、官僚と与党政治家によって運営されている。外交交渉を始めると、政府は「交渉をまとめたい」という欲望に取りつかれる。そのために国民の利益に照らして、不必要な過剰な譲歩をする可能性がある。
荒木氏は〈拉致問題は官僚には絶対に解決できない。もちろん、拉致問題を本気で解決しようとしている人は何人もいるが、官僚機構自体には根本的な方向性、真理とか道理というものがほとんど存在しない。省庁、あるいは官僚機構全体の中での整合性を維持しようとする動きがあるだけである。逆に言えば政治が明確な決断をすれば、官僚機構はそれに従って動くのである/その政治を動かすのは世論であり、運動体の目的はその世論を形成していくことにある〉(『諸君!』7月号)と述べる。筆者も荒木氏の認識が正しいと考える。
特に最近、日朝交渉が再び動き始めている状況で、世論形成の問題は死活的に重要だ。〈政府は13日、北京で11、12の両日行われた日朝の外務省実務者公式協議で、北朝鮮側が日本人拉致問題の再調査を約束し、日航機「よど号」ハイジャック事件関係者の日本への引き渡しに向けて調整することで合意したと発表した。日本側は見返りとして制裁を一部緩和し、人的交流やチャーター便の往来などを認める〉(6月13日asahi.com)。
日本政府が北朝鮮との本格的交渉に踏み切ろうとしていることは、間違いない。外務省は、このような状況において、世論の反応を注意深く観察する。その上で、どの程度の妥協が可能であるかの胸算用をするのだ。〈政府との間では建設的緊張関係を維持し、何よりその基本方針を「北朝鮮自身が拉致問題の解決に向けて具体的な行動を取るように求めていく」から「日本国政府の責務として拉致被害者を救出する」へと変えさせねばならない〉という荒木氏の戦略は正しい。繰り返しになるが、拉致問題は日本人の人権と日本国家の国権が侵害された事案で、これを解決できないようでは日本国家が存在する意味がない。
さて、『世界』7月号の「共同提言 対北対策の転換を」は、荒木氏の提言とは別の方向で、拉致問題の解決を図ろうとする。この「共同提言」を行った和田春樹東京大学名誉教授、高崎宗司津田塾大学教授、山口二郎北海道大学教授らは、北朝鮮に対して融和的で、拉致問題解決に不熱心であるという印象を右翼や保守陣営の一部から持たれているが、これは誤解である。「共同提案」では、拉致問題が北朝鮮による〈許されない事態〉であるという認識を明確にしている。
〈拉致問題などの犯罪 敵対と緊張の関係の中では不正常な、許されない事態が生じた。北朝鮮は日本の領海に工作船を送り込み、工作員を日本に侵入させ、情報収集をおこなった。工作船は正規のルートでは購入も販売もできない物資を調達し、持ち込むのにも使われた。そして1970年代の後半から80年代初めにかけては、韓国民主化運動の中に工作員をおくりこむために、必要な日本語教師の獲得、日本人名義のパスポートの取得、北朝鮮長期定住外国人のための伴侶(はんりょ)の獲得などの目的で、北朝鮮は日本で日本市民の拉致を行った。このような不祥事は停止され、謝罪がなされ、回復できる損害はすべて回復されなければならない。2002年北朝鮮の指導者は首脳会談の席上、日本の総理に対して、拉致と工作船の派遣の事実を認め、謝罪した。日朝平壌宣言には、「朝鮮民主主義人民共和国側は、日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な措置をとることを確認した」と述べられた。5人の原状回復が実現し、北朝鮮で生まれた家族も渡日した。拉致問題のなおのこる未解決な部分の解決が求められている〉(『世界』7月号)
過去のしがらみを超え、〈拉致問題のなおのこる未解決な部分の解決〉に向けてオールジャパンでの取り組みをすることが重要と思う。
「共同提言」では、〈2002年9月の平壌首脳会談で北朝鮮の指導者がおこない、13人を拉致し、うち8人が死亡し、5人が生存していると伝えた。さらに北朝鮮側は死亡したとされる8人については、2度の調査を行い、報告を日本側に提出した。しかし、この報告に対して日本側は多くの疑問を提起し、満足できる回答をえていない〉としつつも〈拉致問題の解決のために北朝鮮側はすでに基本的な認識、謝罪、将来への誓約をおこなっていることを認めなければならない〉という認識を示している。この認識には当然異論もあるだろう。それでも北朝鮮問題、拉致問題について左右の対話の基礎は十分整っていると筆者は考える。