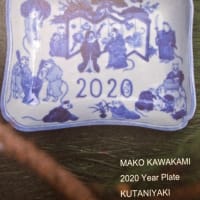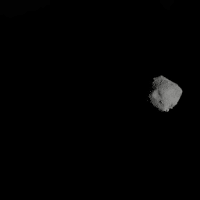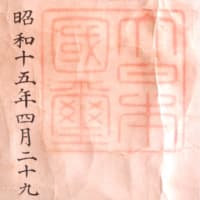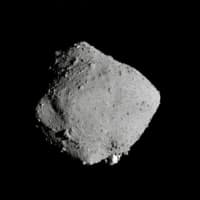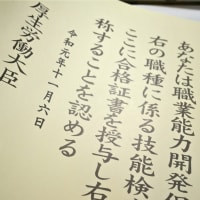「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」という「土佐日記」の冒頭があまりに有名過ぎて、そういうものとしてやり過ごしていたのだけど、当時のいわゆる「男もすなる日記」っていうのが具体的にどんなものだったのか?ついぞ一度も読んだことがないぞと。ふと気づいた。
このあたりが、少々めんどくさいことになっているのだけど、筆者は紀貫之なので、「結局、男が書いてんじゃん!」って、そういえば、中学生の時にみんなでツっこんでた気がするのだが、そのツッコミは今思い出しても、まことに正しい( ・ิω・ิ)b
考えてみると、「日記」を書くにあたり、わざわざ「敢えてこれを書く理由」を冒頭に冠する必要があるということを、当時は想像さえしなかったが、この「日記」は最初から誰か読ませる相手が想定されている、ということなのだろうか?さらには、「非公式文書」であることを最初から明示しておく必要があった、とか?
「わたし」が書いてしまうと、いろいろ「公式」なことになってしまうので、これは「わたし」が書いたものではないですよと、「非公式」であることをまずは「宣言」しておく必要があった。
だとするなら、やっぱり、読まれることが前提なんだな(*‘ω‘ *)
では、わざわざ「女」になったのには、どんな理由があったのだろう?
ここがいまいちよく分からない。
「わたし」が書いたものではないとするのに、わざわざ「女」になってみせる理由。
紀貫之本人でなくても、「男」が書いてしまったことになると、たいして重要な内容を書いていなくても、後々、なにか不都合なことにつながってしまう、とか?そこから変にオオゴトに発展してしまったり、とか?「日記」と銘打っただけで、そういう危険が想定され得るということだったのだろうか?
だとするなら、そもそも、そんな「日記」を残しておくこと自体が危険だ。やめておきなさい!って思う。
いつの時代であっても、感情の発露が理由で危険を呼ぶことがなかったわけではないけれど、こと日本においては天皇陛下から庶民に至るまで、和歌を詠むこと、これがあたりまえだった。「歌」っていうことにして、結構、なんでもかんでも発言していらっしゃいますよね、皆さん(^o^;)
そして、どういうわけか、和歌については驚くほど寛容。ある形式の下において、発言は詩的かつ自由。
自由な発言は詩的であれ!
紀貫之は当代きっての和歌の達人。「土佐日記」にあらわれる数々のシーンを詠じてみせるなどお手のものだったに違いないのだが、これを敢えて「日記」に書く理由。これがなかなかに思いつかないのである。
実際はとてもシンプルな理由だったんじゃないかな?と思うのだ。
つまり、「男」と「女」が逆だったのではないか?
これだと、わりとすんなり腑に落ちる。
「女」の人がやっていた「日記」を紀貫之が読んで、このスタイルは面白いということで、実際に書いてみた。そしたら、結構、いい調子で書ける。
先行する文章スタイルのモデルというか雛形があって、すでに「女」の人による「日記」がさかんに書かれていたのではないか?
もしそうだとすると、「土佐日記」冒頭の書き出しは「男」と「女」を入れ替えて読む必要があるのでは?
「女がすなる日記といふものを、男もしてみむとてするなり」
こうした方が、なんかすんなり腑に落ちる(*^ω^)v
「土佐日記」が「日本最古の日記」と呼ばれてしまうのは、紀貫之が書いてしまった文書がことごとく「公式文書」として扱われ、きちんと保存管理されていたから。。。ということなんじゃないのかな(*‘ω‘ *)?
仕事でもないのに、いや、仕事じゃないから、「女」の人の方が、思ってしまったことを、マメにいろいろ書きつけてそうだし。
後世、傑作と言われる「日記文学」のことごとくが「女」の人の筆による。これは決定的な根拠にはならないのだろうか?
「女」の人のレベルの高い「日記」を社会の表舞台に押し上げる役目を、紀貫之が果たしたのだとしたら?
僕の手元に確かな証拠があるわけではない。だけど、ただ単に興に乗って書いてしまったというよりも、その方がよっぽど「紀貫之」らしいように思える。
ホントのところはどうなんでしょ(*‘ω‘ *)?
これはそもそも「日記」という概念の問題なのではないか?
そんなことを以前に考えていたことがある。以前と言っても、学生の頃なので、今は昔っていうくらい古くなった思いつきの話なんだけど、これをまた急に思い出した。
そもそもが「公式文書」だった「日記」。
この概念を思いっきり拡張してみたという。
「女」の人が書く「文章」も、これは「日記」である、と。
この「日記」の再定義が果たしたことは、改めて考え直してみるべきだと思う。
実は想像を絶するレベルで、文化的影響を及ぼしているように見えてきてしまうはずである。
「土佐日記」以前を想像することはなかなかに難しいのだが、「土佐日記」以降、明らかに景色が変わったのだ。そういう意味で、「土佐日記」は記念碑的な作品なのではないかと。
このあたりが、少々めんどくさいことになっているのだけど、筆者は紀貫之なので、「結局、男が書いてんじゃん!」って、そういえば、中学生の時にみんなでツっこんでた気がするのだが、そのツッコミは今思い出しても、まことに正しい( ・ิω・ิ)b
考えてみると、「日記」を書くにあたり、わざわざ「敢えてこれを書く理由」を冒頭に冠する必要があるということを、当時は想像さえしなかったが、この「日記」は最初から誰か読ませる相手が想定されている、ということなのだろうか?さらには、「非公式文書」であることを最初から明示しておく必要があった、とか?
「わたし」が書いてしまうと、いろいろ「公式」なことになってしまうので、これは「わたし」が書いたものではないですよと、「非公式」であることをまずは「宣言」しておく必要があった。
だとするなら、やっぱり、読まれることが前提なんだな(*‘ω‘ *)
では、わざわざ「女」になったのには、どんな理由があったのだろう?
ここがいまいちよく分からない。
「わたし」が書いたものではないとするのに、わざわざ「女」になってみせる理由。
紀貫之本人でなくても、「男」が書いてしまったことになると、たいして重要な内容を書いていなくても、後々、なにか不都合なことにつながってしまう、とか?そこから変にオオゴトに発展してしまったり、とか?「日記」と銘打っただけで、そういう危険が想定され得るということだったのだろうか?
だとするなら、そもそも、そんな「日記」を残しておくこと自体が危険だ。やめておきなさい!って思う。
いつの時代であっても、感情の発露が理由で危険を呼ぶことがなかったわけではないけれど、こと日本においては天皇陛下から庶民に至るまで、和歌を詠むこと、これがあたりまえだった。「歌」っていうことにして、結構、なんでもかんでも発言していらっしゃいますよね、皆さん(^o^;)
そして、どういうわけか、和歌については驚くほど寛容。ある形式の下において、発言は詩的かつ自由。
自由な発言は詩的であれ!
紀貫之は当代きっての和歌の達人。「土佐日記」にあらわれる数々のシーンを詠じてみせるなどお手のものだったに違いないのだが、これを敢えて「日記」に書く理由。これがなかなかに思いつかないのである。
実際はとてもシンプルな理由だったんじゃないかな?と思うのだ。
つまり、「男」と「女」が逆だったのではないか?
これだと、わりとすんなり腑に落ちる。
「女」の人がやっていた「日記」を紀貫之が読んで、このスタイルは面白いということで、実際に書いてみた。そしたら、結構、いい調子で書ける。
先行する文章スタイルのモデルというか雛形があって、すでに「女」の人による「日記」がさかんに書かれていたのではないか?
もしそうだとすると、「土佐日記」冒頭の書き出しは「男」と「女」を入れ替えて読む必要があるのでは?
「女がすなる日記といふものを、男もしてみむとてするなり」
こうした方が、なんかすんなり腑に落ちる(*^ω^)v
「土佐日記」が「日本最古の日記」と呼ばれてしまうのは、紀貫之が書いてしまった文書がことごとく「公式文書」として扱われ、きちんと保存管理されていたから。。。ということなんじゃないのかな(*‘ω‘ *)?
仕事でもないのに、いや、仕事じゃないから、「女」の人の方が、思ってしまったことを、マメにいろいろ書きつけてそうだし。
後世、傑作と言われる「日記文学」のことごとくが「女」の人の筆による。これは決定的な根拠にはならないのだろうか?
「女」の人のレベルの高い「日記」を社会の表舞台に押し上げる役目を、紀貫之が果たしたのだとしたら?
僕の手元に確かな証拠があるわけではない。だけど、ただ単に興に乗って書いてしまったというよりも、その方がよっぽど「紀貫之」らしいように思える。
ホントのところはどうなんでしょ(*‘ω‘ *)?
これはそもそも「日記」という概念の問題なのではないか?
そんなことを以前に考えていたことがある。以前と言っても、学生の頃なので、今は昔っていうくらい古くなった思いつきの話なんだけど、これをまた急に思い出した。
そもそもが「公式文書」だった「日記」。
この概念を思いっきり拡張してみたという。
「女」の人が書く「文章」も、これは「日記」である、と。
この「日記」の再定義が果たしたことは、改めて考え直してみるべきだと思う。
実は想像を絶するレベルで、文化的影響を及ぼしているように見えてきてしまうはずである。
「土佐日記」以前を想像することはなかなかに難しいのだが、「土佐日記」以降、明らかに景色が変わったのだ。そういう意味で、「土佐日記」は記念碑的な作品なのではないかと。