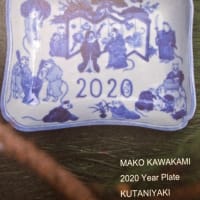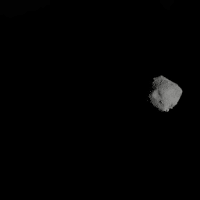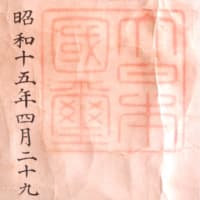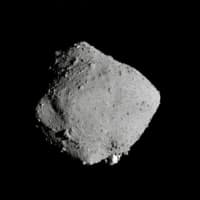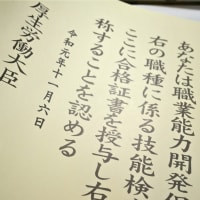「贄持」「井氷鹿」「岩押分」。このあたりはエヴァをイメージさせるのと同時に「碇」を古事記に結びつけるに強力な要素があると考えています。以下は鈴木三重吉による「古事記物語」からの抜粋。
命(みこと)はそのからすがつれて行くとおりに、
あとについてお進みになりますと、
やがて大和の吉野河の河口へお着きになりました。
そうするとそこにやなをかけて魚をとっているものがおりました。
「おまえはだれだ」とおたずねになりますと、
「私はこの国の神で、名は贄持(にえもち)の子と申します」
とお答え申しました。
それから、なお進んでおいでになりますと、
今度はおしりにしっぽのついている人間が、
井戸の中から出て来ました。そしてその井戸がぴかぴか光りました。
「おまえは何者か」とおたずねになりますと、
「私はこの国の神で井冰鹿(いひか)と申すものでございます」
とお答えいたしました。
命はそれらの者を、いちいちお供におつれになって、
そこから山の中を分けていらっしゃいますと、
またしっぽのある人にお会いになりました。
この者は岩をおし分けて出て来たのでした。
「おまえはだれか」とお聞きになりますと、
「わたしはこの国の神で、名は石押分(いわおしわけ)の子と申します。
ただいま、大空の神のご子孫がおいでになると承りまして、
お供に加えていただきにあがりましたのでございます」
と申しあげました。
神武天皇が八咫烏に導かれて熊野を進み吉野に抜けるあたりの場面ですが、同じようなカタチで3人の神様に出会います。
「贄持の子」は鵜飼の始祖であるという説は「日本書紀」では苞苴擔と書かれて紹介されています。鵜飼=エヴァ?いやいや、案外いけそうなイメージです。この際、鵜匠は誰か?というところに想像がいきそうになります。「鵜飼」の「鵜」のイメージはTV版でもはじめの方の話ではよりリアルなんじゃないか?と思いますが、字のイメージというか、劇場版にいたるまでの経緯を見ていると、最終的に「贄」「生け贄」としてのイメージに重ねる方がエヴァの場合は自然な流れかも。「綾波レイ」とか。ひょっとしたら、「シンジ」くんは創世記に描かれる「イサク」のイメージも背負っていて、息子をエヴァの物語にあっさりと捧げてしまった「父」「碇ゲンドウ」は「イサク」を神に捧げようとする「アブラハム」のイメージにはまっちゃうのかも。。。けれど、あんまり大きく展開しちゃうと収拾つかなくなるので、それはどこか別のところで、ジャック・デリダの「死を与える」を絡めつつやれたらいいな。
どちらにしても、「父」「子」の話は精神分析的な話からは近いようで遠いところ、神話の舞台そのものの上で構成されているような気がするのですが、今は古事記に見られる「碇」のイメージをもう少し追いかけてみます。
「井氷鹿」(いひか)。。。詳しいことはよく分からないのですが、「ぴかぴか光る井戸」というのは「水銀」の鉱脈に関係があると見るのが、一般的な説です。そこから尾のついた人が出てくる。「日本書紀」では「至吉野時、有人出自井中。光而有尾。天皇問之曰、汝何人。對曰、臣是國神。名爲井光」とされていて、光っているのは「井戸」ではなくて「尾」や「人」そのもの、ということになっています。吉野にある井光神社は「いかり」と読ませていますし、そこから派生した「碇」神社は各地に点在しますから、「光る巨人」の「光る」の部分に「碇」の匂いを確かめることができます。
「岩押分」にも「尾」がついているのですが、詳細は不明です。でも、エヴァに連なるイメージだけを追いかけているので、ここでは説明は要らないような気もしています。
神武天皇はこの三人のふしぎな神様と出会った後に天下を平らげ、橿原の宮で即位することになるのですから、詳細は分からなくても無視できない出会いであったことは「記紀」から伺えます。
「おしりにしっぽのついている(光る)人が井戸の中を通って岩を押し分け現れる」というイメージを、アンビリカル・ケーブルにつながれてシャフトで第三新東京市にリフトオフされるエヴァのイメージに重ねるのって、そんなに飛躍していないんじゃ?とも思う。
エヴァのイメージには、葛城山の一言主神も貢献していると思われる節があるのですが、それは後段にまわすことにして、ここでは三つのイメージを取上げて、それが「エヴァ」の要素を作っている可能性と「碇」という名前が関わっているということを指摘するにとどめておこうかと思います。
とりあえず「碇」についてはひと通り思いつくことはさらったと思うのですが、まだ「ゲンドウ」の部分が残されています。
ここでは多少の「こじつけ」が許されるものとして語っているのですが、任意の引用や思いつきではなくて、ある種の必然性の線を追いかけているつもりです。イメージを「二重」、またはそれ以上に重ねることができる、というのが採用ルール。学問的、歴史的に「真」とされているか、否か?ではなくて、「エヴァ」の環境設定に貢献しているであろうと思われることに「必然性」を見ているつもりです。
直截に「矢野玄道(やのはるみち)」=「ゲンドウ」と言い切って、それでおしまい!っていう風にしたい。。。けれど、「エヴァ」を見直してみたら、なんだかそうはできないんじゃないか?って思いました。理由があります。サラッと借用しただけにしては、あまりにも「考え抜かれている」ように読み取れるからです。国学とひとこと言ってしまうと、本居宣長や賀茂真淵、荷田春満(かだのあずままろ)にまで遡ることを考えて。。。なんて、ちょっと途方に暮れてしまいそうです。
でも、ここで「ゲンドウ」の参照元ととりあえず見当をつけている矢野「玄道」という人に触れるにも、そこに至るまでの「平田学派」の流れというか、歴史にまで考察がおよんでいると考えられる節がある。偶然に「ゲンドウ」というネーミングができるものか???いやいや、どう考えてもムリです。考え抜いていなければ、普通、そういう発想は浮かばないものです。もし、これを偶然とか、思いつきとか言わなければいけないのだとしたら。。。なんだかよくわからないけど、予防線を張らなければいけない相手がいるのかもしれません。。。よねぇ。
普通に考えたら「平田篤胤」の考えていたことが、「エヴァ」の世界観に近いような気がする。それには「霊能真柱」(たまのまはしら)という平田篤胤の著作を引き合いに出した方がイメージとして伝わりやすい。「画」で表現することが前提のアニメにあっては、平田篤胤が描いた「画」は「セントラルドグマ」や劇場版「Air/まごころを、君に」のラストを描く上で、この上なく参考になったんじゃないか?と思われるからです。
「Air/まごころを、君に」のタイトルにも、ドキッとします。もし、「平田篤胤」の描いた宇宙論というか天地創造(普通は天地開闢)を逆さまに辿ることが「サードインパクト」なのだとしたら、「ゲンドウ」を入り口にして平田篤胤の天地開闢を遡っていくと、そのたどり着く先にある「まごころ」は、本居宣長の思想の核心部分に迫る非常に大事なキーワードだからです。ここではキャラクターのネーミングを分析して、「エヴァ」が展開させている作品世界がいったいどういうところにつながっているのかを探っているわけですが、本当はこのあたりで小林秀雄を引っ張りだして、あれこれ考えたい部分ではあります。
でも、「まごころ」「霊能真柱」「ゲンドウ」と揃えば、ちょっと知っている人なら、必ず同じところにたどり着くはずの明確な「タグ」。これを聞いて間違える人は、そうそういません。
問題なのは、その描かれ方なのですが、恐ろしく広範な資料に目を通しているとしか考えられない。入り口はラフカディオ・ハーンか?と思われるのですが、アーネスト・サトウの報告書や古事記研究の第一人者バジル・ホール・チェンバレンの著作にも目を通している節がある。う~ん、違うのかなぁ?
「エヴァ」を製作した人たちの頭の中には、近世から近代に移り変わるころの幕末の日本が「外国」からどう見られていたのかについて、情報収集してあるだけじゃなくて、そこにある種の価値判断を下し終えているんじゃないか?って思われる節がある。いやいや、とぼけてもらっても困るんです。おそろしいほど読み込んでいなければ、難しい理解だし、これを「思いつき」でやりましたなんて、そっちの方がSF。でなければ化けものばりの天才っていうことになっちゃうんですよ。。。そうなの?ちがうでしょう?ちゃんと資料を読み込んだでしょう?。。。って、思うのです。
普通の意味で「自作を語りすぎるといけない」っていうのはわかるんだけど、なんだかいろいろ警戒し過ぎというか。。。実際に大変なことでもあったのかなぁ?って、変な深読みをしてしまうのだけど。。。
というわけで、次回は「霊能真柱」について、ちょこっとだけご紹介できればいいなぁって考えています。
エヴァンゲリオン/体験
エヴァンゲリオン/体験(2)
エヴァンゲリオン/体験(3)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(1)
命(みこと)はそのからすがつれて行くとおりに、
あとについてお進みになりますと、
やがて大和の吉野河の河口へお着きになりました。
そうするとそこにやなをかけて魚をとっているものがおりました。
「おまえはだれだ」とおたずねになりますと、
「私はこの国の神で、名は贄持(にえもち)の子と申します」
とお答え申しました。
それから、なお進んでおいでになりますと、
今度はおしりにしっぽのついている人間が、
井戸の中から出て来ました。そしてその井戸がぴかぴか光りました。
「おまえは何者か」とおたずねになりますと、
「私はこの国の神で井冰鹿(いひか)と申すものでございます」
とお答えいたしました。
命はそれらの者を、いちいちお供におつれになって、
そこから山の中を分けていらっしゃいますと、
またしっぽのある人にお会いになりました。
この者は岩をおし分けて出て来たのでした。
「おまえはだれか」とお聞きになりますと、
「わたしはこの国の神で、名は石押分(いわおしわけ)の子と申します。
ただいま、大空の神のご子孫がおいでになると承りまして、
お供に加えていただきにあがりましたのでございます」
と申しあげました。
神武天皇が八咫烏に導かれて熊野を進み吉野に抜けるあたりの場面ですが、同じようなカタチで3人の神様に出会います。
「贄持の子」は鵜飼の始祖であるという説は「日本書紀」では苞苴擔と書かれて紹介されています。鵜飼=エヴァ?いやいや、案外いけそうなイメージです。この際、鵜匠は誰か?というところに想像がいきそうになります。「鵜飼」の「鵜」のイメージはTV版でもはじめの方の話ではよりリアルなんじゃないか?と思いますが、字のイメージというか、劇場版にいたるまでの経緯を見ていると、最終的に「贄」「生け贄」としてのイメージに重ねる方がエヴァの場合は自然な流れかも。「綾波レイ」とか。ひょっとしたら、「シンジ」くんは創世記に描かれる「イサク」のイメージも背負っていて、息子をエヴァの物語にあっさりと捧げてしまった「父」「碇ゲンドウ」は「イサク」を神に捧げようとする「アブラハム」のイメージにはまっちゃうのかも。。。けれど、あんまり大きく展開しちゃうと収拾つかなくなるので、それはどこか別のところで、ジャック・デリダの「死を与える」を絡めつつやれたらいいな。
どちらにしても、「父」「子」の話は精神分析的な話からは近いようで遠いところ、神話の舞台そのものの上で構成されているような気がするのですが、今は古事記に見られる「碇」のイメージをもう少し追いかけてみます。
「井氷鹿」(いひか)。。。詳しいことはよく分からないのですが、「ぴかぴか光る井戸」というのは「水銀」の鉱脈に関係があると見るのが、一般的な説です。そこから尾のついた人が出てくる。「日本書紀」では「至吉野時、有人出自井中。光而有尾。天皇問之曰、汝何人。對曰、臣是國神。名爲井光」とされていて、光っているのは「井戸」ではなくて「尾」や「人」そのもの、ということになっています。吉野にある井光神社は「いかり」と読ませていますし、そこから派生した「碇」神社は各地に点在しますから、「光る巨人」の「光る」の部分に「碇」の匂いを確かめることができます。
「岩押分」にも「尾」がついているのですが、詳細は不明です。でも、エヴァに連なるイメージだけを追いかけているので、ここでは説明は要らないような気もしています。
神武天皇はこの三人のふしぎな神様と出会った後に天下を平らげ、橿原の宮で即位することになるのですから、詳細は分からなくても無視できない出会いであったことは「記紀」から伺えます。
「おしりにしっぽのついている(光る)人が井戸の中を通って岩を押し分け現れる」というイメージを、アンビリカル・ケーブルにつながれてシャフトで第三新東京市にリフトオフされるエヴァのイメージに重ねるのって、そんなに飛躍していないんじゃ?とも思う。
エヴァのイメージには、葛城山の一言主神も貢献していると思われる節があるのですが、それは後段にまわすことにして、ここでは三つのイメージを取上げて、それが「エヴァ」の要素を作っている可能性と「碇」という名前が関わっているということを指摘するにとどめておこうかと思います。
とりあえず「碇」についてはひと通り思いつくことはさらったと思うのですが、まだ「ゲンドウ」の部分が残されています。
ここでは多少の「こじつけ」が許されるものとして語っているのですが、任意の引用や思いつきではなくて、ある種の必然性の線を追いかけているつもりです。イメージを「二重」、またはそれ以上に重ねることができる、というのが採用ルール。学問的、歴史的に「真」とされているか、否か?ではなくて、「エヴァ」の環境設定に貢献しているであろうと思われることに「必然性」を見ているつもりです。
直截に「矢野玄道(やのはるみち)」=「ゲンドウ」と言い切って、それでおしまい!っていう風にしたい。。。けれど、「エヴァ」を見直してみたら、なんだかそうはできないんじゃないか?って思いました。理由があります。サラッと借用しただけにしては、あまりにも「考え抜かれている」ように読み取れるからです。国学とひとこと言ってしまうと、本居宣長や賀茂真淵、荷田春満(かだのあずままろ)にまで遡ることを考えて。。。なんて、ちょっと途方に暮れてしまいそうです。
でも、ここで「ゲンドウ」の参照元ととりあえず見当をつけている矢野「玄道」という人に触れるにも、そこに至るまでの「平田学派」の流れというか、歴史にまで考察がおよんでいると考えられる節がある。偶然に「ゲンドウ」というネーミングができるものか???いやいや、どう考えてもムリです。考え抜いていなければ、普通、そういう発想は浮かばないものです。もし、これを偶然とか、思いつきとか言わなければいけないのだとしたら。。。なんだかよくわからないけど、予防線を張らなければいけない相手がいるのかもしれません。。。よねぇ。
普通に考えたら「平田篤胤」の考えていたことが、「エヴァ」の世界観に近いような気がする。それには「霊能真柱」(たまのまはしら)という平田篤胤の著作を引き合いに出した方がイメージとして伝わりやすい。「画」で表現することが前提のアニメにあっては、平田篤胤が描いた「画」は「セントラルドグマ」や劇場版「Air/まごころを、君に」のラストを描く上で、この上なく参考になったんじゃないか?と思われるからです。
「Air/まごころを、君に」のタイトルにも、ドキッとします。もし、「平田篤胤」の描いた宇宙論というか天地創造(普通は天地開闢)を逆さまに辿ることが「サードインパクト」なのだとしたら、「ゲンドウ」を入り口にして平田篤胤の天地開闢を遡っていくと、そのたどり着く先にある「まごころ」は、本居宣長の思想の核心部分に迫る非常に大事なキーワードだからです。ここではキャラクターのネーミングを分析して、「エヴァ」が展開させている作品世界がいったいどういうところにつながっているのかを探っているわけですが、本当はこのあたりで小林秀雄を引っ張りだして、あれこれ考えたい部分ではあります。
でも、「まごころ」「霊能真柱」「ゲンドウ」と揃えば、ちょっと知っている人なら、必ず同じところにたどり着くはずの明確な「タグ」。これを聞いて間違える人は、そうそういません。
問題なのは、その描かれ方なのですが、恐ろしく広範な資料に目を通しているとしか考えられない。入り口はラフカディオ・ハーンか?と思われるのですが、アーネスト・サトウの報告書や古事記研究の第一人者バジル・ホール・チェンバレンの著作にも目を通している節がある。う~ん、違うのかなぁ?
「エヴァ」を製作した人たちの頭の中には、近世から近代に移り変わるころの幕末の日本が「外国」からどう見られていたのかについて、情報収集してあるだけじゃなくて、そこにある種の価値判断を下し終えているんじゃないか?って思われる節がある。いやいや、とぼけてもらっても困るんです。おそろしいほど読み込んでいなければ、難しい理解だし、これを「思いつき」でやりましたなんて、そっちの方がSF。でなければ化けものばりの天才っていうことになっちゃうんですよ。。。そうなの?ちがうでしょう?ちゃんと資料を読み込んだでしょう?。。。って、思うのです。
普通の意味で「自作を語りすぎるといけない」っていうのはわかるんだけど、なんだかいろいろ警戒し過ぎというか。。。実際に大変なことでもあったのかなぁ?って、変な深読みをしてしまうのだけど。。。
というわけで、次回は「霊能真柱」について、ちょこっとだけご紹介できればいいなぁって考えています。
エヴァンゲリオン/体験
エヴァンゲリオン/体験(2)
エヴァンゲリオン/体験(3)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(1)