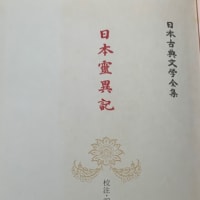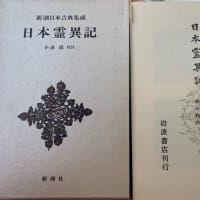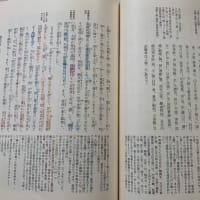大祓式の行われる斎庭です。

注連縄で結界が張ってあります。
去年は本殿に向かって右側の場所でしたが
今年は左側になっていました。
写真でもわかるかと思いますが
新しい建物で
木の香りがさわやかでした。
祭壇です。

三方に載っている奉書包みは、
大祓式で神職たちが祓えに用いる、
祓串、麻幣、切り幣、ヒトガタの
祓えセット一式が入っていたようでした。
ちなみに、三方が載っている台は
八足とか八足案、八脚案といいます。
神事の際に、神饌(シンセン、供え物のことです)
などを乗せたり、
祭壇のように使われたりします。
穢れを移したヒトガタを納める辛櫃です。

箱の周りにも注連縄巻いてあります。
やっぱり、穢れのものを納める箱なので
厳重ですね。
大祓の式の最中にカメラを向けるのも
憚られたので、
大祓式次第を以下に書きます。
ちょっと時間が経って、
記憶が定かでないところもありますが…
概ねこんな進行だったということで。
1.
無言で神職たちが斎庭に参入し、
それぞれの床几に座る
2.
神職の一人が祭壇へ歩み、お供えしてある
奉書包みをとって、懐へ入れる
3.
その後、残りの神職もそれぞれ包みを受け取り
懐に入れる。
4.
斎主、歩み出て、大祓詞を奏上
5.
奏上後、二人の神職が歩み出て葛籠を開ける
6.
続いて、それぞれの懐の奉書包みを開けて、
小さな祓串(白い紐のようなものを束ねて
木につけてある、お祓いでシャっ〜シャっ〜
と振るアレです)で、自分をお祓い。
切り幣(紙や麻を小さく、細かい四角に切った
もの、紙吹雪みたいな感じのものです)を
自分にかけて、さらにお祓い。
ヒトガタに息を吹きかけ、身体を撫でて
穢れを移す。
7.
それぞれで、
穢れを移したヒトガタを辛櫃に入れる。
8.
斎主が祭壇にある大幣
(おおぬさ、祓串の大きなもの)を持って
各方向を向いて振り、修祓。
修祓:しゅばつ、榊の枝に麻や紙垂(しで)を
付けた道具を、左右左と振ってお祓いする
9.
2人の神職が歩み出て、八足の上にある
白い布を取り、八つに割く。
八針神事というものかと思います。
大祓の祝詞に
天津菅麻を本刈り断ち末刈り切りて
八針に取裂きて
天津祝詞の太祝詞事を宣れ。
あまつすがそをもとかりたちすえかりきりて
やはりにとりさきて
あまつのりとのふとのりとごとをのれ
という箇所があります。
その八針に取りさきて
というのを祓えの所作として、行っているのが
木綿や麻の白い布を裂く、という所作ではないか
と言われています。
10.
ヒトガタを入れた辛櫃に蓋をして、紐で縛る。
11.
斎主「川にはらいやられとのる」
2人の神職「おお」と言って担いでいく。
12.
神職ら無言で斎庭を出て本殿に向かう
以上
と、氷川神社では、このような感じで
大祓式が行われていました。
大祓の祝詞は対の詞が多様されていて、
リズム感があって、何度聞いても
心地よいです。
今回の斎主さんは、節回しもよく
わりにいい声で、途中つっかえたり
間違えたりすることもなくて、良かったです。

注連縄で結界が張ってあります。
去年は本殿に向かって右側の場所でしたが
今年は左側になっていました。
写真でもわかるかと思いますが
新しい建物で
木の香りがさわやかでした。
祭壇です。

三方に載っている奉書包みは、
大祓式で神職たちが祓えに用いる、
祓串、麻幣、切り幣、ヒトガタの
祓えセット一式が入っていたようでした。
ちなみに、三方が載っている台は
八足とか八足案、八脚案といいます。
神事の際に、神饌(シンセン、供え物のことです)
などを乗せたり、
祭壇のように使われたりします。
穢れを移したヒトガタを納める辛櫃です。

箱の周りにも注連縄巻いてあります。
やっぱり、穢れのものを納める箱なので
厳重ですね。
大祓の式の最中にカメラを向けるのも
憚られたので、
大祓式次第を以下に書きます。
ちょっと時間が経って、
記憶が定かでないところもありますが…
概ねこんな進行だったということで。
1.
無言で神職たちが斎庭に参入し、
それぞれの床几に座る
2.
神職の一人が祭壇へ歩み、お供えしてある
奉書包みをとって、懐へ入れる
3.
その後、残りの神職もそれぞれ包みを受け取り
懐に入れる。
4.
斎主、歩み出て、大祓詞を奏上
5.
奏上後、二人の神職が歩み出て葛籠を開ける
6.
続いて、それぞれの懐の奉書包みを開けて、
小さな祓串(白い紐のようなものを束ねて
木につけてある、お祓いでシャっ〜シャっ〜
と振るアレです)で、自分をお祓い。
切り幣(紙や麻を小さく、細かい四角に切った
もの、紙吹雪みたいな感じのものです)を
自分にかけて、さらにお祓い。
ヒトガタに息を吹きかけ、身体を撫でて
穢れを移す。
7.
それぞれで、
穢れを移したヒトガタを辛櫃に入れる。
8.
斎主が祭壇にある大幣
(おおぬさ、祓串の大きなもの)を持って
各方向を向いて振り、修祓。
修祓:しゅばつ、榊の枝に麻や紙垂(しで)を
付けた道具を、左右左と振ってお祓いする
9.
2人の神職が歩み出て、八足の上にある
白い布を取り、八つに割く。
八針神事というものかと思います。
大祓の祝詞に
天津菅麻を本刈り断ち末刈り切りて
八針に取裂きて
天津祝詞の太祝詞事を宣れ。
あまつすがそをもとかりたちすえかりきりて
やはりにとりさきて
あまつのりとのふとのりとごとをのれ
という箇所があります。
その八針に取りさきて
というのを祓えの所作として、行っているのが
木綿や麻の白い布を裂く、という所作ではないか
と言われています。
10.
ヒトガタを入れた辛櫃に蓋をして、紐で縛る。
11.
斎主「川にはらいやられとのる」
2人の神職「おお」と言って担いでいく。
12.
神職ら無言で斎庭を出て本殿に向かう
以上
と、氷川神社では、このような感じで
大祓式が行われていました。
大祓の祝詞は対の詞が多様されていて、
リズム感があって、何度聞いても
心地よいです。
今回の斎主さんは、節回しもよく
わりにいい声で、途中つっかえたり
間違えたりすることもなくて、良かったです。