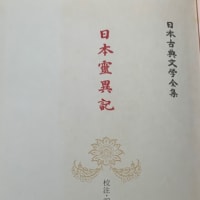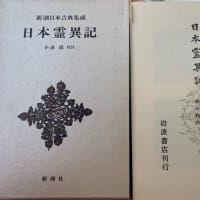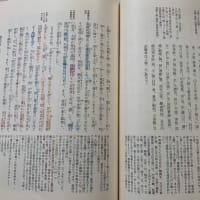今頃の春日大社では、
藤の花が咲いているころかと思います。
春日大社の社紋花は下り藤です。春日大社の
巫女さんは、頭に藤の花を挿しています。
境内の砂ずりの藤

春日大社ホームページより
藤の花が下につくほど長くのびて咲くので
砂ずりの藤、と呼ばれているそうです。
藤棚ではなく、木に巻き付いて自生している
藤の花なども見られます。


春日大社の創建については古事記、日本書紀、
続日本紀などには載っていません。
鎌倉初期の社伝が残っているようですが
私は読んだことはありませんので…
春日大社のホームページによれば
平城京の守護のために鹿島神宮の御祭神である
武甕槌神(たけみかづちのかみ)様が、
白い鹿に乗ってやってきて
御蓋山(みかさやま)の山頂の
浮雲峰(うきぐものみね)に降臨されたそうです。
御蓋山は三笠山とも書かれ、
春日山とも呼ばれています。
その後、社殿を造営して、
さらに経津主神(ふつぬしのかみ・香取神宮)
天児屋根命(あめのこやねのみこと・平岡神社)
比売神(ひめがみ・天児屋根命の妻)を
お招きして、合わせておまつりしました。
この4柱の神様の総称を春日大神と言います。
天児屋根命は、中臣氏の祖先神と
されている神様です。
藤原氏はもとは中臣という姓で
中大兄皇子、のちの天智天皇のもとで働いた
中臣鎌足の功績により藤原姓を賜りました。
でも中臣氏全部が
藤原氏になったわけではありません。
続日本紀、文武天皇2年8月19日
鎌足の直系不比等の子孫のみを藤原姓として、
その他は元の中臣に戻す、
という詔がありました。
中臣氏でも、
中臣を名乗る家系と藤原を名乗る家系は
はっきり分けられたんですね。
藤原氏は中臣氏から分かれた氏族ですから、
中臣氏の祖先神である天児屋根命は
藤原氏の祖先神でもあるのです。
春日大社は建御雷大神様、経津主大神様とともに
藤原氏の氏神様をおまつりする氏神社で、
その社紋の藤の花は、勅命で名乗りを許された
誇らしい藤原という姓を意味する
藤の花でもあるんでしょうね。
さて、
平城京の遷都は710年、元明天皇の治世でした。
元明天皇は持統天皇の息子の草壁皇子の
奥さんで、文武天皇のお母さんです。
文武天皇が早逝してしまい、その息子の首皇子、
のちの聖武天皇がまだ幼かったので(6才)
皇后ではない皇族で、初めて天皇になった
という女性の天皇です。
その頃の左大臣は石上麻呂、
右大臣は鎌足の息子の藤原不比等でした。
石上麻呂は高齢ですし、遷都の時も留守居役を
命ぜられているので、不比等が実権を
持っていたのだろうと思います。
が、藤原氏が天皇家に、娘を嫁に出し
その子どもを天皇にして外戚となる、
という近づき方で権力を握って行くの
はもう少しあとです。
この遷都の頃に、白鹿に乗ってはるばる
茨城の鹿島神宮から建御雷神様が
御蓋山にご降臨されたとされています。
私がこの春日大社の創建時の話を知って
不思議に思ったのは
まず、何故、茨城の鹿島神宮の神様がわざわざ
奈良へ降臨されたのかな?と。
都を守護する神様は、畿内には
おられなかったのかな?ということです。
新幹線や高速がある今にしても
奈良-茨城は近いとは言えないです。
奈良時代、鹿島神宮のある常陸国は
実質な距離以上に、
大和国に暮らす人々からしたら
心理的距離感があったんじゃないか?
もうこの国の果てみたいな場所
だったんじゃないか?と思うんです。
そんな果てなる地から都を護るためにはるばる
降臨して下さった神様!
当時の人々は、今の私たちより
日の暖かさも、闇夜の深さも、
自然の恵の有り難さ、自然の強さ恐ろしさを
日々の中で知っていたので、
神様の御力もまた近しく感じていたと思います。
そういう当時の人々に、建御雷大神様は
どんな印象だったのかな?と思います。
外つ国の、異国の神様、
くらいのインパクトだったのかも?
と思います。
しかも、その神様は国譲り神話にも登場している
剣をかざして敵を打ち破る
強〜い、強〜い神様でしたから。
守って貰えそう💕
頼り甲斐ありそう〜!
に感じられたのかも、と思います。
そして社伝によれば、その後、
神護景曇2年(768)11月9日に
左大臣藤原永手が称徳天皇の命により
社殿を造営して、経津主大神様、天児屋根命、
比売神様をお招きして建御雷大神と
合わせ祭ったそうです。
現在の春日大社の御祭神がこの時、揃いました。
神護景曇2年は、称徳天皇の治世の晩年。
その頃の左大臣は藤原永手、右大臣は吉備真備。
称徳天皇の側近に道鏡もいました。
この後のことですが
称徳天皇の在位中には、皇太子は不在でした。
称徳天皇は神護景曇4年=宝亀元年8月4日に
崩御されています。
称徳天皇は後継が誰かを決めないうちに
亡くなったのですが、
藤原永手は光仁天皇を擁立しました。
なかなかのやり手と思われます。
光仁天皇は、平安京を作った桓武天皇の
お父さんです。
話は戻って、この時の春日大社造営ですが
710年頃に建御雷大神が平城京へいらしてから
768年まで、50年以上
結構、年数経ってますよね?!
その間、どんな事があったのだろうというと、
すっごい大変なこと続きでした。
まず天皇でいえば元明天皇も、その後の
元正天皇も、聖武天皇も亡くなって、
孝謙天皇が即位して、退位して上皇になって、
淳仁天皇が即位して謀反を疑われ廃位されて、
孝謙天皇が即位して称徳天皇になっています。
出来事はといえば…
まず長屋王の変がありました。疫病が大流行
して、重要官僚の貴族や不比等の息子
4人も亡くなってしまいました。
橘奈良麻呂の乱、藤原仲麻呂の乱、
道鏡が法王になるとか、宇佐八幡託宣事件とか。
お寺もどんどん建っています。
国分寺、国分尼寺建立の詔がありましたし。
東大寺が出来てます。
春日大社に隣接している興福寺は
平城京遷都の頃の創建と言われています。
地震や災害、天候不順、飢饉なども煩瑣でした。
と、ざっといっても
山あり、山ありの50年です。
称徳天皇も、藤原不比等の孫の永手も
建御雷大神様にさらに力添えして
平城京を、藤原を守護してくれる神様を
お招きしたい!!という心境だったのかも
しれない…と思います。
建御雷大神様が降臨されたという御蓋山は
平城京遷都以前より
神宿る山・神奈備山として
信仰の場、対象だったようです。
春日大社のご神体山でもあります。
御神域は禁足地ですが
現在、世界遺産にも指定されています。
域内には春日山原始林内には
遊歩道や、一部有料道路があり、
人や車が通行できるところもあるんですよ。
鬱蒼とした森林や大木の森は
人の世ではない、太古より続く自然の
世界を感じ、安らぎとともに、
やはり自然への畏敬を感じるところ
でもあります。
奈良へ行ったら、春日山の散策もおすすめです。
御祭神のお話しは、さらに長くなるので
また、次回に!
20170513 pm加筆修正
藤の花が咲いているころかと思います。
春日大社の社紋花は下り藤です。春日大社の
巫女さんは、頭に藤の花を挿しています。
境内の砂ずりの藤

春日大社ホームページより
藤の花が下につくほど長くのびて咲くので
砂ずりの藤、と呼ばれているそうです。
藤棚ではなく、木に巻き付いて自生している
藤の花なども見られます。


春日大社の創建については古事記、日本書紀、
続日本紀などには載っていません。
鎌倉初期の社伝が残っているようですが
私は読んだことはありませんので…
春日大社のホームページによれば
平城京の守護のために鹿島神宮の御祭神である
武甕槌神(たけみかづちのかみ)様が、
白い鹿に乗ってやってきて
御蓋山(みかさやま)の山頂の
浮雲峰(うきぐものみね)に降臨されたそうです。
御蓋山は三笠山とも書かれ、
春日山とも呼ばれています。
その後、社殿を造営して、
さらに経津主神(ふつぬしのかみ・香取神宮)
天児屋根命(あめのこやねのみこと・平岡神社)
比売神(ひめがみ・天児屋根命の妻)を
お招きして、合わせておまつりしました。
この4柱の神様の総称を春日大神と言います。
天児屋根命は、中臣氏の祖先神と
されている神様です。
藤原氏はもとは中臣という姓で
中大兄皇子、のちの天智天皇のもとで働いた
中臣鎌足の功績により藤原姓を賜りました。
でも中臣氏全部が
藤原氏になったわけではありません。
続日本紀、文武天皇2年8月19日
鎌足の直系不比等の子孫のみを藤原姓として、
その他は元の中臣に戻す、
という詔がありました。
中臣氏でも、
中臣を名乗る家系と藤原を名乗る家系は
はっきり分けられたんですね。
藤原氏は中臣氏から分かれた氏族ですから、
中臣氏の祖先神である天児屋根命は
藤原氏の祖先神でもあるのです。
春日大社は建御雷大神様、経津主大神様とともに
藤原氏の氏神様をおまつりする氏神社で、
その社紋の藤の花は、勅命で名乗りを許された
誇らしい藤原という姓を意味する
藤の花でもあるんでしょうね。
さて、
平城京の遷都は710年、元明天皇の治世でした。
元明天皇は持統天皇の息子の草壁皇子の
奥さんで、文武天皇のお母さんです。
文武天皇が早逝してしまい、その息子の首皇子、
のちの聖武天皇がまだ幼かったので(6才)
皇后ではない皇族で、初めて天皇になった
という女性の天皇です。
その頃の左大臣は石上麻呂、
右大臣は鎌足の息子の藤原不比等でした。
石上麻呂は高齢ですし、遷都の時も留守居役を
命ぜられているので、不比等が実権を
持っていたのだろうと思います。
が、藤原氏が天皇家に、娘を嫁に出し
その子どもを天皇にして外戚となる、
という近づき方で権力を握って行くの
はもう少しあとです。
この遷都の頃に、白鹿に乗ってはるばる
茨城の鹿島神宮から建御雷神様が
御蓋山にご降臨されたとされています。
私がこの春日大社の創建時の話を知って
不思議に思ったのは
まず、何故、茨城の鹿島神宮の神様がわざわざ
奈良へ降臨されたのかな?と。
都を守護する神様は、畿内には
おられなかったのかな?ということです。
新幹線や高速がある今にしても
奈良-茨城は近いとは言えないです。
奈良時代、鹿島神宮のある常陸国は
実質な距離以上に、
大和国に暮らす人々からしたら
心理的距離感があったんじゃないか?
もうこの国の果てみたいな場所
だったんじゃないか?と思うんです。
そんな果てなる地から都を護るためにはるばる
降臨して下さった神様!
当時の人々は、今の私たちより
日の暖かさも、闇夜の深さも、
自然の恵の有り難さ、自然の強さ恐ろしさを
日々の中で知っていたので、
神様の御力もまた近しく感じていたと思います。
そういう当時の人々に、建御雷大神様は
どんな印象だったのかな?と思います。
外つ国の、異国の神様、
くらいのインパクトだったのかも?
と思います。
しかも、その神様は国譲り神話にも登場している
剣をかざして敵を打ち破る
強〜い、強〜い神様でしたから。
守って貰えそう💕
頼り甲斐ありそう〜!
に感じられたのかも、と思います。
そして社伝によれば、その後、
神護景曇2年(768)11月9日に
左大臣藤原永手が称徳天皇の命により
社殿を造営して、経津主大神様、天児屋根命、
比売神様をお招きして建御雷大神と
合わせ祭ったそうです。
現在の春日大社の御祭神がこの時、揃いました。
神護景曇2年は、称徳天皇の治世の晩年。
その頃の左大臣は藤原永手、右大臣は吉備真備。
称徳天皇の側近に道鏡もいました。
この後のことですが
称徳天皇の在位中には、皇太子は不在でした。
称徳天皇は神護景曇4年=宝亀元年8月4日に
崩御されています。
称徳天皇は後継が誰かを決めないうちに
亡くなったのですが、
藤原永手は光仁天皇を擁立しました。
なかなかのやり手と思われます。
光仁天皇は、平安京を作った桓武天皇の
お父さんです。
話は戻って、この時の春日大社造営ですが
710年頃に建御雷大神が平城京へいらしてから
768年まで、50年以上
結構、年数経ってますよね?!
その間、どんな事があったのだろうというと、
すっごい大変なこと続きでした。
まず天皇でいえば元明天皇も、その後の
元正天皇も、聖武天皇も亡くなって、
孝謙天皇が即位して、退位して上皇になって、
淳仁天皇が即位して謀反を疑われ廃位されて、
孝謙天皇が即位して称徳天皇になっています。
出来事はといえば…
まず長屋王の変がありました。疫病が大流行
して、重要官僚の貴族や不比等の息子
4人も亡くなってしまいました。
橘奈良麻呂の乱、藤原仲麻呂の乱、
道鏡が法王になるとか、宇佐八幡託宣事件とか。
お寺もどんどん建っています。
国分寺、国分尼寺建立の詔がありましたし。
東大寺が出来てます。
春日大社に隣接している興福寺は
平城京遷都の頃の創建と言われています。
地震や災害、天候不順、飢饉なども煩瑣でした。
と、ざっといっても
山あり、山ありの50年です。
称徳天皇も、藤原不比等の孫の永手も
建御雷大神様にさらに力添えして
平城京を、藤原を守護してくれる神様を
お招きしたい!!という心境だったのかも
しれない…と思います。
建御雷大神様が降臨されたという御蓋山は
平城京遷都以前より
神宿る山・神奈備山として
信仰の場、対象だったようです。
春日大社のご神体山でもあります。
御神域は禁足地ですが
現在、世界遺産にも指定されています。
域内には春日山原始林内には
遊歩道や、一部有料道路があり、
人や車が通行できるところもあるんですよ。
鬱蒼とした森林や大木の森は
人の世ではない、太古より続く自然の
世界を感じ、安らぎとともに、
やはり自然への畏敬を感じるところ
でもあります。
奈良へ行ったら、春日山の散策もおすすめです。
御祭神のお話しは、さらに長くなるので
また、次回に!
20170513 pm加筆修正