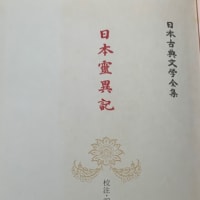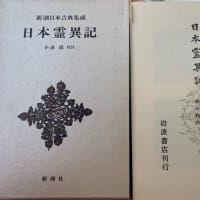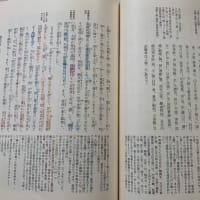日本発酵文化協会のベーシック講座
もう一つ、参加しました。
醤油教室。
どうもお醤油を手作りするみたいです。
お醤油、家で作れるの??
と思いますが、果たして…?
今回も発酵とは、麹とは、というお話しがあり
次に、醤油麹についてや、醤油の歴史、
醤油の醸造の工程と期間、種類について
醤油の様々な表示などのお話しを聞きました。
意外にもお醤油には色々種類がありました。
その違いは素になる醤油麹の
大豆と小麦の割合の違いによるものだそうです。
濃口、淡口、白醤油、たまり醤油、再仕込み醤油。
上の5種類のお醤油に加えて
濃口醤油の熟成期間の違うものと、
九州の甘口醤油、絞る前のお醤油のもろみと
絞った後のお醤油のおからの味見を
させてもらえました。
お豆腐につけて少しずつ、それぞれの味見。
濃口醤油は予想通り、熟成期間の長い方が
塩っぱさの角がとれてまろやかでした。
お醤油のもろみも美味しかったですが、
びっくりしたのはお醤油のおからです。
機械でプレスしたものだそうで、板状のものでした。
初めて食べましたが
それがとても美味しい〜、美味しかったです。
クリームチーズと合わせて
サンドイッチとかにしたら、さらにおいしいかも
思いました。
私はアルコールは飲めないのですが
他の方は、つまみにぴったり!と言ってました。
お醤油は、大豆と小麦で作られた醤油麹に
食塩水を加えて発酵させたものを絞って
できるそうです。
お醤油を作るもとの醤油麹というのは
お塩で作る塩麹、甘酒の素の甘麹
お醤油で作る醤油麹の、醤油麹とは違うものです。
関東で一般的な濃口醤油は大豆と小麦の割合は
5:5、発酵、熟成の期間は6ヶ月〜だそうです。
醤油麹、初めて見ましたが、こんなのでした。

とても香ばしい、そのまま食べれそうな
美味しそ〜な匂いがしました(笑)
一通りお醤油のお話しが終わったら
いよいよお醤油作りです。
お醤油作りの材料はあるこれだけ

醤油麹と、お塩とお水。
まず清潔な容器にお水を入れて、お塩を投入。
ひたすら混ぜて、お塩をよーく溶かします。
ここで溶け残りなどがあると
味にムラが出てしまうそうです。
とにかく、ひたすらかき混ぜ続けること数分。
少し透明になってきて
お塩が底にも何もなくなり、溶けました。
醤油麹を揉んで、ある程度細かくなったところで
塩水にドササッーと投入。
またら混ぜ混ぜ。
あ、混ぜるのは、手で混ぜました。
手を洗って、塩水をぐるぐる混ぜて、
醤油麹を入れて、今度は底からかき混ぜて。
手に住む常在菌も一緒に発酵に参加して貰います。
ちょっと上の方にぶくぶくが出てきたら、よいそうです。


周りについたカスをきれいにして、蓋します。
半年以上は発酵させます。
常温の場所に置いて
しばらくは毎日、1回はかき混ぜるそうです。
注意としては
納豆を開けたところでは、かき混ぜてはいけない
そうです。
納豆菌は大変強力で、醤油麹が納豆菌に負けて
発酵はしますが、納豆味の醤油になってしまうそうです!
すごいですね、納豆菌。
甘麹作るときも、気をつけよっと思いました。
発酵させていると、白いカビみたいのが出て
しまうことがあるそうです。
こんなの


でも、この白いカビみたいのは、害はなくて
口に入っても、大丈夫。
カマンベールの白カビみたいのだそうです。
でも、味が落ちるので、白いのが出てしまったら
その部分は取って捨てしまえばよいそうです。
はぁー、知らなければ、この状態をみたら
もうダメだと思って、捨ててしまいそうです。
白いカビが出てくるときは、何度取っても
また出てくるし、出ない時は出ないそうで
その時によるそうです。
半年以上して、もろみができたら、醤油麹を
絞って、お醤油になるそうですが
そのまま食べても美味しいそうです。
確かに、味見で醤油もろみ食べましたが
美味しかったし。
絞ったあとの醤油のおからも。
捨てるところがないですねー。
半年、ちゃんと面倒をみて、自家製醤油にしたいと思います。
もう一つ、参加しました。
醤油教室。
どうもお醤油を手作りするみたいです。
お醤油、家で作れるの??
と思いますが、果たして…?
今回も発酵とは、麹とは、というお話しがあり
次に、醤油麹についてや、醤油の歴史、
醤油の醸造の工程と期間、種類について
醤油の様々な表示などのお話しを聞きました。
意外にもお醤油には色々種類がありました。
その違いは素になる醤油麹の
大豆と小麦の割合の違いによるものだそうです。
濃口、淡口、白醤油、たまり醤油、再仕込み醤油。
上の5種類のお醤油に加えて
濃口醤油の熟成期間の違うものと、
九州の甘口醤油、絞る前のお醤油のもろみと
絞った後のお醤油のおからの味見を
させてもらえました。
お豆腐につけて少しずつ、それぞれの味見。
濃口醤油は予想通り、熟成期間の長い方が
塩っぱさの角がとれてまろやかでした。
お醤油のもろみも美味しかったですが、
びっくりしたのはお醤油のおからです。
機械でプレスしたものだそうで、板状のものでした。
初めて食べましたが
それがとても美味しい〜、美味しかったです。
クリームチーズと合わせて
サンドイッチとかにしたら、さらにおいしいかも
思いました。
私はアルコールは飲めないのですが
他の方は、つまみにぴったり!と言ってました。
お醤油は、大豆と小麦で作られた醤油麹に
食塩水を加えて発酵させたものを絞って
できるそうです。
お醤油を作るもとの醤油麹というのは
お塩で作る塩麹、甘酒の素の甘麹
お醤油で作る醤油麹の、醤油麹とは違うものです。
関東で一般的な濃口醤油は大豆と小麦の割合は
5:5、発酵、熟成の期間は6ヶ月〜だそうです。
醤油麹、初めて見ましたが、こんなのでした。

とても香ばしい、そのまま食べれそうな
美味しそ〜な匂いがしました(笑)
一通りお醤油のお話しが終わったら
いよいよお醤油作りです。
お醤油作りの材料はあるこれだけ

醤油麹と、お塩とお水。
まず清潔な容器にお水を入れて、お塩を投入。
ひたすら混ぜて、お塩をよーく溶かします。
ここで溶け残りなどがあると
味にムラが出てしまうそうです。
とにかく、ひたすらかき混ぜ続けること数分。
少し透明になってきて
お塩が底にも何もなくなり、溶けました。
醤油麹を揉んで、ある程度細かくなったところで
塩水にドササッーと投入。
またら混ぜ混ぜ。
あ、混ぜるのは、手で混ぜました。
手を洗って、塩水をぐるぐる混ぜて、
醤油麹を入れて、今度は底からかき混ぜて。
手に住む常在菌も一緒に発酵に参加して貰います。
ちょっと上の方にぶくぶくが出てきたら、よいそうです。


周りについたカスをきれいにして、蓋します。
半年以上は発酵させます。
常温の場所に置いて
しばらくは毎日、1回はかき混ぜるそうです。
注意としては
納豆を開けたところでは、かき混ぜてはいけない
そうです。
納豆菌は大変強力で、醤油麹が納豆菌に負けて
発酵はしますが、納豆味の醤油になってしまうそうです!
すごいですね、納豆菌。
甘麹作るときも、気をつけよっと思いました。
発酵させていると、白いカビみたいのが出て
しまうことがあるそうです。
こんなの


でも、この白いカビみたいのは、害はなくて
口に入っても、大丈夫。
カマンベールの白カビみたいのだそうです。
でも、味が落ちるので、白いのが出てしまったら
その部分は取って捨てしまえばよいそうです。
はぁー、知らなければ、この状態をみたら
もうダメだと思って、捨ててしまいそうです。
白いカビが出てくるときは、何度取っても
また出てくるし、出ない時は出ないそうで
その時によるそうです。
半年以上して、もろみができたら、醤油麹を
絞って、お醤油になるそうですが
そのまま食べても美味しいそうです。
確かに、味見で醤油もろみ食べましたが
美味しかったし。
絞ったあとの醤油のおからも。
捨てるところがないですねー。
半年、ちゃんと面倒をみて、自家製醤油にしたいと思います。