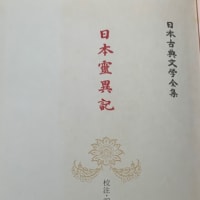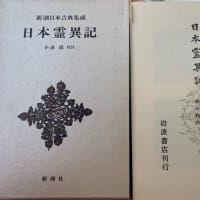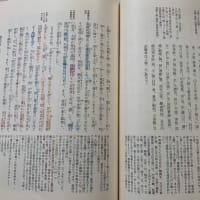次に奈良のことを書くときは、
大神神社の続きで狭井神社、檜原神社について
と思っていましたが…
東大寺の拝観料が値上げになるそうです。
東大寺拝観料、来年値上げ
やっぱり大変だったんた!と思いました。
お寺の経営がどう成り立っているのか、
わからないんですが、
東大寺には塔やお堂など大小たくさんあって
働いてる人もたくさんいるし、
建物や仏像その他の保存や手入れとか
公的補助もあるでしょうけど、
なかなか大変じゃないかと思っていましたが…
その値上げで足りるんでしょうか。
奈良時代に創建されたの東大寺をはじめ、
奈良にある主なお寺さんには、
お墓や檀家さんというのはありません。
なので、檀家さんからお金を集めるとかは
できないわけです。
創建当時は天皇や貴族、その後は
有力豪族とか、大名が後ろ盾になったり
寺領というのもありました。
なので明治以前まではまだ良かったと思います。
今は寺領もないでしょうし、
その昔の権力者や大商人のような人も
いないでしょうから…
お寺や神社の建替修復や現状を保持して
いくだけでも本当に大変なんだろうなぁと。
まぁ私が心配することでもなく、
心配してもどうにもならないんですけど。
東大寺は修二会を行う二月堂のあるお寺で
ずっと修二会を続けて欲しいと思うことと、
もう一つ、
東大寺や大仏様を作った聖武天皇と
その娘さんの孝謙・称徳天皇のことを考えると
創建当時とは変わっているとはいえ、
今に残っている東大寺の姿を、なるべく
このまま守っていて欲しいなぁと思うのです。
どうして、東大寺や大仏様、聖武天皇、
孝謙・称徳天皇が気になるかというと…
以下、もしかしたら、
ものすご〜くマニアックな話しかも、です。
私は日文で古代文学専攻でした
特に古事記の成立と天皇の宣命について
興味がありました。
宣命とは、今で言う天皇のお言葉です。
当時、天皇のお言葉には2種類の表記があって
詔勅というのは漢文で書かれたもので、
宣命は宣命体という文体で書かれたものです。
宣命の表記も漢字表記なんですが、
漢文ではなく、漢字仮名交じり文を、
漢字で書いたような表記になっています。
ちなみに祝詞も宣命体で表記されていました。
祝詞と奈良時代の宣命は文体や語彙が
似ているところがあります。
宣命体は
今の漢字と平仮名を交えた日本語表記の
源流みたいな文体です。
古事記、日本書紀の書名は一般的に知られて
いると思いますが、その続きに、続日本紀
(しょくにほんぎ)という歴史書があります。
その続日本紀に宣命が62、記載されています。
続日本紀の宣命を読んでいたため、
結果的に、続日本紀に記載されていた、
出来事に詳しくなった感じです。
そして宣命が、天皇の個性を感じさせる
文章でもあるので、
その時々に発された宣命とそれに至る経緯から
聖武天皇や孝謙・称徳天皇の個人的な思いを
考えたりしました。
どの時代も大変なことはあると思いますが
続日本紀を読むと、呪詛と讒訴と誣告の
記事がたくさんあります。
それで粛清が続いたり、疫病が蔓延して
庶民から要職に就く貴族も、短期間に
バタバタ亡くなったりしました。
地震や旱魃、民の逃散など…
読んでて、全然穏やかな時期がないじゃん!
ということが続いていました。
聖武天皇の頃は、地方に反乱があったり
大臣だった 長屋王に謀叛の嫌疑出て、
結局自殺?に追い込んでしまったのですが
疫病が大流行して、長屋王を追い込んだ
藤原4兄弟が、4人ともまさかの病死!
立太子したばかりの赤ちゃん皇太子が
亡くなってしまったり、お母様が亡くなったり、
災害があったり、怪異が報告されたり…
もう、どうしたらいいんだ…
と途方に暮れても当然な感じです。
当時は、天皇の行いが良ければ瑞祥が現れ
良くなければ災異が起こると
思われていましたから
聖武天皇は、次々起こる問題に、
自分が至らないからだと思い込むような事態が
続いていて、気の毒なくらいでした。
神様を祀っても収まらないので、
もう、仏に頼るしかない心境だったのだろうと。
それで、
大っきな大っきな仏様を作ろうと思ったり
全国にお寺を建てよう!と思ったりしたんでしょうね。
今では、それで病気や天候不順や災害、
政情不穏が収まることに繋がるなんて
考えられないですが…
大仏様が建立された時、
この大仏様が救ってくれるかも!と
皆が信じるだけのインパクトは
相当あったと思います。
今だって、大仏様と大仏殿を見ると
はぁ〜、すごいなぁ〜と思いますものね。
しかも、創建当時の大仏殿はもっと大きかったと
言われています。
今より大きな大仏殿が、8世紀に立ってたんですよ。
その模型が大仏殿の大仏様の裏側の方に
ありますので、お参りする機会がありましたら、
ご覧になってみてください。
孝謙・称徳天皇と書いていましたが
孝謙天皇は聖武天皇と光明皇后の一人娘さんで
女性で皇太子になって、天皇に即位しました。
一度退位して太政天皇になり、
もう一度即位して称徳天皇になっています。
2度即位することを重祚、ちょうそといいます。
称徳天皇の先例に、皇極・斉明天皇があります。
女性の天皇で、天智、天武天皇のお母様です。
称徳天皇は聖武天皇以上に
波瀾万丈の人生を送った方です。
東大寺の中に、手向山八幡宮という神社が
あります。
九州の宇佐八幡宮から勧進された神社です。
東大寺に参拝された方でお寺の中になんで神社?
と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
大仏造営に聖武天皇が苦労していた時と、
称徳天皇が晩年、譲位しようとした時と、
八幡様は深〜い関わりがあります。
でも、話しがさらに長くなるので、
東大寺の八幡様のお話しまた改めて。
今日は文字のみで愛想がないので
くるみのサービスショットを(笑)

大神神社の続きで狭井神社、檜原神社について
と思っていましたが…
東大寺の拝観料が値上げになるそうです。
東大寺拝観料、来年値上げ
やっぱり大変だったんた!と思いました。
お寺の経営がどう成り立っているのか、
わからないんですが、
東大寺には塔やお堂など大小たくさんあって
働いてる人もたくさんいるし、
建物や仏像その他の保存や手入れとか
公的補助もあるでしょうけど、
なかなか大変じゃないかと思っていましたが…
その値上げで足りるんでしょうか。
奈良時代に創建されたの東大寺をはじめ、
奈良にある主なお寺さんには、
お墓や檀家さんというのはありません。
なので、檀家さんからお金を集めるとかは
できないわけです。
創建当時は天皇や貴族、その後は
有力豪族とか、大名が後ろ盾になったり
寺領というのもありました。
なので明治以前まではまだ良かったと思います。
今は寺領もないでしょうし、
その昔の権力者や大商人のような人も
いないでしょうから…
お寺や神社の建替修復や現状を保持して
いくだけでも本当に大変なんだろうなぁと。
まぁ私が心配することでもなく、
心配してもどうにもならないんですけど。
東大寺は修二会を行う二月堂のあるお寺で
ずっと修二会を続けて欲しいと思うことと、
もう一つ、
東大寺や大仏様を作った聖武天皇と
その娘さんの孝謙・称徳天皇のことを考えると
創建当時とは変わっているとはいえ、
今に残っている東大寺の姿を、なるべく
このまま守っていて欲しいなぁと思うのです。
どうして、東大寺や大仏様、聖武天皇、
孝謙・称徳天皇が気になるかというと…
以下、もしかしたら、
ものすご〜くマニアックな話しかも、です。
私は日文で古代文学専攻でした
特に古事記の成立と天皇の宣命について
興味がありました。
宣命とは、今で言う天皇のお言葉です。
当時、天皇のお言葉には2種類の表記があって
詔勅というのは漢文で書かれたもので、
宣命は宣命体という文体で書かれたものです。
宣命の表記も漢字表記なんですが、
漢文ではなく、漢字仮名交じり文を、
漢字で書いたような表記になっています。
ちなみに祝詞も宣命体で表記されていました。
祝詞と奈良時代の宣命は文体や語彙が
似ているところがあります。
宣命体は
今の漢字と平仮名を交えた日本語表記の
源流みたいな文体です。
古事記、日本書紀の書名は一般的に知られて
いると思いますが、その続きに、続日本紀
(しょくにほんぎ)という歴史書があります。
その続日本紀に宣命が62、記載されています。
続日本紀の宣命を読んでいたため、
結果的に、続日本紀に記載されていた、
出来事に詳しくなった感じです。
そして宣命が、天皇の個性を感じさせる
文章でもあるので、
その時々に発された宣命とそれに至る経緯から
聖武天皇や孝謙・称徳天皇の個人的な思いを
考えたりしました。
どの時代も大変なことはあると思いますが
続日本紀を読むと、呪詛と讒訴と誣告の
記事がたくさんあります。
それで粛清が続いたり、疫病が蔓延して
庶民から要職に就く貴族も、短期間に
バタバタ亡くなったりしました。
地震や旱魃、民の逃散など…
読んでて、全然穏やかな時期がないじゃん!
ということが続いていました。
聖武天皇の頃は、地方に反乱があったり
大臣だった 長屋王に謀叛の嫌疑出て、
結局自殺?に追い込んでしまったのですが
疫病が大流行して、長屋王を追い込んだ
藤原4兄弟が、4人ともまさかの病死!
立太子したばかりの赤ちゃん皇太子が
亡くなってしまったり、お母様が亡くなったり、
災害があったり、怪異が報告されたり…
もう、どうしたらいいんだ…
と途方に暮れても当然な感じです。
当時は、天皇の行いが良ければ瑞祥が現れ
良くなければ災異が起こると
思われていましたから
聖武天皇は、次々起こる問題に、
自分が至らないからだと思い込むような事態が
続いていて、気の毒なくらいでした。
神様を祀っても収まらないので、
もう、仏に頼るしかない心境だったのだろうと。
それで、
大っきな大っきな仏様を作ろうと思ったり
全国にお寺を建てよう!と思ったりしたんでしょうね。
今では、それで病気や天候不順や災害、
政情不穏が収まることに繋がるなんて
考えられないですが…
大仏様が建立された時、
この大仏様が救ってくれるかも!と
皆が信じるだけのインパクトは
相当あったと思います。
今だって、大仏様と大仏殿を見ると
はぁ〜、すごいなぁ〜と思いますものね。
しかも、創建当時の大仏殿はもっと大きかったと
言われています。
今より大きな大仏殿が、8世紀に立ってたんですよ。
その模型が大仏殿の大仏様の裏側の方に
ありますので、お参りする機会がありましたら、
ご覧になってみてください。
孝謙・称徳天皇と書いていましたが
孝謙天皇は聖武天皇と光明皇后の一人娘さんで
女性で皇太子になって、天皇に即位しました。
一度退位して太政天皇になり、
もう一度即位して称徳天皇になっています。
2度即位することを重祚、ちょうそといいます。
称徳天皇の先例に、皇極・斉明天皇があります。
女性の天皇で、天智、天武天皇のお母様です。
称徳天皇は聖武天皇以上に
波瀾万丈の人生を送った方です。
東大寺の中に、手向山八幡宮という神社が
あります。
九州の宇佐八幡宮から勧進された神社です。
東大寺に参拝された方でお寺の中になんで神社?
と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
大仏造営に聖武天皇が苦労していた時と、
称徳天皇が晩年、譲位しようとした時と、
八幡様は深〜い関わりがあります。
でも、話しがさらに長くなるので、
東大寺の八幡様のお話しまた改めて。
今日は文字のみで愛想がないので
くるみのサービスショットを(笑)