・・・世間の反応は真っ二つに分かれている印象がある。
まず、もっと駆除に力入れろという強硬意見。もう一つはクマの駆除に無条件に反対し保護を訴える声である。
だが,どちらも無理がある。前者は、やみくもな銃と罠に頼った駆除を主張しがちだが、人材、手間、費用などを含めて物理的に難しい。後者は、自分は安全圏に身を置きながら、クマなど野生動物を神聖視しており、獣害に遇われる地域の苦悩を無視している。
もっと冷静になり、増えすぎた生息数を抑える対策と同時に、クマの人里への出没を減らす方法を考え、もし出くわした際はどうすべきかという点を具体的に身につけるべきではないか。
同時に、クマなどの野生動物への対応知識と技術を身につけた人材の育成も必要だろう。
実際の対応はいろいろ模索されているようだが、対策マニュアルを二つ紹介しておく。まずは環境省の出しているもの。
やはり事前に出没に備えること、そしてクマが人里に出てこないようにするのが基本だ。そのためには、農山村の最前線における対策が必要となる。
具体的には、餌となるものに近づけないこと。そして可能な限り除くこと。それは防護柵の設置のほか、果樹や農作物とその放棄残滓、生ゴミ、ペットフードの管理まで及ぶ。そのうえで都市部まで出てくる理由と対策を考えなくてはならない。
次にクマが出没した際に取るべき行動。目撃時の連絡先や人員の配置、被害発生時の対応……もし鉢合わせした場合のことも取り上げている。彼らを刺激しない(人を襲う気にさせない)方策も知っておきたい。クマは必ず襲ってくるわけではなく、人を避けることも多い。いや、通常はそちらが普通だ。何が人に怒りを向けて襲うのかを知ることで、危険を抑えることができる。
遭遇した際に、いきなり走って逃げるのはもっとも危険であることなども記されている。そして最悪襲われた際の防御方法も、一応触れている。そのように行動できるかは疑問だが。
日本のクマに則した内容だが、どちらかというと個人の対応策というよりは、自治体の職員向きかもしれない。行政としてクマへのに向き合い方に重きを置いているように感じた。
それに対して、より実践的なものがあった。ただし海外版。
『非致死的なクマ管理技術の手引き』である。
カナダの市民団体製作のマニュアルだが、それを日本の<Bear Smart Japan>が翻訳したものである。イラストや写真も豊富。
タイトルどおり、クマを殺さず人間との共存をめざしているが、何も駆除をすべて否定しているわけではなく、銃器の使用も容認している。ただ、できる限りクマを人間社会に近づけず、追い払うという理念で方策を練ったものだ。
クマを銃で射殺する方法や捕獲方法、別方向に誘導する方法なども触れているが、騒音による抑止などもある。とくにベアドッグ(訓練したイヌによるクマの追い払い)は、今の日本ではほとんど行われていないが、可能性を感じる。
北米を舞台にしているから、対象とするのはグリズリーとクロクマだ。ただグリズリーは、ヒグマとほぼ同種。クロクマはツキノワグマに近い種類で、体格は多少大きいが、生息環境も森林などで生態はツキノワグマと近そうだ。それぞれの対策が、日本の2種類のクマにも応用できるだろう。
丸ごと使うのではなく、日本では取れない手段も紹介されているから、よく考えて選択肢に加えると参考になるかと思う。
・・・
両者を読んで改めて思うのは、クマ出没対策とは、まずクマの生態を知り、人の行動はそれに合わせていくことの重要性だ。画一的な方法ではないのだ。
どうも日本の場合は、冒頭の「駆除至上主義」と「保護至上主義」の両方とも、肝心のクマに関する知識をなおざりにしているように感じてしまう。さらに言えば、出没する地元の人々以外は、みな他人事のように思われる。
「駆除すればいいんだ」と言っても自身がやる気は毛頭ないだろうし、「保護しろ」と叫ぶものの、被害者には目を向けていない。それどころかクマの餌を心配してドングリを撒くような発想をしている。逆効果も甚だしい。
日本でも野生動物の研究は結構行われてきて、それなりの知識の蓄積はある。完全でなくても、それらを習得することから始めるべきだろう。
▶ 土は生命の根源である




















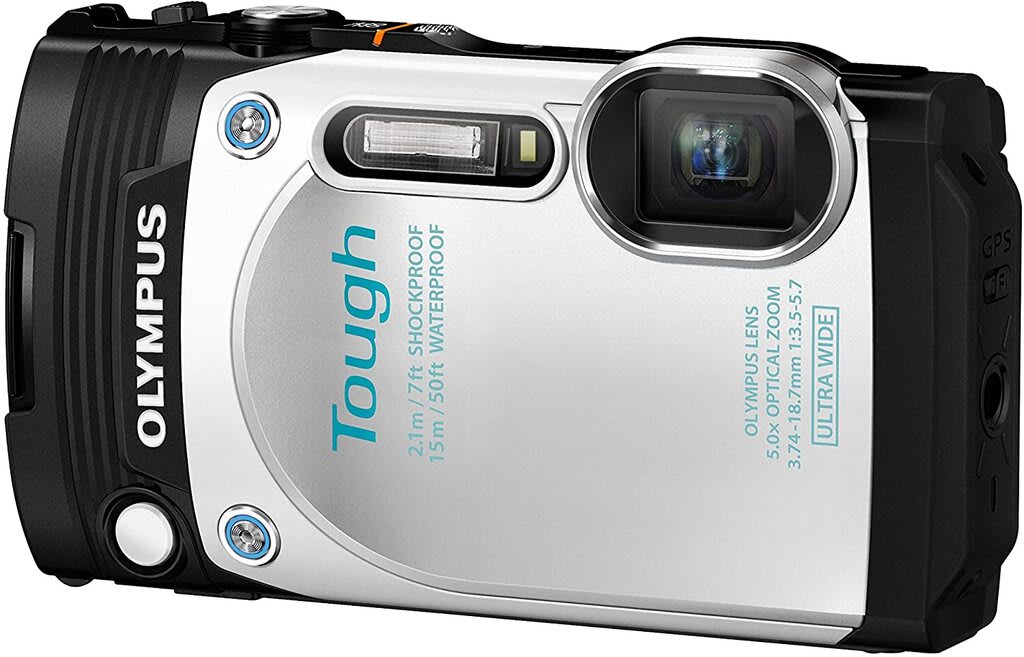

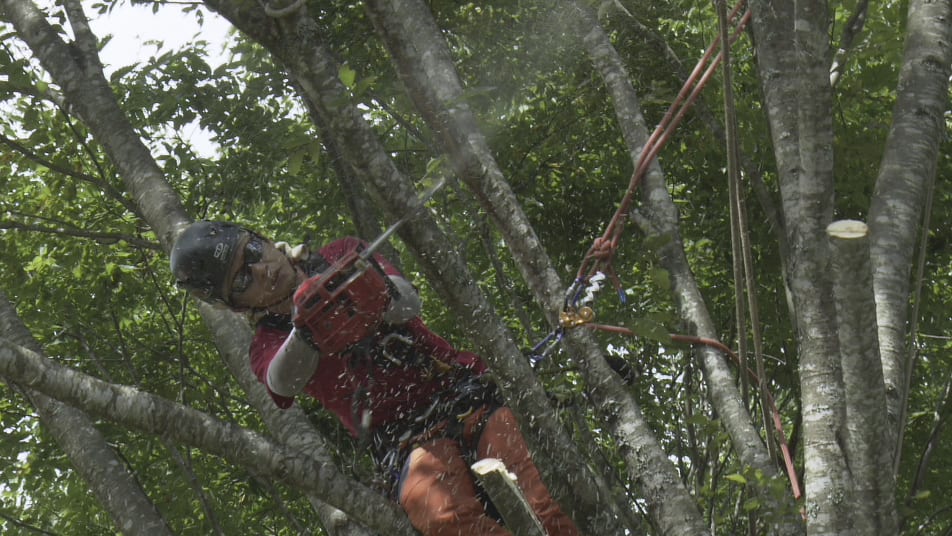
「ああ、あの木はいつまで切られずにいるだろう」
と心配してしまいます。
数百年生きてきた樹木が、人間の生活の邪魔になるという理由で切られていきます。
一番多いのは「電線に近いから危ない」でしょうか。
街中で生き残ることが可能な場所は、神社やお寺の境内くらいでしょう。
しかしその神域・聖域でさえ、安全な場所でなくなってきています。
そんな記事を紹介します;
□ 信号機も隠す危ない「ご神木」 撤去しない神社の言い分
(2019年9月25日 朝日新聞デジタル)
東京都八王子市にある「天満社」。学問の神様・菅原道真をまつり、北野天満社とも呼ばれ、地名の北野町の由来ともされる。その歴史ある神社が、樹木の枝葉を境内からはみ出させており、車や歩行者に接触する危険があるなどとして、国土交通省相武国道事務所と市から2017年以降計11回、文書で行政指導されていることがわかった。
神社側は根本的に改善する気配がなく、地元の町会などは「越境樹木を放置すれば、重大な交通事故につながりかねない」と困惑している。
天満社は京王線北野駅から徒歩3分の場所にある。現場を訪れると、北西角にある大木の枝葉が国道の上におおいかぶさるように伸び、大型トラックの荷台の上部に接触しそうになっている。信号機も枝葉に覆われて見にくい。枝葉が市道をまたいで児童館に達している場所もある。
相武国道事務所によると、2017年に通報をきっかけに越境を確認し、18年5月に宮司に口頭で改善を求めた。今年2月、住民の訴えで再び越境を確認し、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁じた道路法43条に抵触しているとして、2、5月に計3回、「道路占用指導書」を宮司の家族とみられる人に渡したり、宮司の自宅に投函(とうかん)したりしたが、反応はないという。
市も17年以降、今年7月までに6回、神社側に文書でせんていを要請した。だが、市によると、宮司は3月に「樹木医に管理させているから大丈夫。境内の樹木はご神木だ」と主張し、すぐにせんていするとは明言しなかった。市側がせんていするという申し出も受け入れなかった。
思い出すのは、日光の太郎杉。
道路に面したスギの巨樹を残すために話し合い、人間側が譲歩して残されました(日光太郎杉事件)。
しかし都会ではそのような雰囲気はないらしい。
第一次産業中心で自然を恐れ感謝する地方と、
自然と接することを忘れた都会では異なるようですね。
もっとも、自然の驚異(地震・台風など)は場所に関係なく襲ってくる昨今ですが。
さて、上記記事の続報です。
この争い(?)、どのような結末を迎えるのでしょう。
□ はみ出すご神木「年内撤去を」 指導17回、初の期限
(2019/12/21 朝日新聞デジタル)
八王子市北野町の神社「天満社」の樹木の枝葉が境内からはみ出している問題で、国土交通省相武国道事務所と東京都八王子市は、天満社に対し、12月中に越境部分を取り除くようそれぞれ文書で指導した。期限を設けずに指導してきたが、改善が見られないと判断し、初めて期限を設けた。

【写真】神社の境内(左側)から南側の市道に樹木の枝葉がおおいかぶさり、トンネルのようになっている
相武国道事務所は、12月中の撤去を求める11月13日付の勧告書を宮司の自宅に届けた。回答がないため、12月2日に催告書を内容証明郵便で送った。
市は12月中の撤去を求める指示書を11月27日に宮司の自宅に届けた。翌日、宮司から担当課に電話があり、「ご神木なので撤去できない」という趣旨の主張をしたという。
天満社の越境樹木をめぐっては、相武国道事務所と市が、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁じた道路法に抵触しているとして、2017年以降、行政指導を繰り返してきた。12月中の撤去を求める文書を含め計17回になった。
相武国道事務所は「引き続き理解を求め、他の方策も検討していく」、市は「粘り強く指導していく。次の段階についても検討している」としている。
神社の神域に対する日本人の心情は、昔々、西行が伊勢神宮を参拝したときに残した言葉;
「なにごとのおはしますかは知らねども かたじけなさに涙こぼるる」
に象徴されます。
最近、道路脇の空き地に小さな赤い簡易鳥居が立っているのを見かけますが、あれは「ゴミ捨て対策」だそうです。
鳥居があると、日本人はゴミをポイ捨てできない、罰が当たりそう、という意識を利用した措置ですね。
しかし、そのような意識も最近は薄れてきたようです。
それを感じた記事を紹介します;
□ 陸自隊員、神社の鳥居壊して不申告か 山形県警が捜査
(2019/12/16 朝日新聞デジタル)
陸上自衛隊神町駐屯地(山形県東根市)の男性隊員の運転する車が今月上旬、同市内の神社の鳥居を壊す事故を起こし、警察に申告せずに立ち去ったとして、山形県警が道路交通法違反(事故不申告)の疑いで捜査していることがわかった。駐屯地は「調査中のためコメントは差し控える」としている。

【写真】柱が根元から折れ、倒れかかった木造の鳥居=山形県東根市神町東2丁目、住民提供
神社周辺の住民らによると、4日午後10時ごろ、神社の境内に進入した車が木造の鳥居に衝突して、鳥居の柱を折った。運転していたのは第6施設大隊に所属する男性隊員で、ほかにも複数の隊員が乗っており、警察に事故を申告せず、車でその場を離れた可能性があるという。神社は駐屯地北側約500メートルにある。
翌5日早朝、鳥居が壊れて倒れかけているのを近くの住民が発見し、110番通報した。その後、運転していたとみられる男性隊員が上司に付き添われ、地区の住民宅に謝罪に訪れたという。
駐屯地関係者によると、男性隊員らは4日午後6時から午後9時ごろまで駐屯地外で懇親会に参加していたという。駐屯地は隊員らが事故を起こした状況やその後の経緯のほか、隊員らの飲酒の有無を調べているという。
まあおそらく、アルコールが入っていて逃げたのだと思われますが・・・残念なエピソードです。
車で向かったものの、途中トラブルに遭遇して断念。
それ以後も気にはなっているものの、開催地が遠いのでいまだ参加できずにいます。
今年は九州かあ・・・無理だなあ。
■ 巨木の魅力見つめ直す 宇美町で全国フォーラム 2019.10.19/20
(2019/10/8:西日本新聞) ふくおか都市圏版 後藤 潔貴
「巨木を語ろう全国フォーラム」が19、20の両日、宇美町立中央公民館で開かれる。環境省が1988年に実施した巨樹・巨木林調査をきっかけに、愛好者や研究者らでつくる「全国巨樹・巨木林の会」が同年から毎年各地で開いている。地域のシンボルとして親しまれたり、「パワースポット」として各地から多くの人が訪れたりする巨木の魅力とは何か。同会福岡県支部会長の佐野義明さん(81)に話を聞いた。
「前に見たときは、上もあったんですけれどね」
待ち合わせ場所の福岡市の中央区役所前で、佐野さんが指さした。その先に立っていたのが、巨大なイチョウの木「飯田屋敷の大銀杏(おおいちょう)」。市指定の保存樹で樹齢約400年とされる巨木だが、幹の高さ約5メートルより上部がなくなり、無数のひこばえが茂っていた。
案内板を見ると、「枯れかかっていたため数年前から再生治療中」とのこと。50~60年後には「ひこばえが成長して、元の巨木がよみがえるはず」という説明書きも。「そのころにはもう私はおらんですなあ」。佐野さんが力なく笑った。
◆ ◆
佐野さんによると、県内は温暖な気候から、クスの巨木が多いのが特徴とか。
宇美町の宇美八幡宮には、樹齢2千年を超えるとされるクスノキの「湯蓋(ゆふた)の森」(樹高30メートル、幹回り15・7メートル)と、「衣掛(きぬかけ)の森」(樹高20メートル、幹回り20メートル)がそびえる。どちらも国指定天然記念物だ。見ているだけで圧倒されそうになる存在感。大人気のアニメ映画「となりのトトロ」で描かれた大クスのようだ。
今回のフォーラムは32回目で、県内開催は初めて。この2本の巨木があることなどから宇美町が候補地に浮上し、来年の町制施行100周年のプレイベントとして開くことになった。
「今も残っている巨木は先人たちが大事に守ってきたものも多く、その関わりを想像するのもおもしろい」と佐野さん。一方で、「巨木は遠い将来も立ち続けるように思われるが、意外とそうではないのです」。
佐野さんは県内の巨木115本を紹介した「福岡県の巨樹・巨木ガイド」(梓書院)を2012年に出版。その中には、掲載後の数年間で姿を消したものもある。最近も、糸島市指定保存樹の樹齢千年超とされるイチイガシが台風の影響で倒れたばかりだ。
永遠に続く命のように思えるが、実際は飯田屋敷の大銀杏のように力強さとはかなさを併せ持つ。それも巨木の魅力の一つだろう。佐野さんは「大会をきっかけに大勢の人に身近な巨木への関心を持ってもらえれば」と期待している。
(後藤潔貴)
◇ ◇
第32回巨木を語ろう全国フォーラムのテーマは「歴史をつなぎ、次世代につなぐ、巨木の魅力を『うみ』だそう!」。19日は午後1時からフォーラムがあり、福岡県林業技術者連絡会の福島敏彦会長が講演する。その後、パネルディスカッションがあり、佐野さんらが巨木の魅力を語り合う。農林中央金庫、福岡県森林組合連合会のベンチ寄贈などもある。20日は近郊の巨木を巡る見学会(有料)がある。問い合わせは宇美町社会教育課内実行委員会事務局=092(933)2600。









