
★『1リットルの涙』木藤亜也著【幻冬舎】
難病と闘い続ける少女
亜也の日記
15歳の夏、恐ろしい病魔が少女から青春を奪った。 数々の苦難が襲いかかる中、日記を書き続けることが生きる支えだった。
もう、歩けない、何もできない。
でも、生きていたいのです。
たとえ、どんな小さく弱い力だとしても・・・。
亜也は中学3年生の時、突然、脊髄小脳変性症という難病にかかってしまう。 反射的にバランスをとり、素早い滑らかな運動をするのに必要な小脳・脳幹・脊髄の神経細胞が変化し、ついには消滅してしまう病で、発症の原因が不明のため治すことができない。 それでも亜也は進学校の県立東高校に入学、新しい友達に囲まれて勉学に励んでいた。 しかし病は徐々に進行し、亜也はとうとう自力で歩くことすらできなくなってしまう…。
彼女がかかったのは、現時点では体の筋肉が痩せないよう運動訓練を続け、進行を遅らせる薬を使うしかない難病。 体のふらつきに始まり、歩行困難、手や指の不自由、喋るのも発音があいまいになるなど、それぞれの症状が少しずつ進行し、最後には寝たきりになってしまう。
少し前に映画化され上映されていることは聞いていたが、残念なことに映画を観ることはできなかった。 そこで原作を読んでみることにした。
「脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)」とは、人間の脳には約140億の神経細胞と、その10倍もの神経細胞を支持する細胞があり、それぞれの神経細胞は多くのグループに分けられ、運動する時に働くものもあれば、見たり聞いたり感じたりする時に働くものもあり、およそ人間が生きている間はたくさんのグループの神経細胞が活動していることになる。
脊髄小脳変性症はこれらの神経細胞グループのうち反射的にバランスをとり、素速い、滑らかな運動をするのに必要な小脳・脳幹・脊髄の神経細胞が変化し、ついに消えてしまう病気である。 どうして突然、細胞が消えてしまうのかはわかっていない。 全国的な統計では1,000余の患者さんが集められたが、実際にはこの2~3倍はいるらしい。
(藤田保健衛生大学神経内科助教授 山本子先生)
日々失われていく彼女の体を動かすと言う本来誰しもが持つ、当たり前な人としての能力を、15歳という若さで発症し、闘病生活の中で彼女が感じ、体験したことを、彼女の言葉で書き綴っている。 その病気にかかった人間でしかわからないことなのかもしれないが、言葉の一つ一つが、ずしんと心に響く。 五体満足でのほほんと生きている自分が何て無駄に人生を送っているか改めて問われているような、そんな気持ちにさせられる。
話は少し外れるが、先週の日曜日、JRのホームでアイマスクをして介護者(おそらく親だと思う)の腕に引かれ、目の見えない人の立場を実体験しているのだろうグループに出会った。 普段当たり前のように階段を上る行為、電車に乗る行為、その他様々の健常者が当たり前に生活できている中で、そのひとつの機能が失われたとき、この場合は見ることを奪われたことを想定していたのだろうけど、言葉で言うのは簡単だが疑似体験をするということは貴重な体験かもしれない。
彼女の話に戻るが、身体の機能が奪われ日毎に不自由になっていく中で、少しでも生きるための努力を惜しまない、だけど若い遊びたい盛りの少女が闘病し、葛藤する様を彼女なりの言葉で書き綴っているこの本には生きたいという姿勢が克明に記されている。 読み進むにつれ(この本は通勤電車の中で読んでいた)、熱いものが込み上げてきて、ページを先に送ることをが辛くなることもあった。 涙を堪えることに苦労した。
彼女とともに、彼女の看病をした家族・医師・友人、その他多くの彼女に関わった人たちに支えられ、彼女は25歳10ヶ月で亡くなった。
彼女の人生に接し、彼女の周りの人たちが、また彼女に関わった全ての人たちが、生きる勇気と生きることの大事さを学んだことに違いない。
医師が看護婦が彼女と接することで、医療の現場に居ながら、彼女の“生”に対する強い気持ちを感じ、そして周りの患者たちまでもに、彼女のその気持ちがプラス思考にポジティブにはたらいていたことは、言うまでもない事実だ。
彼女の生きた“証”をこの本を読むことで感じられたこと、何不自由のない生活を送っている自分への戒め、健康で生んでくれ育ててくれた両親に感謝するとともに、残された時間を大事に使っていきたいという想いで一杯である。
この本を読んで、色んなところに感じるものがあった。 そのひとつにこんなくだりがあった。
とうとう言われてしまった。
「○○ちゃんもいい子にしていないと、あんなふうになっちゃうよ」
診察を受けに行った病院のトイレで転びそうになり、母に支えてもらっていた時だった。
必死につかまっているわたしの横で、赤いチェックの服を着た30代くらいのおばさんが、
小さい男の子に、ささやいていた。
悲しくて、惨めだった。
「子どもにあんな言い方をして育てていたら、自分が将来年とって体が不自由になった時、
いいお母さんにしとらんかったからそうなった、と間違った教えが自分にもどってくるんよ」
と母は慰めてくれた。
これからも、こんなことはたびたびあると思う。
幼い子が自分と違う人間に出会った時、珍しくてジロジロ見るのは仕方ないとしても、大人
から子供の躾の材料にされたのは初めてだったので、こたえた。
今更ながら、天国では自由に身体を動かして、今まで出来なかったことをひとつずつ、噛み締めながら遊んでいる、そんな彼女を想いつつ・・・。
ご冥福をお祈りします。




















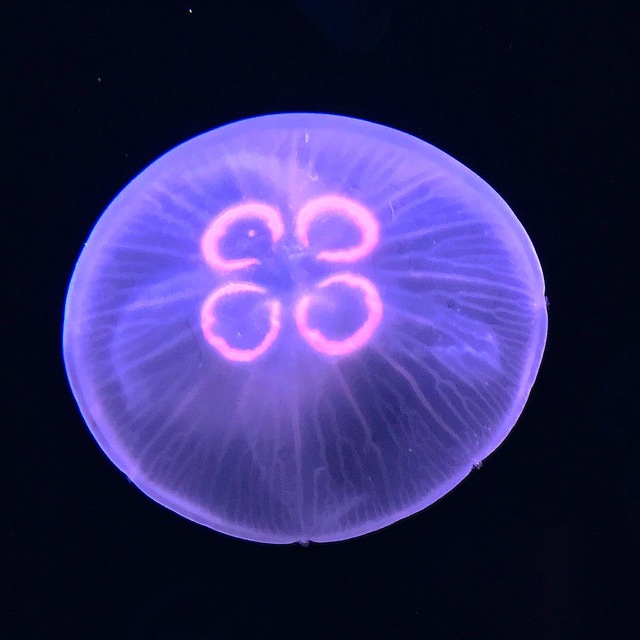





おかあさんの書かれた「いのちのハードル」もとても感動的でしたよ。
普通の生活ができることのありがたさを普段はつい忘れてしまいますね。読んでいて自分のこと反省させられました。
心ない大人もいます。幼い子がじろじろ見る、というのも、これは躾とか親やまわりの大人(環境も含めた)の問題のような気もしています。
赤ちゃんだったら、何もわからない、、、とはいえ、「奇異の目」を向けるということは決してないと思うので。
難しいです。自分がそのような立場になったら…という想像がうまくできません。
同じようにこの世に生を受け、青春と一番楽しいときに、ハンディを背負ってしまった彼女に罪は無いと思います。
それでも強く生きようと、そして彼女を取り巻く人たちも
彼女と共に強くなったと思うのです。
彼女が献体がこの病気の解明に少しでも役立てばいいと願うばかりです。
確かに難しい問題ですね。
この原作の映画版を観なかったことが非常に悔やまれてなりません。
また、東京近郊でこの映画が上映されることを祈ります!
彼女の献体は絶対に無駄になっていないはずです。
頑張って下さい!
私も障害者なので、亜也さんの気持ちが分かる部分(やむなく転校したり、病院での子供と親のやり取りなど)もありますが、辛い状況の中でも自分の人生に絶望せず、光を保って生き続けた姿はとても尊敬しています。
亜也さんの思いはまだ生き続けているんだなと実感できる本ですよね。今後ともよろしくお願いいたします。
ハンディを背負ってもなおかつ諦めないでポジティブに生きる姿勢に感動しました。
この本を読んで彼女は心の中で生き続けています。
また人生に挫けそうになったら読んでみたいと思います!
こちらこそよろしくお願いします。
映画ネタばかりですけど(笑)
読み終わってすぐの感情と少し経ってからの気持ちというのは違いますね。
もう少し、優しくなろうと思いました。
出来るだけ、自分が出来ることは自分でしよう。
助けられることが出来るのであれば、少しでも役に立ったらなぁと思うようになりました。
そういった気持ちの変化も大切ですよね。
これを機会にまた、遊びに来ますね。
なかなか普段日常生活で手助けをと思うのですが、
勇気を持って接することが出来ないのが現実です。
せめてお年寄りには優しく出来るように心がけています。
でも自分ひとりではダメですねぇ・・・
みんながそう思わないと。
“優先席”って意味から理解させないと(怒)?!