前回の最後に述べた3点のうち3に関してです。どちらかと言えば。
混合診療解禁に対する反対派も賛成派も、解禁すれば保険外診療が増えるという点では一致しています。そのことを良しとするか異なとするかで賛否が分かれるわけです。解禁派の経済同友会の提言1)では、「社会保障としての医療費」と「多様な需要に応える医療費」に分けて、「公的な医療の保証とそれを支える財政的持続性の向上」のために「(健康保険の)適用対象の選別」と「公的保険の範囲を最適化」をする必要があるとしています。これは日本医師会に言わせれば「現在健康保険でみている療養までも、「保険外」とする」2b)という当然に否定すべき考えとなるわけです。
しかし日本医師会が「すべての医療」を健康保険適用とすべきとしているのかどうかは、はっきりしないところがあります。「すべての国民が公平・平等により良い医療を受けられる環境」2a)というのは極端に考えると、すべての国民に必要な(望むような?)医療を無料で(費用を気にせずに)提供できる環境3)、のことかとも想像できます。が、現実には例えば前回紹介の上昌広の論説に挙げられたような「不妊治療、出産、美容整形、人間ドック」などもすべて保険内にすべきと考えてはいないように思えます。少なくとも、そのための運動や提言は行っていないように見えます。
上述の発言からはっきりしているのは、日本医師会は「現在保険内の医療はすべて保険内であるべきものだ」と考え、経済同友会は「現在保険内の医療にも保険外とする方がよいものがある」と考えているということです。まあ、文字通り「すべての医療」を保険内とするのは非現実的としても、それではどのような医療を保険内とすべきなのでしょうか?
そもそも保険というものの本質は、個人にとっては希だが集団の中では確実に生じることがあり、ひとたび生じれば個人には賄えないような負担が生じる、という事態に対して、加入者全員がコストを負担するという、互助のための仕組みです。多くの加入者にとっては、使わずに掛け捨てになってしまえばラッキー、と言うべき性質のもので、いわば万が一でも金の心配だけは大丈夫という安心を買っているわけです。間違っても、「払った保険料より多く受け取らないと損」と考えるべき筋合いのものではありません。日本医師会のアピールでも述べられているように、「「自分だけが満足したい」という発想ではなく、常に「社会としてどうあるべきか」という視点を持たなければならない」というべきでしょう。
単純な数学からわかるように、加入者が多く、その中で起きる確率が低い事態ほど保険料は安く済みます。公的な健康保険の場合は国民全員が加入者となることで、相当高額な保証でも妥当な保険料で賄えるようにできるわけです。さらに保険料を所得に相関させることで弱者救済もできる仕組みになっています。
となれば、優先して保険適用すべき医療とは、まず高額なもの、そして命にかかわるもの、生活が著しく困難になるようなもの、に対する医療であることは間違いありません。「家を売って高度医療を受ける」か「死ぬ」かの選択肢の自由4)、などという状態はあってはならないことです。逆の端で、例えば風邪、腹痛、便秘、水虫、などのあまりコストのかからないような治療はどうでしょうか? 病気として重大ではないとは必ずしも言えませんが治療費用は医療の中では低いほうです。このようなものは、少なくとも自費で払える余裕のある人には保険を使うのは遠慮してもらうという考えはできそうです。とはいえ、コストが受診を躊躇させる事態というのもあまりよろしくない、という問題もあります。素人判断で軽い症状だと思っても実は重病ということもあり得るからです。また風邪のような伝染病、特にもっと重くなりうる伝染病などでは、感染から社会を守るという観点から、無料でいいから強制的にでも医療を受けさせる必要がある場合もあります。
さらに前回も触れた「それ以上の医療」にまで保険から支払うべきかという問題もあります。いうまでもなく、こういう支払いは他でもない我々が月々支払っている保険料の中から出ていくのです。しかし具体的に何が「それ以上の医療」かは判断が難しい問題ですし、境界領域のものがあることも当然だと考えるべきでしょう。
こう考えてくると、質やコストの異なる医療に対して一律な自己負担率が適用されていることが、実は大きな問題ではないかと思えてきます。まあ高額医療費の補助のおかげで、一度に高い費用がかかる場合は実質的自己負担率はぐーっと下がるのですが。しかし一般的には、3割自己負担(保険内)と10割自己負担(保険外)とだけで中間の価格がないのです。ここはゼロか1かではなく、もっと連続的な選択ができた方が望ましいのではないでしょうか?
そこでまず、低額な治療ほど自己負担率を高くすれば良いだろうとの考えが生まれます。すると保険会計全体としては、低額治療にかける費用を少なくして高額治療に重点的に配分することで費用を少なくできることになります。被保険者の立場からは、支払える価格の治療は自費分を多くするかわりに、自己負担だけでは破産しそうな治療も安心して受けることができる、ことになります。もちろん比較的低額な治療でも支払い困難な人もいるでしょう。その場合は健康保険という枠組みとは別の手段で何らかの補助なり援助なりをするのが筋でしょう。現に現在の制度でも、自己負担率に所得による差などはなく、低所得者については別の枠組みでの援助があるのですから。なおこの価格反比例の自己負担率を決めるときには、実際にかかる費用の大小と患者が実際に支払う金額の大小とが逆転するような不合理なことがないように決めるのが理想です。計算は単純な方がいい(2011/01/07)でも述べたように、連続関数を使えば単純だと思います。まあ、価格を1回の診療のものとするか1ヶ月分とするか他の方法にするか、という問題はありますが。
また例えば外国では承認済みで国内では未承認という治療法について、取りあえずは完全な保険内よりも高い自己負担率で適用しておく、という手段も考えられます。逆に、昔は標準的な治療法だったが今ではもっと適切な治療法ができていて退場願った方がよい治療法もあるかも知れません。そのような場合も自己負担率を段階的に上げていってついには十割、つまり保険外にする、というやり方が考えられます。
価格だけで決めるならあまり考える必要はありませんが、質も考慮するとなると具体的には専門家に都度判断してもらうしかなくて、そのコストがかかることにはなります。でもそれは現在でも保険点数の決定では必要なことですね。
------------
1) http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/pdf/100421b.pdf
経済同友会 2010/04 「抜本的な医療制度改革への提言」
2a) 日本医師会はこう考えています
2b) 日本医師会 混合診療って何? Q&Aの3番
3) 例えば浜田秀夫「混合診療問題を原則論からわかりやすく国民に示そう」(2005/03/08)より、現保険診療への評価
これだといくら治療費がかかるか心配することなく医療が受けられる。
保険証一枚でだれもが平等にどんな名医にも診てもらえる。
4) 混合診療解禁で保険診療が縮小されるのはガチ(2007-11-15)
混合診療解禁に対する反対派も賛成派も、解禁すれば保険外診療が増えるという点では一致しています。そのことを良しとするか異なとするかで賛否が分かれるわけです。解禁派の経済同友会の提言1)では、「社会保障としての医療費」と「多様な需要に応える医療費」に分けて、「公的な医療の保証とそれを支える財政的持続性の向上」のために「(健康保険の)適用対象の選別」と「公的保険の範囲を最適化」をする必要があるとしています。これは日本医師会に言わせれば「現在健康保険でみている療養までも、「保険外」とする」2b)という当然に否定すべき考えとなるわけです。
しかし日本医師会が「すべての医療」を健康保険適用とすべきとしているのかどうかは、はっきりしないところがあります。「すべての国民が公平・平等により良い医療を受けられる環境」2a)というのは極端に考えると、すべての国民に必要な(望むような?)医療を無料で(費用を気にせずに)提供できる環境3)、のことかとも想像できます。が、現実には例えば前回紹介の上昌広の論説に挙げられたような「不妊治療、出産、美容整形、人間ドック」などもすべて保険内にすべきと考えてはいないように思えます。少なくとも、そのための運動や提言は行っていないように見えます。
上述の発言からはっきりしているのは、日本医師会は「現在保険内の医療はすべて保険内であるべきものだ」と考え、経済同友会は「現在保険内の医療にも保険外とする方がよいものがある」と考えているということです。まあ、文字通り「すべての医療」を保険内とするのは非現実的としても、それではどのような医療を保険内とすべきなのでしょうか?
そもそも保険というものの本質は、個人にとっては希だが集団の中では確実に生じることがあり、ひとたび生じれば個人には賄えないような負担が生じる、という事態に対して、加入者全員がコストを負担するという、互助のための仕組みです。多くの加入者にとっては、使わずに掛け捨てになってしまえばラッキー、と言うべき性質のもので、いわば万が一でも金の心配だけは大丈夫という安心を買っているわけです。間違っても、「払った保険料より多く受け取らないと損」と考えるべき筋合いのものではありません。日本医師会のアピールでも述べられているように、「「自分だけが満足したい」という発想ではなく、常に「社会としてどうあるべきか」という視点を持たなければならない」というべきでしょう。
単純な数学からわかるように、加入者が多く、その中で起きる確率が低い事態ほど保険料は安く済みます。公的な健康保険の場合は国民全員が加入者となることで、相当高額な保証でも妥当な保険料で賄えるようにできるわけです。さらに保険料を所得に相関させることで弱者救済もできる仕組みになっています。
となれば、優先して保険適用すべき医療とは、まず高額なもの、そして命にかかわるもの、生活が著しく困難になるようなもの、に対する医療であることは間違いありません。「家を売って高度医療を受ける」か「死ぬ」かの選択肢の自由4)、などという状態はあってはならないことです。逆の端で、例えば風邪、腹痛、便秘、水虫、などのあまりコストのかからないような治療はどうでしょうか? 病気として重大ではないとは必ずしも言えませんが治療費用は医療の中では低いほうです。このようなものは、少なくとも自費で払える余裕のある人には保険を使うのは遠慮してもらうという考えはできそうです。とはいえ、コストが受診を躊躇させる事態というのもあまりよろしくない、という問題もあります。素人判断で軽い症状だと思っても実は重病ということもあり得るからです。また風邪のような伝染病、特にもっと重くなりうる伝染病などでは、感染から社会を守るという観点から、無料でいいから強制的にでも医療を受けさせる必要がある場合もあります。
さらに前回も触れた「それ以上の医療」にまで保険から支払うべきかという問題もあります。いうまでもなく、こういう支払いは他でもない我々が月々支払っている保険料の中から出ていくのです。しかし具体的に何が「それ以上の医療」かは判断が難しい問題ですし、境界領域のものがあることも当然だと考えるべきでしょう。
こう考えてくると、質やコストの異なる医療に対して一律な自己負担率が適用されていることが、実は大きな問題ではないかと思えてきます。まあ高額医療費の補助のおかげで、一度に高い費用がかかる場合は実質的自己負担率はぐーっと下がるのですが。しかし一般的には、3割自己負担(保険内)と10割自己負担(保険外)とだけで中間の価格がないのです。ここはゼロか1かではなく、もっと連続的な選択ができた方が望ましいのではないでしょうか?
そこでまず、低額な治療ほど自己負担率を高くすれば良いだろうとの考えが生まれます。すると保険会計全体としては、低額治療にかける費用を少なくして高額治療に重点的に配分することで費用を少なくできることになります。被保険者の立場からは、支払える価格の治療は自費分を多くするかわりに、自己負担だけでは破産しそうな治療も安心して受けることができる、ことになります。もちろん比較的低額な治療でも支払い困難な人もいるでしょう。その場合は健康保険という枠組みとは別の手段で何らかの補助なり援助なりをするのが筋でしょう。現に現在の制度でも、自己負担率に所得による差などはなく、低所得者については別の枠組みでの援助があるのですから。なおこの価格反比例の自己負担率を決めるときには、実際にかかる費用の大小と患者が実際に支払う金額の大小とが逆転するような不合理なことがないように決めるのが理想です。計算は単純な方がいい(2011/01/07)でも述べたように、連続関数を使えば単純だと思います。まあ、価格を1回の診療のものとするか1ヶ月分とするか他の方法にするか、という問題はありますが。
また例えば外国では承認済みで国内では未承認という治療法について、取りあえずは完全な保険内よりも高い自己負担率で適用しておく、という手段も考えられます。逆に、昔は標準的な治療法だったが今ではもっと適切な治療法ができていて退場願った方がよい治療法もあるかも知れません。そのような場合も自己負担率を段階的に上げていってついには十割、つまり保険外にする、というやり方が考えられます。
価格だけで決めるならあまり考える必要はありませんが、質も考慮するとなると具体的には専門家に都度判断してもらうしかなくて、そのコストがかかることにはなります。でもそれは現在でも保険点数の決定では必要なことですね。
------------
1) http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/pdf/100421b.pdf
経済同友会 2010/04 「抜本的な医療制度改革への提言」
2a) 日本医師会はこう考えています
2b) 日本医師会 混合診療って何? Q&Aの3番
3) 例えば浜田秀夫「混合診療問題を原則論からわかりやすく国民に示そう」(2005/03/08)より、現保険診療への評価
これだといくら治療費がかかるか心配することなく医療が受けられる。
保険証一枚でだれもが平等にどんな名医にも診てもらえる。
4) 混合診療解禁で保険診療が縮小されるのはガチ(2007-11-15)










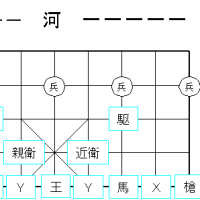
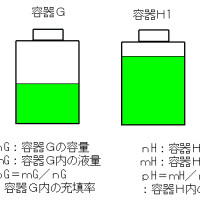
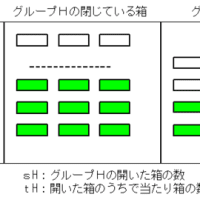
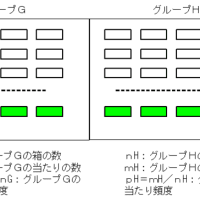
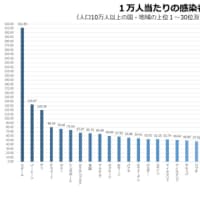
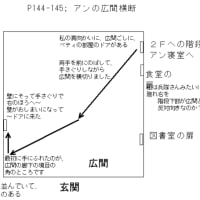
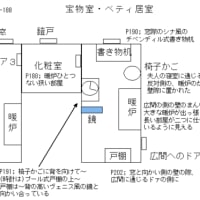
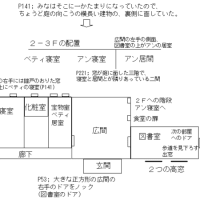
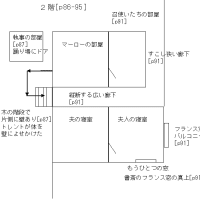
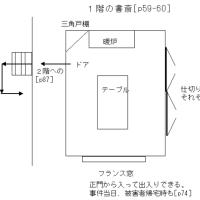






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます