2011-11-15 混合診療のメリットとデメリットおよび日本医師会が混合診療解禁に反対する理由で、NATROMさんが混合診療のことを書いています。この議論が紛糾する要因のひとつに、いわゆる保険外診療の具体的事例について、各論者が想定する集合が人により異なることがあるのではないでしょうか。調べたところ、保険外診療は次の3つないし4つの性質を持つものにわけられそうです。
a) 有効性が確からしいが先端技術なのでまだ保険外のもの
b) 有効性が不確実またはないことが専門家間では確実視されているため、保険外のもの
c) 有効性が確実だが治療だけの目的には必須と見なされないため、保険外のもの
c') 予防のための医療
NATROMさんの記事で紹介されている解禁派の池田信夫氏などは、aだけを想定して議論しているように見えます。bにはいわゆるトンデモ医療も含まれていて、NATROMさんのブログなどでその危険性が指摘されています。そしてcの典型的例は歯科医療での審美的目的の医療などです。ただし歯科医療では例えば金歯のように性能が優れているらしいものが保険外ということも多くて門外漢は戸惑うのですが、愛知県保険医協会による【05.07.05】Q&Aで考える混合診療問題2)によれば、「歯科では、すぐれた治療材料である金合金やセラミックスを使った治療、あるいは新しい医療技術が、政府の歯科医療費抑制策のもとで保険導入されてこなかったことが一番の理由」とされています。それゆえか、日本歯科技工士会では、有効なのに保険適用されていない診療もあるという現実を前提として混合診療解禁を主張しています3)。それに対して日本医師会等の見解は、「必要なものは保険適用させていくのが筋で、現状肯定のまま解禁するのはデメリットが大きい」という趣旨に見えます。では日本歯科医師会はどうかと言うと、統一見解は表明していません。どうも歯科と他とでは事情が違うらしいです。なお、日本歯科技工士会の見解の中でも「予防に保険適用も考えるべき」という趣旨の文章があり、「必要なものは保険適用させていくのが筋」という点は日本医師会等と同様な立場に見えます。
さて金歯などが有効なのに保険外であることの説得力ある理由付けとしては、(厚生労働省の表向きの見解は知りませんが)俗な言葉で「保険にするには贅沢だ」という理由が考えられます。言うなれば、「治すのに必要な最低限のものは保険適用して良いが、それ以上のQOL(Quality of Life)改善のためのものは適用しなくても良い」という発想です。喩えるならば「生きていくのに最低限必要なパンは全国民に平等に配給するが、味を追求する食品は自分の金で買え」というところでしょうか。確かに「限りある保険財源の中から"贅沢な"医療に金を出すのはいかがなものか」と言われると頷かざるをえない面があります。
とはいえ、医療においてどこからが贅沢なのかは難しいところで、技術の発達によっても社会通念も変わるでしょう。ただ歯科のように治癒するだけなら治療法が確立したものが多い分野では、このような「それ以上の治療」の比率が多く、保険適用するか否かで迷う事例が多いとは言えるでしょう。難病治療分野のように、最低限の医療でさえ確立していないという分野では、贅沢という理由で保険外にすることが正当化されるものなどあり得ません。甲状腺ガンをできるだけ傷口を小さくして手術するとか、乳ガンをできるだけ元の姿を残して治療するとかいう方法も進歩していますが、これを"贅沢"とするのも不当なようにも思えます。いや、これらは今も、効果が確立されたものは保険適用でしょうけど。
保険の点数が不適切で硬直化しているために自由競争によるサービスや技術の向上が促進されない、という議論があります。例えば日本経済新聞の経済教室欄で、「医療を考える」と題した4つの論説が連載されましたが5-8)、その中の上昌広の論説では、「わが国の不妊治療が世界最高水準なのは、健康保険が適用されないため、医療機関が独自に価格を設定できることも一因である」、「出産、美容整形、人間ドックでも同様の傾向があるが、共通するのはいずれも自費診療であるということだ。これらの分野におけるわが国の技術水準は高く、医療機関の大きな収益源となっている」、との記載があります。この評価の妥当性を示す根拠やデータを私は知りませんし、上特任教授の評価基準も不明ではあります。が、彼の挙げている分野が「それ以上の治療」の比率が多い分野だということは言えると思います。この場合消費者は、サービスの質を我慢してコストを押さえるという選択も可能だし、逆の選択も可能です。また選択するだけの時間と心の余裕を持てる場合が多いのです。確かにこんな場合には、自由競争により質の向上を図ることは国民の生活の質の向上につながりそうです。
しかし最上の質でも死を免れることという場合や緊急医療の場合では、消費者には選択する余裕などありません。そしてまたこんな場合に限って情報の非対称性も大きくなります。また、このような難病の治療法確立のために日夜奮闘している人達から見ると、必要なはずの分野を差し置いて上記のような「それ以上の治療」に資源が注入されて技術が発達してゆくのは、あるいは歯がゆい想いになるかも知れません。
なお上記の問題は保険適用するか否かというよりは、保険内であれなんであれ適切な価格をどう決めるかという問題でしょう。まあ管理された保険点数制という枠組みの中では市場原理の助けを得にくいので、適切な価格を決めにくいという問題はあるかも知れません。しかし保険内でも工夫はできるはずだとも考えます。
考察の不十分な状態でアレですが、今考えている結論めいたことをいくつか挙げます。
1. 保険内であれ保険外であれ、医療(ないし医療と称するもの)の質を担保する仕組みは必須である。
2. 保険適用で所得にかかわらずアクセスできるべき医療に優先度を付けるとしたら、優先すべきは命にかかわるもの、重篤なもの、高額なもの、であろう。
3. 素直に考えると混合診療禁止というのは不自然に感じられ、その妥当性の主張には相当強い論理が必要だろう
この3点については、また改めて詳しく書いて見ようかと思います。
なお、3についての日本医師会の見解ですが、アピールは抽象的で参考になりませんが、Q&Aの3番が具体的な理由になっています。この内容はRef-2と同じようなものです。またこの理由の中で「現在健康保険でみている療養までも、「保険外」とする可能性」というのは、「解禁反対は開業医の市場が奪われることを恐れたため」と似たような陰謀論にも見えますが、その点についてはNATROMさんによる混合診療解禁で保険診療が縮小されるのはガチ(2007-11-15)が説得力がありそうです。
--参考文献------
Ref-1) 日本医師会が混合診療解禁に反対する理由
Ref-2) 【05.07.05】Q&Aで考える混合診療問題
Ref-3) 混合診療について考えてください(2005/01/20)日本歯科技工士会
Ref-4) 「混合診療をめぐる世論」(2010/07/14)
Ref-5) 小塩隆士(一橋大教授・公共経済学)「医療を考える1.所得に応じた負担徹底を」日本経済新聞(2011/12/06),経済教室欄
Ref-6) 印南一路(慶應義塾大教授・医療政策)「医療を考える2.診療報酬通じ失向上促せ」日本経済新聞(2011/12/07),経済教室欄
Ref-7) 上昌広(東京大特任教授・医療ガバナンス論)「医療を考える3.混合診療、成長戦略の軸に」日本経済新聞(2011/12/09),経済教室欄
Ref-8) 林良造(東京大特任教授)「医療を考える4.産業化促す制度改革急げ」日本経済新聞(2011/12/13),経済教室欄
a) 有効性が確からしいが先端技術なのでまだ保険外のもの
b) 有効性が不確実またはないことが専門家間では確実視されているため、保険外のもの
c) 有効性が確実だが治療だけの目的には必須と見なされないため、保険外のもの
c') 予防のための医療
NATROMさんの記事で紹介されている解禁派の池田信夫氏などは、aだけを想定して議論しているように見えます。bにはいわゆるトンデモ医療も含まれていて、NATROMさんのブログなどでその危険性が指摘されています。そしてcの典型的例は歯科医療での審美的目的の医療などです。ただし歯科医療では例えば金歯のように性能が優れているらしいものが保険外ということも多くて門外漢は戸惑うのですが、愛知県保険医協会による【05.07.05】Q&Aで考える混合診療問題2)によれば、「歯科では、すぐれた治療材料である金合金やセラミックスを使った治療、あるいは新しい医療技術が、政府の歯科医療費抑制策のもとで保険導入されてこなかったことが一番の理由」とされています。それゆえか、日本歯科技工士会では、有効なのに保険適用されていない診療もあるという現実を前提として混合診療解禁を主張しています3)。それに対して日本医師会等の見解は、「必要なものは保険適用させていくのが筋で、現状肯定のまま解禁するのはデメリットが大きい」という趣旨に見えます。では日本歯科医師会はどうかと言うと、統一見解は表明していません。どうも歯科と他とでは事情が違うらしいです。なお、日本歯科技工士会の見解の中でも「予防に保険適用も考えるべき」という趣旨の文章があり、「必要なものは保険適用させていくのが筋」という点は日本医師会等と同様な立場に見えます。
さて金歯などが有効なのに保険外であることの説得力ある理由付けとしては、(厚生労働省の表向きの見解は知りませんが)俗な言葉で「保険にするには贅沢だ」という理由が考えられます。言うなれば、「治すのに必要な最低限のものは保険適用して良いが、それ以上のQOL(Quality of Life)改善のためのものは適用しなくても良い」という発想です。喩えるならば「生きていくのに最低限必要なパンは全国民に平等に配給するが、味を追求する食品は自分の金で買え」というところでしょうか。確かに「限りある保険財源の中から"贅沢な"医療に金を出すのはいかがなものか」と言われると頷かざるをえない面があります。
とはいえ、医療においてどこからが贅沢なのかは難しいところで、技術の発達によっても社会通念も変わるでしょう。ただ歯科のように治癒するだけなら治療法が確立したものが多い分野では、このような「それ以上の治療」の比率が多く、保険適用するか否かで迷う事例が多いとは言えるでしょう。難病治療分野のように、最低限の医療でさえ確立していないという分野では、贅沢という理由で保険外にすることが正当化されるものなどあり得ません。甲状腺ガンをできるだけ傷口を小さくして手術するとか、乳ガンをできるだけ元の姿を残して治療するとかいう方法も進歩していますが、これを"贅沢"とするのも不当なようにも思えます。いや、これらは今も、効果が確立されたものは保険適用でしょうけど。
保険の点数が不適切で硬直化しているために自由競争によるサービスや技術の向上が促進されない、という議論があります。例えば日本経済新聞の経済教室欄で、「医療を考える」と題した4つの論説が連載されましたが5-8)、その中の上昌広の論説では、「わが国の不妊治療が世界最高水準なのは、健康保険が適用されないため、医療機関が独自に価格を設定できることも一因である」、「出産、美容整形、人間ドックでも同様の傾向があるが、共通するのはいずれも自費診療であるということだ。これらの分野におけるわが国の技術水準は高く、医療機関の大きな収益源となっている」、との記載があります。この評価の妥当性を示す根拠やデータを私は知りませんし、上特任教授の評価基準も不明ではあります。が、彼の挙げている分野が「それ以上の治療」の比率が多い分野だということは言えると思います。この場合消費者は、サービスの質を我慢してコストを押さえるという選択も可能だし、逆の選択も可能です。また選択するだけの時間と心の余裕を持てる場合が多いのです。確かにこんな場合には、自由競争により質の向上を図ることは国民の生活の質の向上につながりそうです。
しかし最上の質でも死を免れることという場合や緊急医療の場合では、消費者には選択する余裕などありません。そしてまたこんな場合に限って情報の非対称性も大きくなります。また、このような難病の治療法確立のために日夜奮闘している人達から見ると、必要なはずの分野を差し置いて上記のような「それ以上の治療」に資源が注入されて技術が発達してゆくのは、あるいは歯がゆい想いになるかも知れません。
なお上記の問題は保険適用するか否かというよりは、保険内であれなんであれ適切な価格をどう決めるかという問題でしょう。まあ管理された保険点数制という枠組みの中では市場原理の助けを得にくいので、適切な価格を決めにくいという問題はあるかも知れません。しかし保険内でも工夫はできるはずだとも考えます。
考察の不十分な状態でアレですが、今考えている結論めいたことをいくつか挙げます。
1. 保険内であれ保険外であれ、医療(ないし医療と称するもの)の質を担保する仕組みは必須である。
2. 保険適用で所得にかかわらずアクセスできるべき医療に優先度を付けるとしたら、優先すべきは命にかかわるもの、重篤なもの、高額なもの、であろう。
3. 素直に考えると混合診療禁止というのは不自然に感じられ、その妥当性の主張には相当強い論理が必要だろう
この3点については、また改めて詳しく書いて見ようかと思います。
なお、3についての日本医師会の見解ですが、アピールは抽象的で参考になりませんが、Q&Aの3番が具体的な理由になっています。この内容はRef-2と同じようなものです。またこの理由の中で「現在健康保険でみている療養までも、「保険外」とする可能性」というのは、「解禁反対は開業医の市場が奪われることを恐れたため」と似たような陰謀論にも見えますが、その点についてはNATROMさんによる混合診療解禁で保険診療が縮小されるのはガチ(2007-11-15)が説得力がありそうです。
--参考文献------
Ref-1) 日本医師会が混合診療解禁に反対する理由
Ref-2) 【05.07.05】Q&Aで考える混合診療問題
Ref-3) 混合診療について考えてください(2005/01/20)日本歯科技工士会
Ref-4) 「混合診療をめぐる世論」(2010/07/14)
Ref-5) 小塩隆士(一橋大教授・公共経済学)「医療を考える1.所得に応じた負担徹底を」日本経済新聞(2011/12/06),経済教室欄
Ref-6) 印南一路(慶應義塾大教授・医療政策)「医療を考える2.診療報酬通じ失向上促せ」日本経済新聞(2011/12/07),経済教室欄
Ref-7) 上昌広(東京大特任教授・医療ガバナンス論)「医療を考える3.混合診療、成長戦略の軸に」日本経済新聞(2011/12/09),経済教室欄
Ref-8) 林良造(東京大特任教授)「医療を考える4.産業化促す制度改革急げ」日本経済新聞(2011/12/13),経済教室欄










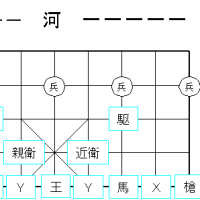
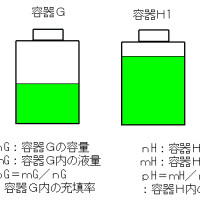
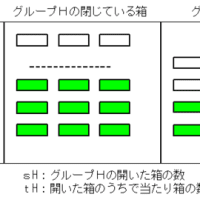
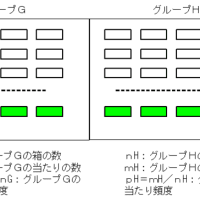
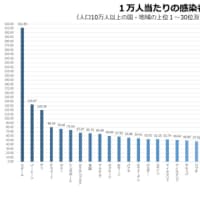
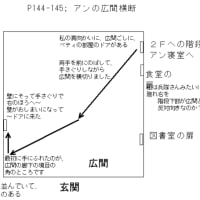
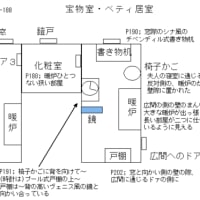
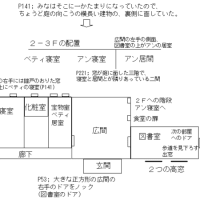
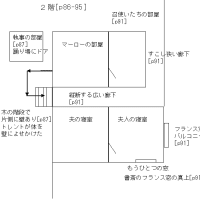
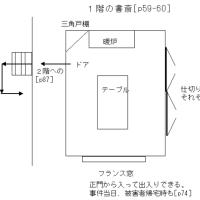







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます