健康保険について現物給付と現金給付という概念があります。この2つの違いの簡単な説明は色々な健康保険組合のサイトなどにも記載されていますが、私が一番わかりやすかったのはこちら休日社労士Web事務所の医療保険のひみつ(9) - 現物給付と現金給付1)の記事です。
すなわち、保険が医療機関に支払うべき金額[=全医療価格×(1-自己負担率)]の移動経路を考えると次の3通りがあります。
1.保険機関から医療機関に直接支払う
2.患者がまず医療機関に支払い、事後に保険機関から患者に支払う
3.保険機関から事前に患者に支払い、患者が医療機関に支払う
1が現物給付で2と3が現金給付です。日本の公的保険は通常の医療については1の方式ですが、例えば民間の入院保険や手術保険などは2の方式です。2の場合には患者は手元資金がないと、いくら後から金が入るとわかっていても支払いができません。逆に医療機関はしばらく後でないと入金がありませんし、そのために保険機関に請求するなどの手続きが必要です。とはいえ、この2点の不便さは医療機関の方が患者個人よりもうまく処理できるのはいうまでもありません。3の場合なら患者に手元資金が不足することはありませんが、今度は医療機関にとって入金のさらなる遅れや極端には未払いのリスクが大きくなるでしょう。
では現金給付の方が適切なものとはどんなものかというと、次のようなものになるのではないでしょうか?
1.使途が自由なもの
2.使途と金額が事前にわかるもの
3.支払い金額が費用によらないもの
医療保険の中なら出産育児一時金や傷病手当金が1でしょう。また年金、失業保険、生活保護手当、なども1に入るでしょう。2に該当するものというと例が思いつきにくいですが、例えば教育バウチャーなどは2の性質が一部あるといえるでしょう。3は日本の民間の入院保険などです。
ともかく現物給付の利点は、患者にとって手続きが簡単になり、手元資金が少なくて済む、という点です。すると浜田秀夫「混合診療問題を原則論からわかりやすく国民に示そう」(2005/03/08)2)で述べている「現物給付と現金給付こそ保険診療と自由診療それぞれの本質」という話や(現物給付であるがゆえに)治療費の心配がないとか「(現物給付であるがゆえに)だれもが平等にどんな名医にも診てもらえる」とかいう表現は、明らかに変です。自己負担率が0でない以上は治療費の心配がないことはありませんし、どんな名医にも診てもらえるかどうかはむしろ医療体制の充実度の要因が大きいでしょう。
また「(経済界などの確信派は)現物給付制度から現金給付へ持っていこうと考えている」という話も変です。民間保険でも消費者に魅力のある現物給付の方が売り物になりやすいはずだからです。現にアメリカの保険制度を解説したサイト3a,3b)によれば、管理医療型民間保険のHMOは現物給付ですし、「ほとんどの診療所や病院は保険加入者に対してキャッシュレスサービスを設けています3c)」との記事もあります。またフランスにおいては、公的保健でも現金給付がありますし(Ref-4[5/15])、民間保険(共済保険)でも第三者支払い制度という名の現物給付があります(Ref-4[6/15])。ちなみにHMOに対する、「医師の治療内容に対する管理が厳しすぎる」「コスト削減が優先されすぎ」という不満3a)は、日本の公的医療保険の診療報酬制度でも運用次第で出てきそうではあります。
ちなみにフランスでは医療の種類により自己負担率が異なっていて、12/25の記事での私の提案もまんざら非現実的なものではなさそうです。具体的には給付割合が、入院80%、開業医による一般的医療行為70%、一般薬剤65%、胃薬など医学的な貢献度が低いとみなされる薬剤35%、予防のための検診等100%、です。
またちなみにRef-5aで紹介されるような複雑過ぎるのは不便ですねえ。特にネットワークの乱立は消費者には不便なはずで、クレジットカード会社の連携とか、日本でのIC乗車カードの連携みたいに消費者の利便性を増すような方向には、自由競争は働かないものなのでしょうか?日本でも生命保険等の種類が多すぎて、各人に最適の組み合わせを考えてくれるサービスなんてものが登場していますが、複雑化するとまたさらに余計な?サービスが増えるというか・・・。それが最高だという記事5b)もありますが(^_^)。Ref-5bの記事では米国の民間保険は寡占市場の弊害が出ているという評価なので、実は自由競争にはなっていないと言っているのですが、真偽のほどは私にはわかりません。
余談ですが、Ref-2の「もっとも派」「ちゃっかり派」「乱暴派」「確信派」「分からず屋派」という分類はなかなかおもしろかったので、元発言者青柳氏の言葉6)を紹介しておきます。なお、Ref-6には、3大学学長が先端医療についての規制緩和を要望した「医療保険制度等の規制緩和に関する要望書(2004/11/22)」の全文?が載っています。これは愛知県保険医協会の【05.07.05】Q&Aで考える混合診療問題のQ11への回答で「あらゆる医療が健康保険によって給付されることが理想だということを述べている」と記されている要望です。が、「あらゆる医療が」云々の原文がどうも見つかりません。12/25の記事で述べたことと関連しますが、「あらゆる医療」とはどの範囲なのかをぼんやりとでも示してもらわないと議論になりにくいですね。
なおRef-6の青柳氏やRef-2の浜田氏の議論は、「現物給付が最善」という妙な論理を前提にしているために受け入れにくいものになっています。ことの本質は医療にかかる費用全額を誰がどのように分担すべきかという問題なのに、70%分だけについて議論するのはずれていると思います。まあ自己負担率は0%にせよという主張とセットならば、それなりの整合性はあるでしょうけど。
と、今回はややとりとめがなくなりました。
------------
1) 医療保険のひみつ(9) - 現物給付と現金給付
2) 浜田秀夫「混合診療問題を原則論からわかりやすく国民に示そう」(2005/03/08)
3a) アメリカと日本の医療保険制度(概要)
3b) アメリカの健康保険制度
3c) アメリカの医療保険・福利厚生制度
4) 損保ジャパン総研クォータリー(2006/12,Vol46)「フランスにおける民間医療保険の動向(PDF)」
5a) アメリカ情報局米国の民間医療保険制度とメディケア、メディケイド(2008/02/05)
5b) アメリカの医療保険制度は最高だ!(2009/08/04)
6) 先見創意の会「混合診療問題について」
すなわち、保険が医療機関に支払うべき金額[=全医療価格×(1-自己負担率)]の移動経路を考えると次の3通りがあります。
1.保険機関から医療機関に直接支払う
2.患者がまず医療機関に支払い、事後に保険機関から患者に支払う
3.保険機関から事前に患者に支払い、患者が医療機関に支払う
1が現物給付で2と3が現金給付です。日本の公的保険は通常の医療については1の方式ですが、例えば民間の入院保険や手術保険などは2の方式です。2の場合には患者は手元資金がないと、いくら後から金が入るとわかっていても支払いができません。逆に医療機関はしばらく後でないと入金がありませんし、そのために保険機関に請求するなどの手続きが必要です。とはいえ、この2点の不便さは医療機関の方が患者個人よりもうまく処理できるのはいうまでもありません。3の場合なら患者に手元資金が不足することはありませんが、今度は医療機関にとって入金のさらなる遅れや極端には未払いのリスクが大きくなるでしょう。
では現金給付の方が適切なものとはどんなものかというと、次のようなものになるのではないでしょうか?
1.使途が自由なもの
2.使途と金額が事前にわかるもの
3.支払い金額が費用によらないもの
医療保険の中なら出産育児一時金や傷病手当金が1でしょう。また年金、失業保険、生活保護手当、なども1に入るでしょう。2に該当するものというと例が思いつきにくいですが、例えば教育バウチャーなどは2の性質が一部あるといえるでしょう。3は日本の民間の入院保険などです。
ともかく現物給付の利点は、患者にとって手続きが簡単になり、手元資金が少なくて済む、という点です。すると浜田秀夫「混合診療問題を原則論からわかりやすく国民に示そう」(2005/03/08)2)で述べている「現物給付と現金給付こそ保険診療と自由診療それぞれの本質」という話や(現物給付であるがゆえに)治療費の心配がないとか「(現物給付であるがゆえに)だれもが平等にどんな名医にも診てもらえる」とかいう表現は、明らかに変です。自己負担率が0でない以上は治療費の心配がないことはありませんし、どんな名医にも診てもらえるかどうかはむしろ医療体制の充実度の要因が大きいでしょう。
また「(経済界などの確信派は)現物給付制度から現金給付へ持っていこうと考えている」という話も変です。民間保険でも消費者に魅力のある現物給付の方が売り物になりやすいはずだからです。現にアメリカの保険制度を解説したサイト3a,3b)によれば、管理医療型民間保険のHMOは現物給付ですし、「ほとんどの診療所や病院は保険加入者に対してキャッシュレスサービスを設けています3c)」との記事もあります。またフランスにおいては、公的保健でも現金給付がありますし(Ref-4[5/15])、民間保険(共済保険)でも第三者支払い制度という名の現物給付があります(Ref-4[6/15])。ちなみにHMOに対する、「医師の治療内容に対する管理が厳しすぎる」「コスト削減が優先されすぎ」という不満3a)は、日本の公的医療保険の診療報酬制度でも運用次第で出てきそうではあります。
ちなみにフランスでは医療の種類により自己負担率が異なっていて、12/25の記事での私の提案もまんざら非現実的なものではなさそうです。具体的には給付割合が、入院80%、開業医による一般的医療行為70%、一般薬剤65%、胃薬など医学的な貢献度が低いとみなされる薬剤35%、予防のための検診等100%、です。
またちなみにRef-5aで紹介されるような複雑過ぎるのは不便ですねえ。特にネットワークの乱立は消費者には不便なはずで、クレジットカード会社の連携とか、日本でのIC乗車カードの連携みたいに消費者の利便性を増すような方向には、自由競争は働かないものなのでしょうか?日本でも生命保険等の種類が多すぎて、各人に最適の組み合わせを考えてくれるサービスなんてものが登場していますが、複雑化するとまたさらに余計な?サービスが増えるというか・・・。それが最高だという記事5b)もありますが(^_^)。Ref-5bの記事では米国の民間保険は寡占市場の弊害が出ているという評価なので、実は自由競争にはなっていないと言っているのですが、真偽のほどは私にはわかりません。
余談ですが、Ref-2の「もっとも派」「ちゃっかり派」「乱暴派」「確信派」「分からず屋派」という分類はなかなかおもしろかったので、元発言者青柳氏の言葉6)を紹介しておきます。なお、Ref-6には、3大学学長が先端医療についての規制緩和を要望した「医療保険制度等の規制緩和に関する要望書(2004/11/22)」の全文?が載っています。これは愛知県保険医協会の【05.07.05】Q&Aで考える混合診療問題のQ11への回答で「あらゆる医療が健康保険によって給付されることが理想だということを述べている」と記されている要望です。が、「あらゆる医療が」云々の原文がどうも見つかりません。12/25の記事で述べたことと関連しますが、「あらゆる医療」とはどの範囲なのかをぼんやりとでも示してもらわないと議論になりにくいですね。
なおRef-6の青柳氏やRef-2の浜田氏の議論は、「現物給付が最善」という妙な論理を前提にしているために受け入れにくいものになっています。ことの本質は医療にかかる費用全額を誰がどのように分担すべきかという問題なのに、70%分だけについて議論するのはずれていると思います。まあ自己負担率は0%にせよという主張とセットならば、それなりの整合性はあるでしょうけど。
と、今回はややとりとめがなくなりました。
------------
1) 医療保険のひみつ(9) - 現物給付と現金給付
2) 浜田秀夫「混合診療問題を原則論からわかりやすく国民に示そう」(2005/03/08)
3a) アメリカと日本の医療保険制度(概要)
3b) アメリカの健康保険制度
3c) アメリカの医療保険・福利厚生制度
4) 損保ジャパン総研クォータリー(2006/12,Vol46)「フランスにおける民間医療保険の動向(PDF)」
5a) アメリカ情報局米国の民間医療保険制度とメディケア、メディケイド(2008/02/05)
5b) アメリカの医療保険制度は最高だ!(2009/08/04)
6) 先見創意の会「混合診療問題について」










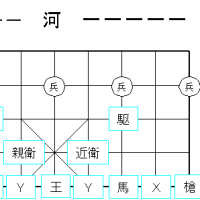
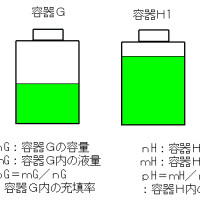
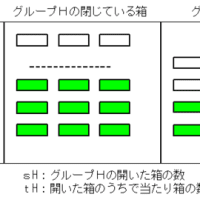
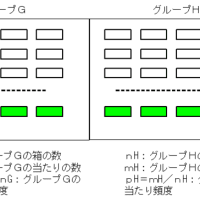
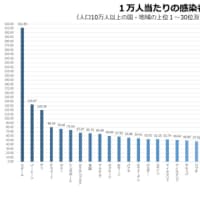
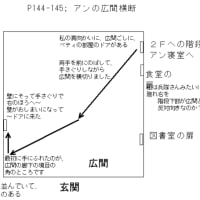
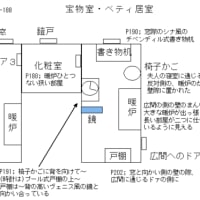
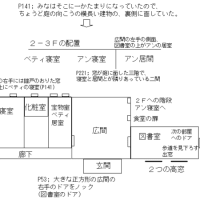
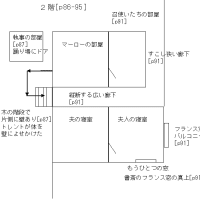
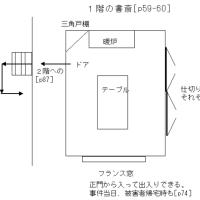






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます