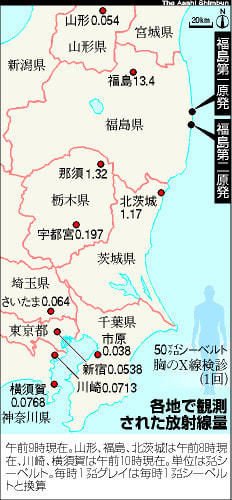4号機プール、爆発原因不明 天井残り放水効果も不透明
4号機プール、爆発原因不明 天井残り放水効果も不透明「
2011.3.20 23:20
東京消防庁が20日から放水を始めた東京電力福島第1原子力発電所4号機は、昨年11月まで発電していた高熱を帯びた使用済み核燃料が貯蔵プールにあり、放射性物質(放射能)露出の危険度が高いとの指摘が出ている。ただ、15日のプール付近の爆発で建屋が損壊したものの、3号機に比べ上部構造が残っており、放水の難易度は高い。また爆発の原因など分かっていないことが多い。震災時、定期検査のため停止していた4号機のプールには、使用済み燃料と新しい燃料を合わせて1535本が保管されており、17日から放水が始まった3号機の2・7倍もある。また、その一部には昨年11月30日の検査開始時に原子炉から出されたものがあり、「高い温度の燃料が保管されている状態」(東電)で、14日にはプールの水温が84度まで上がった。
このため、早い段階から冷却の必要性が指摘されてきたが、天井が残っていることからプールに水が届くのか疑問視されており、20日の放水の効果も不透明だ。
また4号機で起きた爆発は水面から燃料が露出し、過熱されて水素が発生したことが原因とみられている。ただ、16日に陸上自衛隊のヘリに同乗した東電社員は、プールの水面を確認し、燃料も露出していなかったとしている。これが事実なら爆発の説明がつかなくなる。原子力安全・保安院には「爆発でプールの壁が壊れ、別の場所にあった水が流れ込んできた」との分析もあるが、原因は依然、はっきりしない。
」
 3号機、蒸気の外部放出検討 格納容器保護を優先
3号機、蒸気の外部放出検討 格納容器保護を優先「
2011.3.20 23:18
東京電力福島第1原子力発電所3号機で20日、容器の圧力が高まり、内部の蒸気を外部に直接放出することが一時検討された。今回の重大事故でも初めての措置で、多くの放射性物質(放射能)が漏出する。実際には回避できたが、放射性物質を閉じ込めるための「最後の砦」である格納容器が内部の圧力で損傷するのを回避するため、東電から報告を受けた経済産業省原子量安全・保安院も「やむを得ない措置」との判断を示した。3号機の圧力容器には外部のポンプで海水の注入を続けているが、十分な水位を確保できず、燃料棒が一部露出して過熱して海水がどんどん蒸発している。蒸気は外側の格納容器内に出しており、蒸気がたまって圧力が上昇した。
これまで圧力が上昇した場合、格納容器につながっている圧力抑制室の水に蒸気を通し、放射性物質を吸収して放出していた。しかし、大量の海水を投入し続けたことで、抑制室で冷やされた蒸気が水になり、満杯になっている恐れがあるという。その場合、外部に蒸気を出せない。外部に蒸気を直接放出するため、格納容器上部の弁を開くのに2時間程度の時間がかかるという。
隣の2号機では圧力上昇で爆発が起き、圧力抑制室が破損し外部に放射性物資が漏出し続けている恐れがある。東電は3号機が同様の深刻な事態に陥るのを避けることを最優先にした。同原発は依然、余談の許さない状況が続いている。
」
 栃木県内のホウレンソウとカキナから基準値を超す放射性物質を検出
栃木県内のホウレンソウとカキナから基準値を超す放射性物質を検出「
2011.3.20 22:52
栃木県は20日、県内産のホウレンソウとカキナから食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性物質(ヨウ素、セシウム)が検出されたと発表した。県は農業団体に対し、ホウレンソウとカキナの出荷自粛などを要請した。また、ネギと原乳からも放射性物質が検出されたが、規制値以下だった。県は19~20日に県内15カ所でサンプル調査を実施。壬生町産のホウレンソウから、最高値で1キログラムあたり5700ベクレルの放射性ヨウ素(規制値2000ベクレル)と、同790ベクレルの放射性セシウム(同500ベクレル)を検出。また宇都宮、下野の両市と上三川町のホウレンソウからも3200~3900ベクレルのヨウ素と450~740ベクレルのセシウムを検出した。
さらに、佐野市産のカキナから規制値にあたる2000ベクレルの放射性ヨウ素を検出した。さくら、大田原、那須塩原の各市で採れたネギのほか、県北地域産の原乳からも放射性物質が検出されたが、いずれも規制値未満だったという。
福田富一知事は20日、県庁で記者会見し、サンプル調査結果について「最高値のホウレンソウを15グラムずつ1年間食べ続けても胃のレントゲン集団検診の1回分と同じ。健康にただちに害を及ぼすレベルではない」と述べ、冷静な対応を求めた。
」
 千葉県産のシュンギクに放射性物質 都内流通も「健康に影響なし」
千葉県産のシュンギクに放射性物質 都内流通も「健康に影響なし」「
2011.3.20 22:51
東京都は20日、千葉県旭市産のシュンギクから、食品衛生法に基づく暫定規制値を超える放射性物質が検出されたと発表した。都はこのシュンギクを販売禁止とし、回収作業をすすめている。都は、「すぐに健康に影響が生じるレベルではない」としている。都によると、このシュンギクからは1キロあたり4300ベクレルの放射性ヨウ素を検出。18日に築地市場(中央区)で入荷し、19日に市場内で流通しており、3キロ入りの段ボール30ケースで計90キロが販売されていたという。
」
 ホウレンソウ、カキナから規制値超える放射性物質 群馬
ホウレンソウ、カキナから規制値超える放射性物質 群馬「
2011.3.20 21:52
群馬県は20日、県内の一部のホウレンソウとカキナから、食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性物質が検出されたと発表した。大沢正明知事は同日、県内の農家や農業団体に出荷の自粛を要請した。大沢知事は同日夜の記者会見で「ただちに健康に影響を与えるものではない」として冷静な対応を求めた。
同県が実施したサンプル調査では、19日に伊勢崎市で採取されたホウレンソウから、規制値(1キロ当たり2千ベクレル)を超える2080~2630ベクレルのヨウ素を検出。また、高崎市で同日採取されたカキナからも、規制値(同500ベクレル)を超える555ベクレルのセシウムが検出された。
」
 風評被害タクシーや旅館にも?
風評被害タクシーや旅館にも?「
2011.3.20 21:19
福島県では風評被害が広がっており、乗車拒否や宿泊拒否も起きている。神奈川県在住の主婦(50)は「福島県に向かおうとしたら、タクシー会社2社に乗車を拒否された」という。
主婦は福島市にいる被災した両親を迎えに行こうと、栃木県内のタクシーに予約の電話を入れたが、電話した2社とも「放射性物質が危険だから行くなと上司に言われている」と断られたという。
乗車拒否したとされるタクシー会社は「19日にまで、50キロ圏内に向かうことを控えていたのは事実。会社で総合的に判断したもので、悪意や作為ではない」としている。
また、厚生労働省には避難している被災者から「福島県から来たというだけで宿泊を拒否された」などの匿名の苦情が2件あり、岩手県の旅館からも県を通じて「福島からの避難者を泊めても大丈夫か」などと相談があったという。
旅館業法では、宿泊者が伝染病にかかっているなど、正当な理由がなく宿泊拒否するのを禁止しており、厚生労働省は19日、福島県からの避難者が宿泊を拒否しないよう各都道府県などを通じ、宿泊施設を指導するよう通達を出した。
」