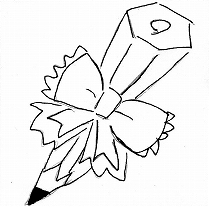本日は『文字・活字文化の日』であると同時に、「読書週間」の始まりの日でもあります。
読書週間とか、小学校ぶりに聞いたわ〜。
2005(平成17)年10月27日に文字・活字文化振興法の中で制定されました。
文章を読んだり書いたり、または出版する「文字・活字文化」の振興を図り、知的で心豊かな生活、活力ある社会を実現することを目指す法律です。
...あれ、物書きの私には意外と関わりある法律だったかも。
近年は電子機器の普及により、活字離れや出版不況が問題視されていますが、知識や知恵、健全な民主主義の発達にも欠かすことの出来ない文字や活字を正確に知ることを提唱しています。
ここでふと思ったのが、「活字離れとはいうけれど、決して文字離れじゃないんだな」ってことです。
じゃあ活字と文字の違いはなんでしょうか。
活字はもともと、活版印刷に使う凸型の字形という意味の言葉で、転じて書籍や新聞のような「印刷されたもの」も指します。
一方の文字は、言葉を表記するために用いられる記号のことです。
つまり、手書きだろうが印刷されてようがネット上のものだろうが、等しく「文字」です。
ですが手書き文字や電子機器に表示される文字は「活字」ではありません。
もっとも、活字は一文字ずつ彫られた木または金属のことをいい、活版印刷とは活字を組み合わせて作られた文章を紙に転写して印刷する方法です。
なのでデジタルデータをコピー機で印刷する現在の本の姿を見ると、厳密にいうと活字ではないのかもしれませんが。
私は試し読みぐらいなら電子でもいいんですけど、好きになったものは絶対紙で欲しいタイプなので、出版がなくなると普通に困る😞