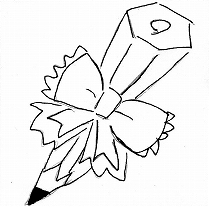今日は『いい風呂の日』です!
急に寒くなってきたので、お風呂が気持ちよくなってきましたよね〜。
「い(1)い(1)ふ(2)ろ(6)」の語呂合わせから、日本浴用剤工業会が制定しました。
「風呂」という言葉の語源は、諸説ありますが「室(むろ)」から派生したと言われています。
もともとは、蒸気を浴びて身体の汚れをふやかし、こすりだした後に湯で流す「蒸し風呂」が一般的でした。
この蒸気を逃がさないための狭い部屋を「室」と呼んでおり、ムロ=(蒸し風呂を指す)フロという音に変わったそうです。
ところが江戸時代に入って公衆浴場が登場し、湯に全身を浸す入浴スタイルが確立すると、徐々に蒸し風呂は姿を消していきました。
こうして、「風呂」という言葉は「湯船に全身浸かる入浴方法」を指す今の意味に変わっていきました。
「湯治」という日本語もあるように、世界でも有数の温泉大国である日本は、古くから天然の温泉を利用して病気やけがの治療を行なってきました。
同様の目的で薬用植物の利用が盛んに行われ、端午の節句の菖蒲湯や冬至の柚子湯などは慣習として残っています。
これが入浴剤の始まりだとされています。
現在のような入浴剤が初めて発売されたのは、1897(明治30)年の銭湯向けに販売されたくすり湯『浴用中将湯』だそうです。
入浴剤の基本的な効果は、そもそも入浴によって得られる温浴効果と清浄効果を促進することにあります。
参考HP:日本浴用剤工業会
入浴剤といえば、インテリアにもなるようなシャレオツなものを誕プレにもらったことがありました。
使いどころが分からなくてずっとインテリアにしてたんですけど、こないだ思い切って使ってみたら効果切れだったみたいで、思ったような泡風呂になってくれませんでした...。
まあ5年以上放置してたわけだし、そうなるかぁ(◞‸◟)トホホ