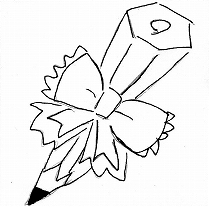本日は『絵本の日』です!
1986(昭和61)年11月30日に、「絵本論」(福音館書店)の初版が出版されたことにちなんで制定されました。
「絵本論」は、戦後初めて、日本の絵本に関する基本的な考え方を示し、その後の絵本の世界に大きな影響を与えた瀬田貞二氏の著作です。
瀬田貞二氏という方は、作家、評論家、翻訳家として有名な人で、なんとあの「ナルニア国物語」や「指輪物語」「三びきのやぎのがらがらどん」の翻訳をした人です。
マジで!?!? めっちゃすごいな!?!?
そういえば、タイトルや著者は結構記憶に残ったりしますけど(ナルニアはC.S.ルイス、指輪物語はトールキン)、翻訳者って気に留めたことなかったなあ...。
この「絵本論」の中で、瀬田貞二氏は
「子どもを静かなところにさそいこんで、ゆっくり深々と、楽しくおもしろく美しく、いくどでも聞きたくなるようなすばらしい語り手を、私たちは絵本とよびましょう。」 参照:Biblio
と述べて、絵本を定義しているそうです。
絵本と似たようなイメージで「童話」というものもありますが、絵本が絵を中心にして文章を補助の意味で使うのに対し、童話は文章を中心に挿絵を補助的に使うものとされています。
私はこれまで、童話と称して小説を書いてきました。
文章がメインなのでそれであっていたのかもしれませんが、今日この話を知って、
「在り方は絵本がいいな」
と感じました。
「絵本論」はとりあえず読むとして、どうすれば童話として絵本のあり方に近づけるか、チャレンジしてみたいと思います。
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
感想をいただけると、泣いて喜びます!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。