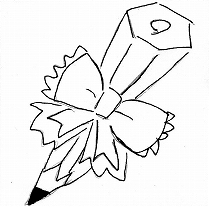なんと今日は、あの! 『ルーヴル美術館が開館した日』なんだそうです!
しかも1793(寛政5)年8月10日のことだそうで、思った以上に古くてびっくりです。
日本で一番古い公立美術館は1933年(昭和8年)開館の京都市京セラ美術館です。200年ぐらい後ですね。
ちなみに日本で一番古い博物館は、上野の東京国立博物館で1872(明治5)年開館です。こっちでも100年ぐらい差がありますね...。
「モナ・リザ」や「ミロのヴィーナス」など、知らぬ人はいないぐらいの超有名な作品を数多く所蔵しているルーヴル美術館は、元々12世紀にフィリップ2世によって城砦として建てられたものだったそうです。
その後16世紀にフランソワ1世によって宮殿に作り替えられ、ルイ14世がヴェルサイユ宮殿に移る1678年まで歴代君主の居城として利用されていました。
ちなみに居城がヴェルサイユ宮殿に移ったことで空いたルーヴル宮殿は、芸術作品の保管だったり芸術家たちのアトリエとして使われたりしていたそうです。
君主の好みはもちろん、流行の建築様式に合わせてどんどん増改築が行われ、ルネサンス様式やバロック様式が入り混じった美術館自体が芸術品としての価値を持っています。
そして1793年。フランス革命が起こり、貴族や教会の所蔵品が国有化され、それ以前からルーヴル宮殿内にコレクションとして保存されていたものも含めて、美術作品を展示するための一般に開かれた美術館として生まれ変わりました。
1980年には「ダヴィンチ・コード」にも登場したガラスのピラミッドを中庭に設置する大規模な改築を実施し、ルーヴル美術館は今の形になったそうです。
国境と時代を超えた所蔵品が38万点をこえるルーヴル美術館は、展示されているものだけでも全部じっくり見るのに1週間かかるとかいわれています。
イギリスの大英博物館も全体をサッと見て回るだけで5時間とか書いてある記事もありましたし、どーなってんのヨーロッパの美術館( ゚д゚)

※こちらのホームページで紹介されていた写真です。