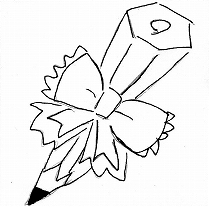本日8月16日は、月遅れ盆の送り火の日です。
お盆で我が家に帰ってきた人たちを再びあの世へ送り出すための送り火は、京都の五山送り火に代表されるように各地域でも大々的に焚かれます。
明治以前、日本では月の運行を基準として定めた太陰暦を使用しており、そのころのお盆は文月の満月の日だったそうです。
開国後、西洋にならって太陽の運行に従った太陽暦を採用し、お盆は新しい暦の上での7月15日にせよというお達しが政府から出たそうです。
東京近郊など一部の都市部ではそれにすぐに従いましたが、地方ではその通達が届かず、旧暦の日付のままお盆を続けていたと言います。
ところがカレンダーや新聞の日付と旧暦の日付のズレが次第に不便になり、旧暦のお盆の日付に近い8月15日を「月遅れ盆」と称して行うようになりました。
新盆だと7月15日を中心とした2、3日になりますが、月遅れのお盆だと8月の半ばで学校も大半が夏休みです。
帰省のタイミングともあいやすいので、8月の「お盆」の方が一般的なんじゃないかなあとは思います。
さて、京都の五山送り火は例年8月16日の20時に大文字に火が入れられ、妙法、船形、左大文字、鳥居形と次々に点火されます。
ところが今年2020年は、新型コロナウイルスの影響で3密回避が叫ばれている年です。
五山送り火を見るためにたっっっくさんの人が集まりますので、クラスター発生不可避です。
しかも集まるのは公園とか道路とかでも可能なので、施設のように「閉館します」というようなことができません。
そこで、まさに苦肉の策というしかありませんが、点火する火床の数を減らして規模を縮小するという方法がとられることになりました。
今日の夜は京都市内へ出かけても例年のように美しい大文字は見えないので、家でそっと手を合わせるようにしてください。
ちなみに、私は小さい頃はこの五山送り火を「大文字焼き」と呼んでいたのですが、送り火を担う誇り高い人々にそれを言うと修羅か羅刹か般若かというぐらい激怒するそうなので、間違えないようにしてください。
京都の送り火は「五山送り火」です!!!!