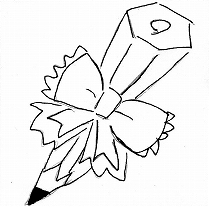本日は『ハイビジョンの日』です。
ハイビジョンの走査線の数が1,125本なことから、当時の郵政省(現・総務省)とNHKが1987(昭和62)年に制定しました。
ちなみに、ハイビジョンテレビの画面対比が9:16であることから、経済産業省は9月16日を「ハイビジョンの日」として定めています。
...せめてちょっと違う名前をつける優しさが欲しかったなぁ。
走査線とは、画面を構成する横線のことです。
従来のアナログ放送は走査線が525本でしたが、アナログハイビジョンは1125本で約2倍の解像度で美しい画面を見ることができるようになりました。
アナログハイビジョンの研究は東京オリンピックがあった1964年頃に始まりましたが、あまり普及しないまま2007年に終了してしまったそうです。
さて、機械オンチの私にはさっぱり意味不明なのですが。
そもそもハイビジョンテレビとは、日本のNHK放送技術研究所が開発したMUSE方式のアナログ高精細度テレビの名称でした。
なので、デジタルハイビジョンテレビを含む現行の高精細度テレビは「HDTV(High Definition Televisionの略)」と呼ぶのが正しいそうですが、ご存知の通り全部ひっくるめてハイビジョンと呼ぶのが習慣づいています。
ハイビジョンテレビの原理を簡単にいうとこんな感じらしいです(参照はこちら)↓
①放送する動画を、1秒につき60枚の静止画に分ける。
②その静止画をそれぞれ1080本の線に分ける(この線が走査線)。
③この走査線を1920個の画素(ピクセル)に分割し、1個ずつ0と1の電気信号に変換して電波として放送する。
④ハイビジョンテレビは放送を受信すると、信号に従って順番に走査線を重ねて画像を再現する。
再現された画像が目にも止まらぬ速さで流れていくので、結果人間の目には高精細でなめらかな動画に映るというわけだそうです。
ちなみにハイビジョンテレビの走査線は1125本ですが、映像表示のための走査線は1080本で、残りは同期信号や字幕などに使われているらしいです。
結局、分かったような分からんような????