いままでここのブログでは、三面記事が読めない受験生に社説を読ませて訳させるような受験英語のあり方について批判を重ねてきました。ただけっして翻訳という行為を否定するわけではなく、めちゃくちゃな順序の英語教育を否定するだけの話です。
受験参考書の中には、伊藤和夫著「英文解釈教室」のような、翻訳家から高く評価させるような本もあります。しかし子ども向けペーパーバックを読めない受験生が難解な英文の翻訳技術を学んでも英語ができるようになるわけはありません。
とはいえ、昨日本屋をぶらついていて思わず買ってしまった「伊藤和夫の英語学習法」(駿台文庫)という本の中に以下のような一節がありました。
(引用開始)
僕がいつも言うだろう。授業が効果をあげるのは、その内容が10だとして、そのうち5つはすでに十分知っていることであり、3つは言われれば思い出すことであって、全く知らないことは2つぐらいの場合なんだって。「読む」という作業もそれと同じで、5つは知っていること、3つはだいたい分かっていること、2つが全く知らないことぐらいの文章が読んで分かる文章なんだ。極端な言い方をすれば、読む前に「分かって」いるから、読んで分かる、「読めて」いるから読めるんだよ。ところが、君たちの知識や教養をみくびるわけではないけれども、今の試験問題の大部分は、日本語で書いてあっても、そう簡単に君たちに分かる文章ではないはずなんだ。その意味で、読む前に「分かって」いない文章を「ななめ読み」したり、「飛ばし読み」したところで、結局は妄想と誤解しか生まれてこないのさ。
(引用終了)
「今の試験問題の大部分は、日本語で書いてあっても、そう簡単に君たちに分かる文章ではないはずなんだ」という指摘が「受験英語の神様」と呼ばれるような英語講師からなされていたことは注目に値すべきことです。97年に他界した伊藤和夫氏の95年の著作ですので晩年の、しかも病床で構想された本です。だから思いのたけを歯に衣着せることなく書いたのかもしれません。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の伊藤和夫語録には
「英文を左から右へ、上から下へ、一度目を走らせるだけで、全てが終わっている」
「いいかい。訳せたから読めたんじゃない。読めてるから、必要な場合には訳せるんだ」
「一文一文の正確な理解をおろそかにしたままで、キーセンテンスだのパラグラフリーディングだのと言ったところで、砂上の楼閣に等しい」
といったものが掲載されています。いずれも英語学習者にとって普遍的妥当性のある指摘だと思います。ただこういった英語学習はレベル相応の教材を使って初めてできることです。
難解な英文を読んで合格答案を作成する方法を教えることに関して伊藤和夫氏が達人であったのは衆目の一致するところでしょう。ただもう少し受験英語の本格的批判をやってほしかったと思わずにはいられません。「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文」を減点されないように和訳して合格点をとる技術よりも、「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文」は大学入試あたりで使うべきではないという見識の方がはるかに世の役に立つと思います。外国語はそう簡単に身につくものではありません。中学高校の六年間普通に英語を学んでネイティブの子ども向け読み物をすらすら読めるようになれば、それは十分満足すべき成果です。
(引用開始)「伊藤和夫の英語学習法」より
君たちの憧れのまとである東大生ですら、その東大の教官からは、定員増の結果下位3分の1は「講義についていくのが大変だ」とか、「中学生レベルの英語さえまともに読めない」とかいう評価しか受けていない(産経新聞社会部編:「大学を問う」新潮社p46)ことも知っていていいんじゃないか。
(引用終了)
こと英語に関して、こういった状況の元凶は、アカデミックな入試問題に固執するバカデミックな大学教官にあるといって過言ではありません。
念のために書いておきますと、「日本語で書いてあれば簡単にわかるような英文(おおむねTIMEFORKIDSレベル)」を高い精度で読めるレベルに達した受験生ならば、「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文(おおむねTIME,NEWSWEEKの論説記事レベル)」が出題される大学入試で合格点をとるのは難しくありません。ライバルの多くは「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文」にばかり取り組んできた結果、「日本語で書いてあれば簡単にわかるような英文」すら満足に読めないレベルなのです。一定期間過去問に取り組んで入試慣れすれば負けるわけがありません。
受験参考書の中には、伊藤和夫著「英文解釈教室」のような、翻訳家から高く評価させるような本もあります。しかし子ども向けペーパーバックを読めない受験生が難解な英文の翻訳技術を学んでも英語ができるようになるわけはありません。
とはいえ、昨日本屋をぶらついていて思わず買ってしまった「伊藤和夫の英語学習法」(駿台文庫)という本の中に以下のような一節がありました。
(引用開始)
僕がいつも言うだろう。授業が効果をあげるのは、その内容が10だとして、そのうち5つはすでに十分知っていることであり、3つは言われれば思い出すことであって、全く知らないことは2つぐらいの場合なんだって。「読む」という作業もそれと同じで、5つは知っていること、3つはだいたい分かっていること、2つが全く知らないことぐらいの文章が読んで分かる文章なんだ。極端な言い方をすれば、読む前に「分かって」いるから、読んで分かる、「読めて」いるから読めるんだよ。ところが、君たちの知識や教養をみくびるわけではないけれども、今の試験問題の大部分は、日本語で書いてあっても、そう簡単に君たちに分かる文章ではないはずなんだ。その意味で、読む前に「分かって」いない文章を「ななめ読み」したり、「飛ばし読み」したところで、結局は妄想と誤解しか生まれてこないのさ。
(引用終了)
「今の試験問題の大部分は、日本語で書いてあっても、そう簡単に君たちに分かる文章ではないはずなんだ」という指摘が「受験英語の神様」と呼ばれるような英語講師からなされていたことは注目に値すべきことです。97年に他界した伊藤和夫氏の95年の著作ですので晩年の、しかも病床で構想された本です。だから思いのたけを歯に衣着せることなく書いたのかもしれません。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の伊藤和夫語録には
「英文を左から右へ、上から下へ、一度目を走らせるだけで、全てが終わっている」
「いいかい。訳せたから読めたんじゃない。読めてるから、必要な場合には訳せるんだ」
「一文一文の正確な理解をおろそかにしたままで、キーセンテンスだのパラグラフリーディングだのと言ったところで、砂上の楼閣に等しい」
といったものが掲載されています。いずれも英語学習者にとって普遍的妥当性のある指摘だと思います。ただこういった英語学習はレベル相応の教材を使って初めてできることです。
難解な英文を読んで合格答案を作成する方法を教えることに関して伊藤和夫氏が達人であったのは衆目の一致するところでしょう。ただもう少し受験英語の本格的批判をやってほしかったと思わずにはいられません。「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文」を減点されないように和訳して合格点をとる技術よりも、「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文」は大学入試あたりで使うべきではないという見識の方がはるかに世の役に立つと思います。外国語はそう簡単に身につくものではありません。中学高校の六年間普通に英語を学んでネイティブの子ども向け読み物をすらすら読めるようになれば、それは十分満足すべき成果です。
(引用開始)「伊藤和夫の英語学習法」より
君たちの憧れのまとである東大生ですら、その東大の教官からは、定員増の結果下位3分の1は「講義についていくのが大変だ」とか、「中学生レベルの英語さえまともに読めない」とかいう評価しか受けていない(産経新聞社会部編:「大学を問う」新潮社p46)ことも知っていていいんじゃないか。
(引用終了)
こと英語に関して、こういった状況の元凶は、アカデミックな入試問題に固執するバカデミックな大学教官にあるといって過言ではありません。
念のために書いておきますと、「日本語で書いてあれば簡単にわかるような英文(おおむねTIMEFORKIDSレベル)」を高い精度で読めるレベルに達した受験生ならば、「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文(おおむねTIME,NEWSWEEKの論説記事レベル)」が出題される大学入試で合格点をとるのは難しくありません。ライバルの多くは「日本語で書いてあってもそう簡単にわからないような英文」にばかり取り組んできた結果、「日本語で書いてあれば簡単にわかるような英文」すら満足に読めないレベルなのです。一定期間過去問に取り組んで入試慣れすれば負けるわけがありません。











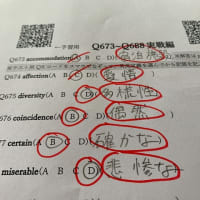


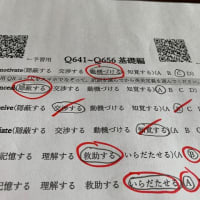

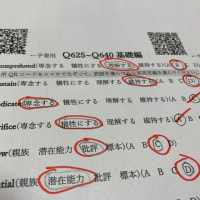





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます