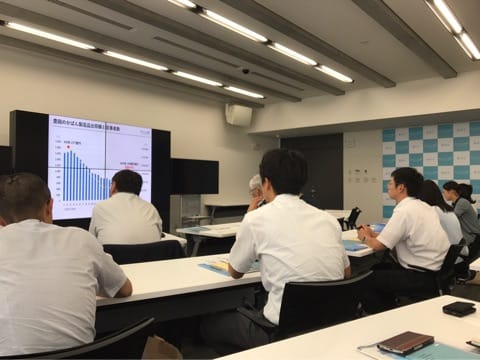江戸時代の寺子屋の様子を描いた絵を見ると、子供たちが思い思い自由気ままに手習いをしているように見えます。
しかし、この自主的な勉強スタイルで、当時の日本は世界最高の識字率を達成していました。(江戸時代の日本の識字率70~80%、同時代のヨーロッパ先進国の識字率20~30%)
この教育の普及度が、明治期に日本が短期間の近代化を成功させる要因となりました。
これからの日本に求められるのは、この必要以上に強制のない自主的な教育を新たに復活させることです。
そして、その教育を、現代のインターネット技術を利用して、親子、友達、先生との人間的な触れ合いの中で行っていくことです。
そのことによって、すべての子に十分な基礎学力をつけるとともに、その子の関心に応じた高度な学習を行う場を作ることができるのです。
小、中学生の学力トップの福井。
私たちは現代に合わせた寺子屋を目指します。
その名も「寺子屋」プロジェクトを立ち上げました。