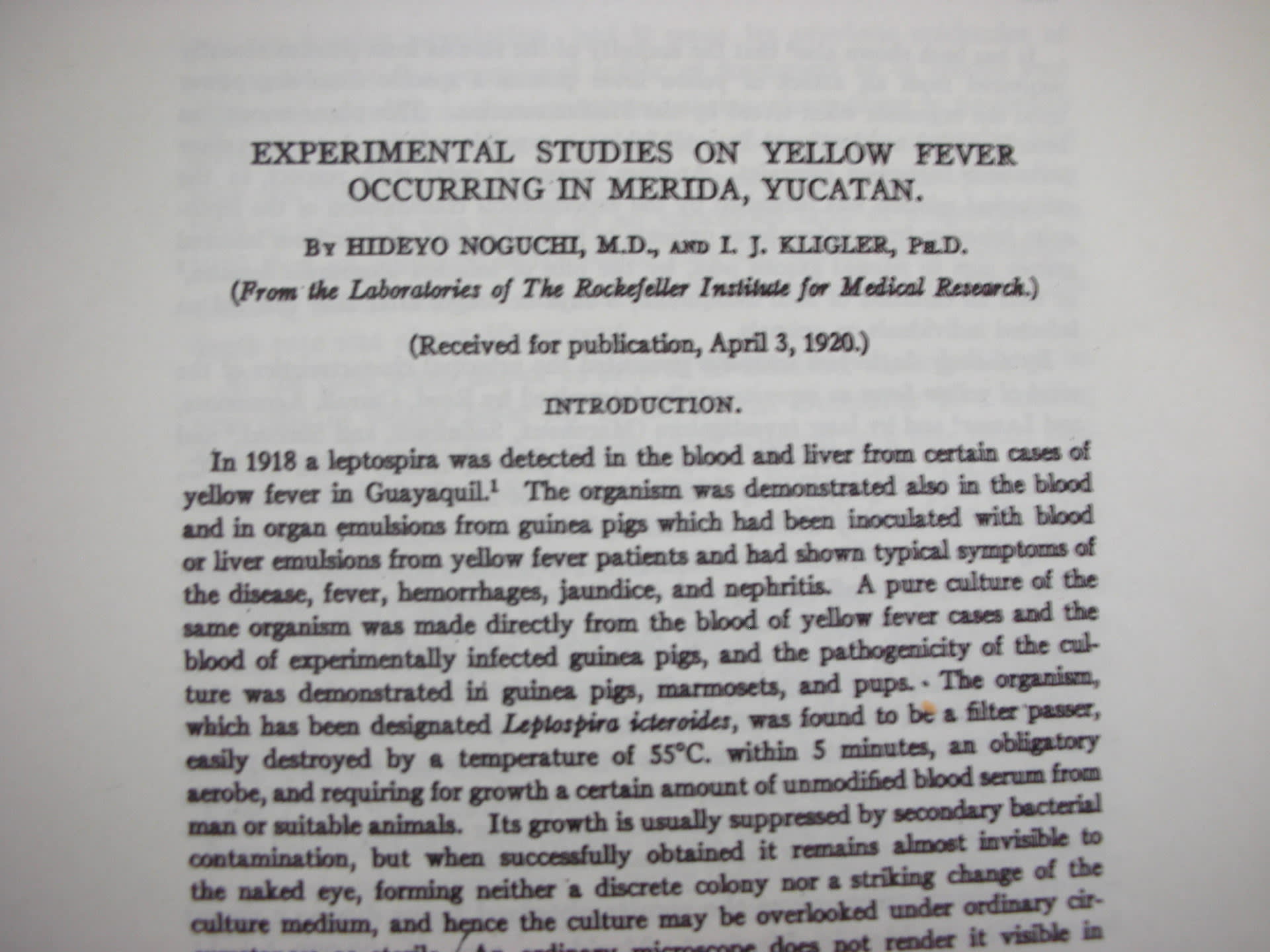野口はメキシコから帰ってまもなく今度はペルーに出張する。
既にクリグラーがペルーに入り研究を開始していたが、当地の実験室はひどく、町には水がなく電気も使える状態ではなかった。研究に使うモルモットも原因不明の疾病で死亡してしまった。また衛生状態も悪く、黄熱病と共に腺ペストの流行も起きていた。そして実験ははことごとく失敗に終わっていた。
この窮地を救うため、上司のフレクスナーは1920年4月に野口をペルーに派遣した。
その際の研究結果を論文「ペルー北部における黄熱病の実験的研究(1920年8月7日受付)」として、前報と同様にクリグラーとの共著で発表した。
 論文の要旨
論文の要旨
1920年に発生した黄熱病の流行の14症例(Paytaで3月、4月の9症例とMorroponとPiuraで4月、5月の5症例)をペルーの北部で研究した。
研究の方法は以前に行ったものと同様であるが、研究設備は非常に貧弱だったので相当の変更が必要であった。Paytaにおける仕事は電灯がなく、水と動物のエサが不足し、接種用のモルモットの不具合、古い培地中の変化など不利な条件であったが、このような不利な条件下で得られた結果は決して否定的ではなかった。
血液の直接接種又は培養物での両方で動物に典型的な感染を起こした例はなかった。それでも各シリーズのあるモルモットは一時的に発熱又は温和なレプトスピラ感染を示す肺の明確な出血傷害を示した。暗視野顕微鏡が使えなかったので患者の血液中又は培養液中の
Leptospira icteroidesの直接探索は行わなかった。次にPiura研究設備は大いに改善された。暗視野顕微鏡の使用はバッテリーの方法で可能になった。若い健康なモルモットはニューヨークから受取った。そして新鮮なウサギ血清はPiuraで得た。Morroponでの黄熱病5症例の培養は11、12と13日後に調べた。3症例から生きたレプトスピラが見つかった。これら5症例の培養液のモルモット接種によって、暗視野顕微鏡でレプトスピラが見つかる、見つからないにかかわらず、典型的な
L.icteroides感染が5症例のうち4症例で見られた。こうして1症例のみが暗視野顕微鏡下でレプトスピラが見つからず、動物接種が陰性であった。
感染モルモットの血液中又は臓器エマルジョン中にレプトスピラが見つかり、そして各株の他のモルモットへの更なる転移が得られた。そして純培養が得られた。
研究中に実際的な重要なポイントが明らかになった。一つは培地には新鮮なウサギ血清を使用することが重要であること。古いウサギ血清は、それのみ又は寒天と一緒であっても熱帯気候では数ヶ月で
L.icteroidesの発育に不十分になる。
二番目のポイントは
L.icteroidesで感染させるモルモットの感受性の違いである。Morropon培養材料で動物接種陽性の4シリーズのうち二つにおいて与えられた材料を接種されたモルモットの半分だけが典型的な症状を呈した。他の半分は肺に少数の出血斑、又は全く感染しないことで示されるように一時的な温和な感染であった。
これらの事実からPayta材料を接種されたあるモルモットに見られた肺の傷害と発熱は温和なレプトスピラ感染のためと考えられる。
比較実験で、Paytaで得られた土着のモルモットはニューヨークから最近送られたものよりレプトスピラ感染により抵抗性であることが分かった。事実、Morropon流行から得られた
L.icteroidesの有毒株を接種された時でさえ、前者の少数しか典型的な感染で死亡しなかった。
最終的に、ペルーにおいて研究された黄熱病の14症例で典型的なレプトスピラ感染と同時に実験的感染モルモットにその微生物が見つかったのは4症例であった。温和なレプトスピラ感染を示した例の大多数は致死的ではなかった。数症例のみが全くの陰性結果であった。
黄熱病のMorropon症例から分離されたレプトスピラは形態的及び培養的に
L.icteroidesのグアヤキルとメリダ株と同一であった。そして免疫試験によりグアヤキルの菌と区別できないことも示された。(以上)
当時のペルーでは衛生状態が悪く腺ペストが流行していた。腺ペストの感染源はネズミである。当時の衛生状態から多くのネズミが走り回っていたことは容易に想像される。ということは、ワイル病も多数発生していたに違いない。従って野口にとって好都合な黄熱病患者(実はワイル病患者)はいくらでも存在していたであろう。
今回は免疫血清を用いた免疫学的試験を二つの方法で実施している。一つはPfeiffer反応で、もう一つは免疫血清にレプトスピラを加えて18時間放置して暗視野顕微鏡観察する方法である。用いた血清はグアヤキル株で作製した抗icteroides血清とアメリカ株で作製した抗icterohaemorrhagiae血清である。ペルーで分離したレプトスピラの2株は両方の試験法で、前者に陽性、後者では陰性との成績を発表している。この成績は現在でも非常に考えにくいものである。この成績が正しいとするならば、抗icterohaemorrhagiae血清の力価が抗icteroides血清のそれに比べて非常に低かったことを意味する。この実験では両血清の力価を揃えないで行っているので、このような結果になったことも考えられる。当時抗体の力価という概念はなかったのだろうか。