12月10日に飯田市の山間部、南信濃の遠山霜月祭りに行ってきました。地元の人たちによって、500年以上受け継がれ、続けられているお祭りです。お祭りは9日の午後からはじめられ、終わったのは10日の朝5時頃でした。寒さと暗闇と静寂の中で、延々と行われる「神事」です。教育基本法の問題などで、報告が少し遅くなってしまいました。
 霜月祭りの特徴「かまど」
霜月祭りの特徴「かまど」
他の写真をたくさん、下記のブログページに掲載しました。
http://www.jocoso.jp/hidepeace
日本の「地方」では、まだ旧暦が生き生きと残っています。旧暦では12月はまだ霜月、つまり11月なのです。10月といえば神無月。この月には日本中の神様が出雲大社に集まって会議をされる。したがって出雲以外は神のいない神無月です。
その神様たちに霜月には遠山に来てもらおうというのが、このお祭りの趣旨。日本のチベットといわれ急斜面に家と畑が点在する上村をはじめ、谷間(たにあい)のわずかな空間に寄り添うようにして生きてきた人々にとって、日本中の神々が来てくれることへの期待は、そのまま翌年への希望となっているのです。
日本の中心(京都や東京)から遠く離れ、豊かな実りがあるわけでもなく、古書には「獣と魑魅魍魎の地」と書かれているような土地で生きていく人々にとって、神々に寄り添うことは、本当にそれなくして生きてはいけない心の支えだったのだろうと思います。その状況は、21世紀のいまも実はそう変わっていないのかもしれません。
人々は1年をこの祭りのために生きて、あらゆるエネルギーをこの祭りで炸裂させるのかもしれません。
12月に入ってから遠山の10ほどの地区で順々に行われます。私が行ったのは木沢地区の正八幡神社での霜月祭りです。飯田での自然エネルギーと省エネルギーの市民事業に出資していただいた出資者の皆さんのツアーとして企画し、私も付き添いとして参加したわけです。
祭りのうたい文句は「さむい、ねむい、けむい」。12月の飯田の山中ですから極寒です。氷点下を覚悟しましたが、地球温暖化のせいか意外と暖かでした。4℃くらいはあったでしょう。夜通し、朝までの祭りですから、まともに付き合っては眠れません。地元の人たちは延々と12時間以上、神事を続けるのですが、私たちは適当なところで仮眠場所で眠るよう指示されます。そのまま朝まで眠って、お祭りを見られなくなる人、酒宴の席に行って酔いつぶれてしまう人・・これも祭りの一環かも知れません。
この祭りの特徴は「かまど」です。小さな祠の中にかまどをつくり、そこに薪をくべてお湯を大量に沸かすのです。その湯気が立ち上り、日本中の神々はこの湯気の中に現れるとされます。そして神々の一人ひとりに「今日の良き日、遠山八社の神が、全国の神々をお湯の上に呼び、神楽や舞を見せるので、春まく種もみのり豊かに、商売繁盛するようにこの里をお守りください」と奏上します。神の一人について、それぞれ東西南北で結界を切りつつこれをやりますので、延々と時間がかかるのです。
人が100人入ると満杯になるような祠の中で、もうもうと「かまど」の火が熾(おこ)されますので、湯気だけではなく、煙、すすも猛烈です。さらに、湯木(ゆぼく)で熱湯をかき混ぜ、飛び散らせたりするので、「さむい、ねむい、けむい」の次に「あつい」もあります。このお湯にかかると無病息災、長生きをするのだそうで、私は3度くらいかかりましたので、そうとう寿命が延びたかもしれません。
クライマックスとされるのは、地元の神々が、日本中の神々のお迎えの大役を終え、喜び踊るところ。ここまでは神様をお迎えする「同じ行為」の繰り返しだったものが、にぎやかにお面をかぶって地元の神様たちが登場します。天狗もいれば狐もいる。500年前に遠山地区を領地としていた源氏の関係者、北条政子や源のなんたら・・というのもあります。子供を抱いた女の人や、観客をたたいてまわるおばあさんもいます。権力者から庶民まで、みんな神様ということでしょうか。
中には、日本中の神様と一緒に遠山に来て、居心地が良いので帰るのを忘れてしまった悪霊や魑魅魍魎を代表するものもいるようです。この役には若者が振り当てられ、小さな祠の中をところせましと飛び回ります。エネルギーの爆発です。それまでの静から動へ。飛び回る若者は、このときばかりは観客の中の「好きな女性」に抱きつくことも許される・・ような世界があります。
やがてみんなに取り押さえられ、面をはがされて「ただの人」に戻されます。そこで悪霊が去り、遠山の地にいくつことを防いだのです。ちなみに神事に参加するのはすべて男性です。女性の役も面をかぶった男性が行っています。祭りでは女性のエネルギーの爆発は、じっと抑えられているのかもしれませんが、見に来ている人にはとても女性が多かったように思います。
祭りの最後は「大天白」という神様の舞で締めるのですが、この神様はかつてこの地をおさめていた遠山氏(殿様)であるとも言われています。遠山氏の時代がとても豊かで安定していて、後の権力者にこの地を追われた殿様を住民はひそかに慕い続けていて、それを祭りの中で表現していたのだとも言われます。であれば、抵抗の精神が奥底にある祭りとも言えます。
この祭りをベースで支え、人々を神々の世界に引き込むのは、延々と同じリズム(なんパターンかある)を打ち続ける太鼓と笛であると思います。ベテランのおじいさんもいれば、おじさんに若者に、まだ小学生というような子供がやっていたりします。世代がつながっているのです。12時間以上もの時間の中で、延々と参加し、きたえられていると、それが身体に染み付いていくのかもしれません。祭りを中心とした地域共同体が、ここには残っているのです。
このお祭りは文化庁の調査で、50年前に記録されたときと、今でもまったく変わっていないと確認されたそうです。人々の伝統文化への強い思いもありますが、それだけ社会と隔絶された地域であったということでもあるかもしれません。
「格差社会」という壁をとりのぞきながら、この悠久の文化がずっと続いていくことを、どのように実現したらよいのか・・難しい課題だなあと感じました。











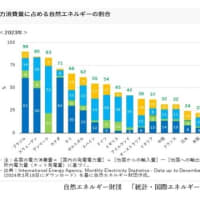


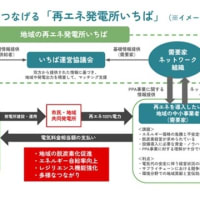






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます