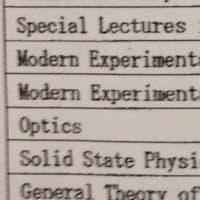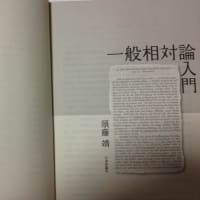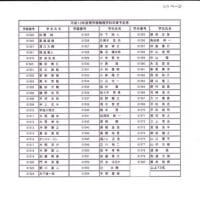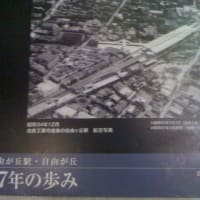1.脳をエミュレートするコンピュータのようなものができないと解明できたといえないとする立場。
2.人間の脳外科医や神経外科医そして、脳科学者が理解共有システムで、共通に納得するよりよいモデルができたときに解明できたとする立場。
の二つに分かれるだろう。
後者の場合は、脳内の化学反応とエネルギー情報伝達システムの解明さえできればよく、これを他の物質でコピーし人工物として作る必要は無いと考える。
私はこれで十分だと思うが、前者の立場は、工学的に重要であるかもしれないし、逆に、この立場でエミュレートできる物質モデルが完成し、後者の立場の成果の重要な手がかりになることも忘れてはならないと思う。
たとえば、最近議論している”同様に確からしい”ことの理解を、脳の物質モデルとしての「エミュレータ」がどうやって実現するのだろうか?対称性の高いものが美しいと感じたりするのはその次に待つ課題。そして、その前に解決すべき課題は、もっとシンプルであるはず。つまり、
1と2は2の方が大きいとはどういうことか?「エミュレータ」が脳のように、自分自身でルールを発生する必要がある。今のコンピュータには、人間が考えた算術アルゴリズムを実現するアーキテクチャーがあらかじめ作られているのである。
数字の観念が欠損しているため、数字を色などに置き換えて、どうにか買い物をしている素晴らしい人間がいることをご存知でしょうか?彼の脳には、算術アルゴリズムが無いか、使いにくい状態にある。しかし、同じ脳が別の機能でそれを補って、現実社会の生活上の価値のある仕事が達成できる(クオリティーは低下するといわざるを得ないかもしれないが:そもそも、早くお勘定を済ませるようになったのは、文化的な発展のプロセスが関連するので、そこでクオリティーがどうとかいう一般化は問題だろう。もしかしたら、一般の人よりも、ある意味クオリティーの高い脳かもしれないのだ)。彼の脳は、算術演算が苦手かもしれないが、無い、0:ゼロである、ということは価値として理解している。
「エミュレータ」にとって、ゼロとは何だろう?数の大小とは何だろう?
まずはこの課題をクリアしなくては次に進めなくないだろうか?
もう既に、解決されているのかどうか、ご存知の方は教えていただければ幸いです!
サラリーマンCMOS回路設計エンジニアの妄想でした。
2.人間の脳外科医や神経外科医そして、脳科学者が理解共有システムで、共通に納得するよりよいモデルができたときに解明できたとする立場。
の二つに分かれるだろう。
後者の場合は、脳内の化学反応とエネルギー情報伝達システムの解明さえできればよく、これを他の物質でコピーし人工物として作る必要は無いと考える。
私はこれで十分だと思うが、前者の立場は、工学的に重要であるかもしれないし、逆に、この立場でエミュレートできる物質モデルが完成し、後者の立場の成果の重要な手がかりになることも忘れてはならないと思う。
たとえば、最近議論している”同様に確からしい”ことの理解を、脳の物質モデルとしての「エミュレータ」がどうやって実現するのだろうか?対称性の高いものが美しいと感じたりするのはその次に待つ課題。そして、その前に解決すべき課題は、もっとシンプルであるはず。つまり、
1と2は2の方が大きいとはどういうことか?「エミュレータ」が脳のように、自分自身でルールを発生する必要がある。今のコンピュータには、人間が考えた算術アルゴリズムを実現するアーキテクチャーがあらかじめ作られているのである。
数字の観念が欠損しているため、数字を色などに置き換えて、どうにか買い物をしている素晴らしい人間がいることをご存知でしょうか?彼の脳には、算術アルゴリズムが無いか、使いにくい状態にある。しかし、同じ脳が別の機能でそれを補って、現実社会の生活上の価値のある仕事が達成できる(クオリティーは低下するといわざるを得ないかもしれないが:そもそも、早くお勘定を済ませるようになったのは、文化的な発展のプロセスが関連するので、そこでクオリティーがどうとかいう一般化は問題だろう。もしかしたら、一般の人よりも、ある意味クオリティーの高い脳かもしれないのだ)。彼の脳は、算術演算が苦手かもしれないが、無い、0:ゼロである、ということは価値として理解している。
「エミュレータ」にとって、ゼロとは何だろう?数の大小とは何だろう?
まずはこの課題をクリアしなくては次に進めなくないだろうか?
もう既に、解決されているのかどうか、ご存知の方は教えていただければ幸いです!
サラリーマンCMOS回路設計エンジニアの妄想でした。