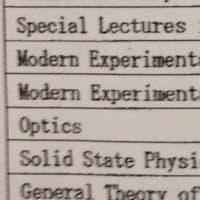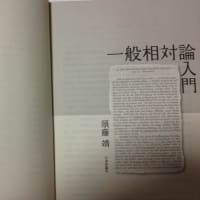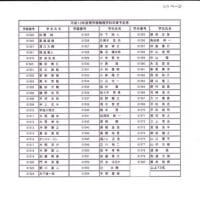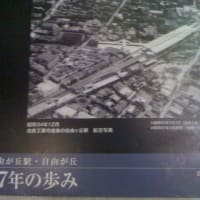(ただ単に、昨年度の数学が簡単すぎて(おじさんでも、時間内で90点取れた。今回のプレの約4倍楽です。)
、合格最低点が75%くらいだったから、
今年はやや難になるだろうと想定しただけかもしれないけど・・・
それにしても、今回のプレは良く作られています!感心。。。)
もちろん、難問は一部だけなので、
既に優秀な仕上がりレベルの高い受験生は、80点~90点は楽勝でした。
但し、それはおじさんのように、ノーベル賞でも夢見る少年少女でないと無理。
普通の受験生は、コケルようになっていると思います。
というわけで、まず、数学の反省と、
それを活かす戦略をひとまとめで書きます。
そこの慶大理工受験生!、素直に良く聞けよ!
年末の試験は、本番ではない、だからそこで、こけておいて良かったのだよ!
上手く行った人で、知っているタイプの問題だったら、
逆に、自分自身の弱点がチェックできなかったわけで、損なんです(要注意)。
ホント!
----------------------------
2010年度
第2回 慶大入試プレ 反省会
----------------------------
【数学】(私は、受験生ではないので、問題を一通り見もせず、
全部解くつもりで後ろから解いていって、こけまくったわけですが。。。当然でしょうね。)
A1.
となりに、A2の確率があり、しかも、漸化式が要りそうな、
完答がしんどそうな問題。そして、計算をする便利なスペースが全くない。
私などからすると、サービスの悪い、不親切な出題方法。。。
「解けるもんなら解いてみろ」「ほれ、ミスしろ」 と、言わんばかりの
と、言わんばかりの
問題文の羅列だ。
実は、上手く計算しなくちゃならないのは、(3)くらい。
受験生は、まず、全問をスキャンして作戦を立てる必要があるという
そういうタイプのものです。
この出題方法と、問題用紙。。。
A3はガウスの記号をつかった難問。
(2)だけは、書き出せば、途中が消えるので、ただ単に計算はできましたね。
しかし、他は一貫した方針でアプローチしないとできない。
A4は、この手の出題を、練習してないと、
このシチュエーションで、眠い朝一には、思いっきりしんどい。。。。
すっかり目が冴えた、夕方に、コーヒー飲みながらなら、
楽しんで、工夫して、解けそう。。。そういう代物だ。
(1)をうっかり、私のように、微分したあと、二倍角公式とかで、
楽できないかと計算に走った諸君!!
『甘~~っい!!』
二倍角の公式は、極限や積分では使えるのだが、三角関数の構造を上手く使った問題には、
逆に命取りだ。。。。図形問題でも、ヘタに楽しようとすると、遠回りになる。
機械的にやりすごしたい理系受験生の鬼門である。
一階微分したら、あとは、和積の公式が、見えないといけない。
(わたしはおじさんだから、見えなくていいのだ!)
(2)は、x・x'だけ計算し、きれいにしようとあがいた君!!
それでは、おじさんとおなじだよ!!
何のために、この(2)があるのか?!
こうセットにすると、驚くほどうまく厄介なのが消えてしまうからだ。
B1は割と安易な出題である。それに計算用紙が次のページにある。
さて、これは、A3をとりあえずすてて、
A4に集中した受験生の有利さがみえみえだ。
そして、A1で計算ミスした受験生は、英語と理科で80%を切ると、
奇跡でも起きないと合格できない。
(おじさんには奇跡がおこるだろうが・・・君には無理だ!)
ところが、A1には、計算スペースがない。
実はおじさん、p.6 と、p.7の白紙を、使っていない・・・・
今回が本番ならおそらく、この2ページを駆使した受験生が、合格しただろう。
(おじさんは、そもそも、受験しないのであるから、どうでもいいのだが)
そこで、提案!!!
まず、A1で、計算スペースをケチるな!
見開きになる計算用紙を用意可能ならば、
今回のp.6 と、p.7の白紙を、用意するのだ。
まず、初めにやる作業は、計算用紙の準備割り当てだ。
まちがっても(おじさんのように)問題文のすきまでチョコッと
計算してしまってはならない。。。。自滅である。
狭い所に、わざわざ、計算しにくい問題になっている。
だって、短い問題文で、簡単だったら、
慶応受験生に出題する意味がない・・・・
そして、p.6 と、p.7の白紙は取り出し横に置いてあるだろう。
つづいて、A2.
ページをめくるとp.12と、p.7が白紙だ。
取り出したA2.をここで解くのだ!!!
残念ながら、これをしなかった受験生は、
最後まで正解する、スペースがなく、
精神的に抑圧されて、やる気が無くなり、エフィカシー(苫米地先生の言葉から)が
自分で急低下。。。自滅するのだ。
自分で、エフィカシーを上げやすいように、工夫する
戦略と度胸!
そしたら、B1をp10,11で解く。
受験生は、往々にして、t^2-1で平気で割った式を書いてしまうだろう。
(おじさんは、いいのだ。あえて、気を抜いてそうなっている。
無意識に受験生の為にコケたのだ。)
論述なら配慮する習慣がややあったとしても、
この迫りくる提出期限のなかで、
しかも、欲をそそる(へ)と(ホ)を埋めるだけ。。。
余計、いい加減に当てはめたくなるところだ。。。
その欲求のままに書くと、合格が限りなく遠のくわけだ。
精神的に怠けず、しっかりと、
論述答案作成するのと同じように、
白紙計算スペースにストーリーを展開する必要があります。
その中で、必要な部分を吟味して、空欄に入れよう!!
(おじさんは、物理で暗算しすぎて、運動エネルギーを読み忘れ、
速度をかいてしまったりしている。
t=0がx=Lだったのも、すっかり慌てて忘れている。
欲求のままに。。。
『どっか~ん 』
』
これらミスがなければ、80点は堅いのにだ。この意味がわかるか!
おじさんが、バカなのだ。。。。
 )
)
そして、
A4.
工夫をする誘導のココロを察して、
裏の、p8,p.5を使ってしっかり、綺麗に計算する。
さて、
もう一度このように、全部解いてみよう!!
間違えなくなるまで、繰り返せ!!!
修行だと思え!!!
そうすると、合格が近づいていく。
A3は部分点狙いでよい。
解答解説を理解して、今度から使えるようにしよう!!
さて、理科に入ろう。
【物理】
1.わかってしまえば簡単な問題である。
ただ問題設定が単純なのだからと焦るといけない。
一応誘導になっていて親切。Fの符号を間違えるのは、
問題文の言うことをよく聞かず、自分で勝手に答えを急ぐからだ!
(おじさんは、めんどうなので、急いで、こけた)
ちょうど、タイミングがx=0でぶつかることがイメージできたら、
瞬殺のはず。
(眠いおじさんでなかったら、楽勝)
2.これも、簡単。
ローレンツ力をしっかり勉強していたら、x-y平面
y-z平面での運動を写像することは容易。
ちょうどV=0になるところの計算を
等加速度直線運動の方程式がすぐに見えれば、問題ない。
できない人は、最近の問題経験が足りない。
イメージと方程式を一致させる練習問題を
力学から選んで復習しよう。すぐに!
(おじさんは、別にいいです。。。)
3.
(オ)で、状態方程式が使えたら、なんのことはない。
(おじさんは、眠くて忘れた)
以降、物理的考察をするには、
P-Vグラフで考えることをした経験があるかどうかにかかっている。
これは、センスを養うのに良い。
良く復習されたい。
(おじさんも、復習するしかないな)
昔のおじさんなら、90点は堅いだろうか?
【化学】
基本ばかり、いきものばかり・・・
って、化学だけどねえ。
数学、物理に比べると、手抜きな出題で、
得意な人に差が付かず、良くないね。これは。
しっかり計算、練習していると、
できるでしょう。
全部できるようにしてください。
つまづいた問題は、類題を復習、繰り返し、鍛えよう!!
受験生として鍛えていたら、おじさんでも、90点とれそうだ。。。
、合格最低点が75%くらいだったから、
今年はやや難になるだろうと想定しただけかもしれないけど・・・
それにしても、今回のプレは良く作られています!感心。。。)
もちろん、難問は一部だけなので、
既に優秀な仕上がりレベルの高い受験生は、80点~90点は楽勝でした。
但し、それはおじさんのように、ノーベル賞でも夢見る少年少女でないと無理。
普通の受験生は、コケルようになっていると思います。
というわけで、まず、数学の反省と、
それを活かす戦略をひとまとめで書きます。
そこの慶大理工受験生!、素直に良く聞けよ!
年末の試験は、本番ではない、だからそこで、こけておいて良かったのだよ!
上手く行った人で、知っているタイプの問題だったら、
逆に、自分自身の弱点がチェックできなかったわけで、損なんです(要注意)。
ホント!
----------------------------
2010年度
第2回 慶大入試プレ 反省会
----------------------------
【数学】(私は、受験生ではないので、問題を一通り見もせず、
全部解くつもりで後ろから解いていって、こけまくったわけですが。。。当然でしょうね。)
A1.
となりに、A2の確率があり、しかも、漸化式が要りそうな、
完答がしんどそうな問題。そして、計算をする便利なスペースが全くない。
私などからすると、サービスの悪い、不親切な出題方法。。。
「解けるもんなら解いてみろ」「ほれ、ミスしろ」
 と、言わんばかりの
と、言わんばかりの問題文の羅列だ。
実は、上手く計算しなくちゃならないのは、(3)くらい。
受験生は、まず、全問をスキャンして作戦を立てる必要があるという
そういうタイプのものです。
この出題方法と、問題用紙。。。
A3はガウスの記号をつかった難問。
(2)だけは、書き出せば、途中が消えるので、ただ単に計算はできましたね。
しかし、他は一貫した方針でアプローチしないとできない。
A4は、この手の出題を、練習してないと、
このシチュエーションで、眠い朝一には、思いっきりしんどい。。。。
すっかり目が冴えた、夕方に、コーヒー飲みながらなら、
楽しんで、工夫して、解けそう。。。そういう代物だ。
(1)をうっかり、私のように、微分したあと、二倍角公式とかで、
楽できないかと計算に走った諸君!!
『甘~~っい!!』

二倍角の公式は、極限や積分では使えるのだが、三角関数の構造を上手く使った問題には、
逆に命取りだ。。。。図形問題でも、ヘタに楽しようとすると、遠回りになる。
機械的にやりすごしたい理系受験生の鬼門である。
一階微分したら、あとは、和積の公式が、見えないといけない。
(わたしはおじさんだから、見えなくていいのだ!)
(2)は、x・x'だけ計算し、きれいにしようとあがいた君!!
それでは、おじさんとおなじだよ!!
何のために、この(2)があるのか?!
こうセットにすると、驚くほどうまく厄介なのが消えてしまうからだ。
B1は割と安易な出題である。それに計算用紙が次のページにある。
さて、これは、A3をとりあえずすてて、
A4に集中した受験生の有利さがみえみえだ。
そして、A1で計算ミスした受験生は、英語と理科で80%を切ると、
奇跡でも起きないと合格できない。

(おじさんには奇跡がおこるだろうが・・・君には無理だ!)
ところが、A1には、計算スペースがない。

実はおじさん、p.6 と、p.7の白紙を、使っていない・・・・
今回が本番ならおそらく、この2ページを駆使した受験生が、合格しただろう。
(おじさんは、そもそも、受験しないのであるから、どうでもいいのだが)
そこで、提案!!!
まず、A1で、計算スペースをケチるな!

見開きになる計算用紙を用意可能ならば、
今回のp.6 と、p.7の白紙を、用意するのだ。
まず、初めにやる作業は、計算用紙の準備割り当てだ。
まちがっても(おじさんのように)問題文のすきまでチョコッと
計算してしまってはならない。。。。自滅である。

狭い所に、わざわざ、計算しにくい問題になっている。
だって、短い問題文で、簡単だったら、
慶応受験生に出題する意味がない・・・・
そして、p.6 と、p.7の白紙は取り出し横に置いてあるだろう。
つづいて、A2.
ページをめくるとp.12と、p.7が白紙だ。
取り出したA2.をここで解くのだ!!!

残念ながら、これをしなかった受験生は、
最後まで正解する、スペースがなく、
精神的に抑圧されて、やる気が無くなり、エフィカシー(苫米地先生の言葉から)が
自分で急低下。。。自滅するのだ。

自分で、エフィカシーを上げやすいように、工夫する
戦略と度胸!

そしたら、B1をp10,11で解く。
受験生は、往々にして、t^2-1で平気で割った式を書いてしまうだろう。
(おじさんは、いいのだ。あえて、気を抜いてそうなっている。
無意識に受験生の為にコケたのだ。)
論述なら配慮する習慣がややあったとしても、
この迫りくる提出期限のなかで、
しかも、欲をそそる(へ)と(ホ)を埋めるだけ。。。
余計、いい加減に当てはめたくなるところだ。。。
その欲求のままに書くと、合格が限りなく遠のくわけだ。

精神的に怠けず、しっかりと、
論述答案作成するのと同じように、
白紙計算スペースにストーリーを展開する必要があります。
その中で、必要な部分を吟味して、空欄に入れよう!!
(おじさんは、物理で暗算しすぎて、運動エネルギーを読み忘れ、
速度をかいてしまったりしている。
t=0がx=Lだったのも、すっかり慌てて忘れている。
欲求のままに。。。

『どっか~ん
 』
』これらミスがなければ、80点は堅いのにだ。この意味がわかるか!
おじさんが、バカなのだ。。。。

 )
)そして、
A4.
工夫をする誘導のココロを察して、
裏の、p8,p.5を使ってしっかり、綺麗に計算する。
さて、
もう一度このように、全部解いてみよう!!
間違えなくなるまで、繰り返せ!!!

修行だと思え!!!
そうすると、合格が近づいていく。

A3は部分点狙いでよい。
解答解説を理解して、今度から使えるようにしよう!!
さて、理科に入ろう。
【物理】
1.わかってしまえば簡単な問題である。
ただ問題設定が単純なのだからと焦るといけない。
一応誘導になっていて親切。Fの符号を間違えるのは、
問題文の言うことをよく聞かず、自分で勝手に答えを急ぐからだ!
(おじさんは、めんどうなので、急いで、こけた)
ちょうど、タイミングがx=0でぶつかることがイメージできたら、
瞬殺のはず。
(眠いおじさんでなかったら、楽勝)
2.これも、簡単。
ローレンツ力をしっかり勉強していたら、x-y平面
y-z平面での運動を写像することは容易。
ちょうどV=0になるところの計算を
等加速度直線運動の方程式がすぐに見えれば、問題ない。
できない人は、最近の問題経験が足りない。
イメージと方程式を一致させる練習問題を
力学から選んで復習しよう。すぐに!
(おじさんは、別にいいです。。。)
3.
(オ)で、状態方程式が使えたら、なんのことはない。
(おじさんは、眠くて忘れた)
以降、物理的考察をするには、
P-Vグラフで考えることをした経験があるかどうかにかかっている。
これは、センスを養うのに良い。
良く復習されたい。
(おじさんも、復習するしかないな)
昔のおじさんなら、90点は堅いだろうか?
【化学】
基本ばかり、いきものばかり・・・
って、化学だけどねえ。
数学、物理に比べると、手抜きな出題で、
得意な人に差が付かず、良くないね。これは。
しっかり計算、練習していると、
できるでしょう。
全部できるようにしてください。
つまづいた問題は、類題を復習、繰り返し、鍛えよう!!
受験生として鍛えていたら、おじさんでも、90点とれそうだ。。。