<多文化共生の「共生」は、梁泰昊が初めて使った>説 飛田雄一
(『むくげ通信』328号(2025.1.26)より)
※PDFファイル版は、https://ksyc.jp/mukuge/328/hida-yanteho.pdf
梁泰昊(ヤンテホ)は、親しい友人だった。1970年代、80年代に申京煥支援、民族差別と闘う連絡協議会(以下、民闘連)、指紋押なつ反対などで行動をともにした。
ある民闘連集会での会話。その場にいあわせたのではないが、直後?に彼から聞いた。
梁泰昊 共生ということばをどうでしょう?
李仁夏 それは生物学用語だからだめだよ。
民闘連大会は、第1回(1975、大阪)から第16回(1990、神戸)まで開かれた。私はほぼ皆勤だったと思う。第6回集会(1980)が、八尾。記念講演が李仁夏、テーマが「⽣活に根ざした地域の闘いを結集しよう!」なので、この時ではないかと推測している。いまでは、政府・行政もこぞって使う「共生」、少々さび付いた言葉だ。
●
梁泰昊は、1998年7月22日、クローン病のため死去した。享年51歳。以下、簡単な記録。
1946年12月13日 東大阪市生まれ
1971年3月 関西大学文学部史学科卒業
1973~78年 申京煥君を支える会に事務局として参加
1977年 民闘連全国交流尼崎集会より兵庫民闘連会員として参加
1984年1月28日 神戸学生青年センター朝鮮史セミナー講演「在日朝鮮人青年は語る-民族差別に抗する闘いの中で」
1985年3月1日 指紋押なつを拒否
1989年9月29日 指紋押捺拒否裁判が昭和天皇死亡による恩赦となる。
1993年10月、北海道移住(~95年)
1995年10月1日~98年4月27日 民団滋賀県本部事務局長
1997年4月~98年3月 関西大学非常勤講師(朝鮮語担当)
●
梁泰昊のよく知られた本は『プサン港にかえれない』(1984.8、創生社発行/発売元は第三書館)。題名は、チョヨンピルの「釜山港へ帰れ」のパロディーだ。彼らしい。そこで、在日論を展開している。1978年から1984年に「交流」「民闘連ニュース」「朝鮮研究」などに書いたものに新しい文章を加えている。
そのなかに、「『太く短く』から『細く長く』へ」(『民闘連ニュース』32号、1982.7)がある。そこに以下の一文がある。
「われわれは民族差別をなくすために日本人と共闘するということをやってきた。共闘といっても日本人の側ではそれによって具体的なメリットというものはない。国籍条項を撤廃したところで、日本人が利益をうけとることは何もない。にもかかわらず何故共闘するのかというのは今一度改めて考えてみる必要がある。共闘するということの前提には共に生きる『共生』といういうことがあったはずではないか。その意味するところを今後具体的にふくらませていくことが課題になるだろう」。
私は、ここで使われた「共生」が、多文化共生の共生の初出ではないかと考えている。(どうか、研究者の方々にはそのあたりの調査をお願いしたい。)
●
梁泰昊は、80年代には、民闘連のイデオローグ的な存在となったが、それ以前から出版活動に力をいれていた。
1974年には、金容海『本名は民族の誇り』(おおぞら書房、1974.9)を梁泰昊がだしている。奥付には、「発行者・梁泰昊」となっている。(その復刻版は、碧川書房、1996.3。ちなみに装丁の鄭雄男も私と共通の友人だ。)
1975年には、『韓国のことわざ』を出している。この2冊は彼の自費出版によるものだと思う。
●
1985年3月1日、彼は指紋押捺を拒否した。略式裁判に応じずに裁判が開かれた。その意見陳述が「サラム宣言」。「朝鮮人宣言」ではない。彼は、人間の普遍的な権利を常に強調していたが、それは、朝鮮人としての権利ではなく、サラム(朝鮮語で人間の意)としての権利を主張したのである。同名の本が「指紋押捺拒否裁判意見陳述」を副題として、1987年、神戸学生青年センターから出版されている。あとがきに、以下のようにある。
「いま、指紋押なつ拒否が『サラム宣言』であるというのは、一方的に日本国籍を剥奪した上で、外国人であることを問われる以前から生活の基盤を築いている者を、外国人という理由で退去強制の対象とし、その担保として指紋を採取することが許されるのかという、人間としての問いに他ならない。外国人になるという原因を作った者が、外国人になった結果をとがめているものであり、はなはだしい『マッチポンプ』なのである。/指紋強制が差別であるというのは、屈辱感等という形而上的なもの以上に、日本における『居住権』という、生存に直結するもっとも根本の人権にかかわっているからである。それが、『定住』の実態をふまえて一九八〇年代になって表出した意味である。/あえて言おう。われわれは日本社会にあって押しもおされもせぬ『サラム』であると」。
●
彼はエッセイの名手であるが、「兵庫指紋拒否をともに闘う連絡会」ニュース8号(1998.12.1)に掲載された「(指紋は)バーコードなのだ」が秀逸である。
最後に次の一文がある。
「人間と物品を同じように扱うことができるという発想が、人権を損なうことになるのではないか。指絞によって人間を管理するということもまた同様であろう。バーコードとは商品に与えられた指紋であり、指紋は人間を捕捉するバーコードなのである。」
●
『季刊三千里』誌上での姜尚中・梁泰昊論争がよく知られている。
・ 姜尚中:42号(1985年5月)「『在日』の現在と未来の間」
・ 梁泰昊:43号(同年8月)「事実としての『在日』―姜尚中氏への疑問―」
・ 姜尚中:44号(同年11月)「方法としての『在日』/梁泰昊氏の反論に答える」
・ 梁泰昊:45号(1986年2月)「共存・共生・共感/姜尚中氏への疑問(Ⅱ)」
姜尚中のことが話題となったとき、梁泰昊が「あんな有名な先生と論争していたんだなあ」と言っていたことがある。姜尚中が有名になったあとのことだ。この論争は、飯沼二郎編著『在日韓国・朝鮮人―その日本社会における存在価値』(海風社、1988.9)にも再録されている。また、「わったり☆がったり」というjihyang_tomoさんのブログに「「事実」か「方法」か~梁泰昊・姜尚中『三千里』誌上論争(1985)から学ぶ」がある。そこではでその論争の内容が詳しく紹介されている。
私の印象としては、当時梁泰昊の行っていた内容をいま姜尚中が言っているように思う。
またその時期のアグネス・チャン・梁泰昊の対談「国籍は、どうってことないの」(『世界』1985/10)も興味深い。
●
彼は、それほど強いものではなかったが、吃音だった。申京煥君を支える会の最初のころはそうだった。その後、自身も人前で話すことも多くなり、講演の機会も増えていったが、彼自身は多くの努力を払ってそれを克服したのだと思う。
1988~89年、「ふるさと創生1億円」というのがあった。そのとき淡路島の自治体が、金塊を作って展示して話題になった。彼は特別な印刷技術を駆使する印刷所で働いていたが、その金塊に印刷をしたのが彼の会社だった。何が書かれているのか、見たことがないので、しらんけど。
北海道に引っ越しして奥さんの実家の仕事を手伝っていた時代がある(93~95年)。その後、滋賀県で民団の事務局長をしていたこともあった。
民闘連時代、行政法の専門家・岡﨑勝彦さんと交流があった。国籍条項裁判、指紋押捺裁判などで証言もしてくださった。『兵庫在日外国人人権協会40年誌/民族差別と排外に抗して―在日韓国・朝鮮人差別撤廃運動1975~2015』(2015.8)というすぐれた本がある。そこに「梁泰昊(1946~1998)を想う―「事実としての在日」に即して―」(岡崎勝彦)がある。多くの思い出も書かれている。
同書には、「梁泰昊と民闘連」の項目もある。「1975.05.09-10 尼崎市児童手当徹夜交渉参加(個人として)/1977.10.8-10 第3 回民闘連全国交流尼崎集会より兵庫民闘連会員として参加、その後全国代表者会議に兵庫の代表(役職なし)として参加/1977.10~1979.03市報〝あまがさき〟に「民族差別をなくすため」連載に協力」などと兵庫民闘連とのかかわりについて書かれている。また彼の文章のほかに、関連の遺稿、著作目録が掲載されている。再録されている遺稿に、「主体性問い続けた2世―民族差別克服と私の総括―」(1995.01.06、統一日報)もある。
最初と最後の部分を紹介する。
主体性問い続けた2世―民族差別克服と私の総括
解放50年というのは、在日2世が生まれておじさん、おばさんになる過程と重なっている。かつて 1 世から「パンチョッパリ」と嘆かれ、日本人から「チョーセン」と突き放された2世であるが、いつの間にかライフサイクルの後半期に入ってしまった。/解放50年という大きな時代のうねりの中で、在日2世は常に二方向からの圧力を感じながら自我のありかを追い求めてきた。(中略)いまではだれもが「共生」を口にするようになったが、そのためにはまず自分が何であるかを見定めなくてはならないからだ。/解放30年がたって在日同胞はようやく「個人」として解放されつつある。これからの若い世代には「主体性」を国家や民族という枠組みに探すのではなく、自分自身の中に夢を求めて、自分が本当にしたいことに情熱を燃やしていただきたい。/お楽しみはこれからだ!
●
1998年、私も関係した民闘連の「補償・人権法」の策定に彼も参加し、その解説本の執筆も担当している。
金英達・宮田節子と共著『創氏改名』(1991、明石書店)もすぐれた本だ。
また梁泰昊の仕事のひとつに、『朝鮮人強制連行論文集成』(1993、明石書店)がある。その調査の時の話だと思うが、こんなことがあった。
長野に調査にいくとき、現地の人から電話があった。「“シンマイ”の記者』に迎えに行かせますから」と。シンマイ?、新米ではなくて信濃毎日の記者こととだった。シャンシャン。
『プサン港に』の本のあとも、雑誌論文、エッセイを発表している。「『地方参政権』は歴史の通過点」(『現代コリア』、1995.10)、「<追悼>『さよなら、新井将敬さん』―『ガラスの天井』のもどかしさ」(『アプロ21』、1998/03)など。また、『在日韓国・朝鮮人読本―リラックスした関係を求めて』(緑風出版、1996/01)は、当時としては読みやすい、すぐれた入門書だった。
また訳書として、李讃三『戦争になれば飢えは終わる―北朝鮮庶民の願いと現実』(三五館、1995)、金璡『ドキュメント朴正煕時代』(亜紀書房、1993)、金敬勲編『韓国が変わる―新世代の生活と意見』(亜紀書房、1995)、魯樹旻『ソウル火の海』(光文社、1994)がある。
「共生」の起源?を求めて、書いているうちに、いろいろ思い出し、梁泰昊のことを書かせていただいた。ほんとに若すぎた惜しい死だった。
(『むくげ通信』328号(2025.1.26)より)
※PDFファイル版は、https://ksyc.jp/mukuge/328/hida-yanteho.pdf
梁泰昊(ヤンテホ)は、親しい友人だった。1970年代、80年代に申京煥支援、民族差別と闘う連絡協議会(以下、民闘連)、指紋押なつ反対などで行動をともにした。
ある民闘連集会での会話。その場にいあわせたのではないが、直後?に彼から聞いた。
梁泰昊 共生ということばをどうでしょう?
李仁夏 それは生物学用語だからだめだよ。
民闘連大会は、第1回(1975、大阪)から第16回(1990、神戸)まで開かれた。私はほぼ皆勤だったと思う。第6回集会(1980)が、八尾。記念講演が李仁夏、テーマが「⽣活に根ざした地域の闘いを結集しよう!」なので、この時ではないかと推測している。いまでは、政府・行政もこぞって使う「共生」、少々さび付いた言葉だ。
●
梁泰昊は、1998年7月22日、クローン病のため死去した。享年51歳。以下、簡単な記録。
1946年12月13日 東大阪市生まれ
1971年3月 関西大学文学部史学科卒業
1973~78年 申京煥君を支える会に事務局として参加
1977年 民闘連全国交流尼崎集会より兵庫民闘連会員として参加
1984年1月28日 神戸学生青年センター朝鮮史セミナー講演「在日朝鮮人青年は語る-民族差別に抗する闘いの中で」
1985年3月1日 指紋押なつを拒否
1989年9月29日 指紋押捺拒否裁判が昭和天皇死亡による恩赦となる。
1993年10月、北海道移住(~95年)
1995年10月1日~98年4月27日 民団滋賀県本部事務局長
1997年4月~98年3月 関西大学非常勤講師(朝鮮語担当)
●
梁泰昊のよく知られた本は『プサン港にかえれない』(1984.8、創生社発行/発売元は第三書館)。題名は、チョヨンピルの「釜山港へ帰れ」のパロディーだ。彼らしい。そこで、在日論を展開している。1978年から1984年に「交流」「民闘連ニュース」「朝鮮研究」などに書いたものに新しい文章を加えている。
そのなかに、「『太く短く』から『細く長く』へ」(『民闘連ニュース』32号、1982.7)がある。そこに以下の一文がある。
「われわれは民族差別をなくすために日本人と共闘するということをやってきた。共闘といっても日本人の側ではそれによって具体的なメリットというものはない。国籍条項を撤廃したところで、日本人が利益をうけとることは何もない。にもかかわらず何故共闘するのかというのは今一度改めて考えてみる必要がある。共闘するということの前提には共に生きる『共生』といういうことがあったはずではないか。その意味するところを今後具体的にふくらませていくことが課題になるだろう」。
私は、ここで使われた「共生」が、多文化共生の共生の初出ではないかと考えている。(どうか、研究者の方々にはそのあたりの調査をお願いしたい。)
●
梁泰昊は、80年代には、民闘連のイデオローグ的な存在となったが、それ以前から出版活動に力をいれていた。
1974年には、金容海『本名は民族の誇り』(おおぞら書房、1974.9)を梁泰昊がだしている。奥付には、「発行者・梁泰昊」となっている。(その復刻版は、碧川書房、1996.3。ちなみに装丁の鄭雄男も私と共通の友人だ。)
1975年には、『韓国のことわざ』を出している。この2冊は彼の自費出版によるものだと思う。
●
1985年3月1日、彼は指紋押捺を拒否した。略式裁判に応じずに裁判が開かれた。その意見陳述が「サラム宣言」。「朝鮮人宣言」ではない。彼は、人間の普遍的な権利を常に強調していたが、それは、朝鮮人としての権利ではなく、サラム(朝鮮語で人間の意)としての権利を主張したのである。同名の本が「指紋押捺拒否裁判意見陳述」を副題として、1987年、神戸学生青年センターから出版されている。あとがきに、以下のようにある。
「いま、指紋押なつ拒否が『サラム宣言』であるというのは、一方的に日本国籍を剥奪した上で、外国人であることを問われる以前から生活の基盤を築いている者を、外国人という理由で退去強制の対象とし、その担保として指紋を採取することが許されるのかという、人間としての問いに他ならない。外国人になるという原因を作った者が、外国人になった結果をとがめているものであり、はなはだしい『マッチポンプ』なのである。/指紋強制が差別であるというのは、屈辱感等という形而上的なもの以上に、日本における『居住権』という、生存に直結するもっとも根本の人権にかかわっているからである。それが、『定住』の実態をふまえて一九八〇年代になって表出した意味である。/あえて言おう。われわれは日本社会にあって押しもおされもせぬ『サラム』であると」。
●
彼はエッセイの名手であるが、「兵庫指紋拒否をともに闘う連絡会」ニュース8号(1998.12.1)に掲載された「(指紋は)バーコードなのだ」が秀逸である。
最後に次の一文がある。
「人間と物品を同じように扱うことができるという発想が、人権を損なうことになるのではないか。指絞によって人間を管理するということもまた同様であろう。バーコードとは商品に与えられた指紋であり、指紋は人間を捕捉するバーコードなのである。」
●
『季刊三千里』誌上での姜尚中・梁泰昊論争がよく知られている。
・ 姜尚中:42号(1985年5月)「『在日』の現在と未来の間」
・ 梁泰昊:43号(同年8月)「事実としての『在日』―姜尚中氏への疑問―」
・ 姜尚中:44号(同年11月)「方法としての『在日』/梁泰昊氏の反論に答える」
・ 梁泰昊:45号(1986年2月)「共存・共生・共感/姜尚中氏への疑問(Ⅱ)」
姜尚中のことが話題となったとき、梁泰昊が「あんな有名な先生と論争していたんだなあ」と言っていたことがある。姜尚中が有名になったあとのことだ。この論争は、飯沼二郎編著『在日韓国・朝鮮人―その日本社会における存在価値』(海風社、1988.9)にも再録されている。また、「わったり☆がったり」というjihyang_tomoさんのブログに「「事実」か「方法」か~梁泰昊・姜尚中『三千里』誌上論争(1985)から学ぶ」がある。そこではでその論争の内容が詳しく紹介されている。
私の印象としては、当時梁泰昊の行っていた内容をいま姜尚中が言っているように思う。
またその時期のアグネス・チャン・梁泰昊の対談「国籍は、どうってことないの」(『世界』1985/10)も興味深い。
●
彼は、それほど強いものではなかったが、吃音だった。申京煥君を支える会の最初のころはそうだった。その後、自身も人前で話すことも多くなり、講演の機会も増えていったが、彼自身は多くの努力を払ってそれを克服したのだと思う。
1988~89年、「ふるさと創生1億円」というのがあった。そのとき淡路島の自治体が、金塊を作って展示して話題になった。彼は特別な印刷技術を駆使する印刷所で働いていたが、その金塊に印刷をしたのが彼の会社だった。何が書かれているのか、見たことがないので、しらんけど。
北海道に引っ越しして奥さんの実家の仕事を手伝っていた時代がある(93~95年)。その後、滋賀県で民団の事務局長をしていたこともあった。
民闘連時代、行政法の専門家・岡﨑勝彦さんと交流があった。国籍条項裁判、指紋押捺裁判などで証言もしてくださった。『兵庫在日外国人人権協会40年誌/民族差別と排外に抗して―在日韓国・朝鮮人差別撤廃運動1975~2015』(2015.8)というすぐれた本がある。そこに「梁泰昊(1946~1998)を想う―「事実としての在日」に即して―」(岡崎勝彦)がある。多くの思い出も書かれている。
同書には、「梁泰昊と民闘連」の項目もある。「1975.05.09-10 尼崎市児童手当徹夜交渉参加(個人として)/1977.10.8-10 第3 回民闘連全国交流尼崎集会より兵庫民闘連会員として参加、その後全国代表者会議に兵庫の代表(役職なし)として参加/1977.10~1979.03市報〝あまがさき〟に「民族差別をなくすため」連載に協力」などと兵庫民闘連とのかかわりについて書かれている。また彼の文章のほかに、関連の遺稿、著作目録が掲載されている。再録されている遺稿に、「主体性問い続けた2世―民族差別克服と私の総括―」(1995.01.06、統一日報)もある。
最初と最後の部分を紹介する。
主体性問い続けた2世―民族差別克服と私の総括
解放50年というのは、在日2世が生まれておじさん、おばさんになる過程と重なっている。かつて 1 世から「パンチョッパリ」と嘆かれ、日本人から「チョーセン」と突き放された2世であるが、いつの間にかライフサイクルの後半期に入ってしまった。/解放50年という大きな時代のうねりの中で、在日2世は常に二方向からの圧力を感じながら自我のありかを追い求めてきた。(中略)いまではだれもが「共生」を口にするようになったが、そのためにはまず自分が何であるかを見定めなくてはならないからだ。/解放30年がたって在日同胞はようやく「個人」として解放されつつある。これからの若い世代には「主体性」を国家や民族という枠組みに探すのではなく、自分自身の中に夢を求めて、自分が本当にしたいことに情熱を燃やしていただきたい。/お楽しみはこれからだ!
●
1998年、私も関係した民闘連の「補償・人権法」の策定に彼も参加し、その解説本の執筆も担当している。
金英達・宮田節子と共著『創氏改名』(1991、明石書店)もすぐれた本だ。
また梁泰昊の仕事のひとつに、『朝鮮人強制連行論文集成』(1993、明石書店)がある。その調査の時の話だと思うが、こんなことがあった。
長野に調査にいくとき、現地の人から電話があった。「“シンマイ”の記者』に迎えに行かせますから」と。シンマイ?、新米ではなくて信濃毎日の記者こととだった。シャンシャン。
『プサン港に』の本のあとも、雑誌論文、エッセイを発表している。「『地方参政権』は歴史の通過点」(『現代コリア』、1995.10)、「<追悼>『さよなら、新井将敬さん』―『ガラスの天井』のもどかしさ」(『アプロ21』、1998/03)など。また、『在日韓国・朝鮮人読本―リラックスした関係を求めて』(緑風出版、1996/01)は、当時としては読みやすい、すぐれた入門書だった。
また訳書として、李讃三『戦争になれば飢えは終わる―北朝鮮庶民の願いと現実』(三五館、1995)、金璡『ドキュメント朴正煕時代』(亜紀書房、1993)、金敬勲編『韓国が変わる―新世代の生活と意見』(亜紀書房、1995)、魯樹旻『ソウル火の海』(光文社、1994)がある。
「共生」の起源?を求めて、書いているうちに、いろいろ思い出し、梁泰昊のことを書かせていただいた。ほんとに若すぎた惜しい死だった。










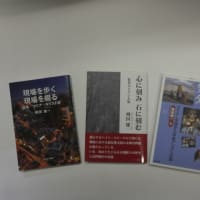





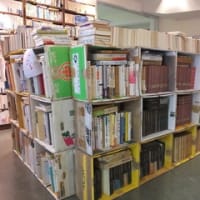
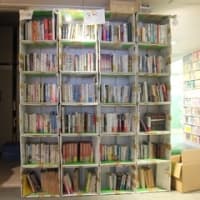








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます