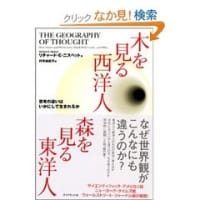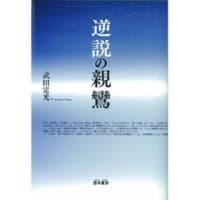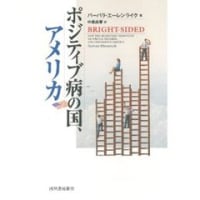宣伝も兼ねてかどうかは分からないが、先日行なわれた周防正行監督と草刈民代夫妻の講演会に足を運んだ。監督は「宣伝費があまりないので、夫婦ともどもこうして行脚して・・」と言って笑いを取っていたが。
ダンシング・チャップリンの詳細はこちらで。
この映画は「バレエ」を映画化したものであり、映画の「題材がバレエ」ではないとのこと。つまり、普通の映画であれば、監督は俳優に細かく指示を出し、ベストのカメラアングルを考え、自分が納得できるまで何テイクでも取り直しができる。しかし、この映画では、
1.バレエの芸術的・技術的完成度について、口出しできない。(バレエのプロではないから)
2.バレエダンサーが同じ演目を繰り返し踊れるのは精神的・肉体的な面から2度まで。
という辛さがあったという。素人目にも大変そうであることは想像できるから、プロたちは、相当の緊張だっただろう。
そうまでしても、今回の映画に敢えて挑んだのは「単純にバレエを踊る妻を観て美しいと思った。その美しいものを映画にしたかった」からだそうである。ちょっと「ごちそうさま」と言いたくなる場面であったが、美しい妻を見てデヘデヘするイメージではなく、もっと素朴に美しいと思ったそうだ。話を聞いているうちに「妻」という言葉を使うときは客観的に見た関係性を重視していると分かった。草刈さんを自分の妻として認識し、人格を持たせたときの言い方は「奥さん」となるのだ。例えば、「うちの奥さんは肉を食べないので・・」という風に。そして、仕事に関係する話になると「草刈」となる。バレエを見始めたのは草刈さんと結婚したからであり、そうでなければこんな美しいものに出合わなかったという感謝と、踊る妻を観て「美しい」と思う心、そんなものがあるにもかかわらず、その3つの言葉の使い分けは鮮やかの一言に尽きた。三色パンのように、きちんと分かれていながら、周防さんは草刈さんをパンのように大きく包んでいる(いえ、別に今、おなかが空いているわけではありません)、そんな雰囲気を感じた。
そして、もうひとつ、周防監督が払うバレエへの敬意の高さと理解の深さに胸を打たれた。先に書いたとおり、やろうと思えばカメラはどのアングルからでも撮れる。この場面はこのアングルがベストだ!と感じることもあったそうだ。でも、監督はそれをしなかった。なぜか。
バレエは、ナマの舞台で披露するものであり、したがって、正面に居る観客が一番感動してくれるように、ダンサーが観客に対し一番美しい姿に写るように構成されているからだそうだ。その本質を歪曲させて、例えば後ろから・上からとアングルを決めるのはNG、いわばクラシックバレエに対する冒涜になるというスタンスなのだ。自分の感性を、撮る対象の本質のために譲るというのは、簡単そうでなかなかできることではないように思う。芸術を扱うプロとして、感性は表現したいと思っていることの源ではないか。
そんな話を聴いていて、いつもの「発展させ癖」が出てしまった。
物事や関わる人を、深く理解したいと思う。だから、様々な角度から見たり、何かと比較してみたりする。もがくうちに理解が深まるのを感じて、ある一定で「これはこういうもの」「この人はこんな人」とある程度のところで着地点を見つけたくなる。降りるとそれ以上、掘り下げなくても良くなってラクだからである。
問題はそこからだ。
着地してから考えなくてはいけないのは、
言葉で伝えるべきこと。
言葉で伝えるべきではないこと。
感じなければならないこと。
感じたけれど伝えなくてよいこと。
感じなくてよいこと。
のバランスであり、それに対する自分の機微を磨くことだと思う。
この人を理解したと思って、こちらが掴んだことを何でも言葉にするだけが良いとは限らない。理解しているからこそ、目を向けない優しさもあろう。こちらが感じていることを伝える手段として言葉が最良ではない場合もある。会話の間であったり、表情であったり、何かの行動で示すほうが相手の心に届くケースを体験したことはないだろうか。
私の言葉を含めたどんな「機微」が相手の心を癒し、元気づけるのか、これからよく考えなくてはいけない。なぜなら、どんな人にもその人の「正面」があるからだ。私が良かれと思って掛けた言葉も、した行動も、正面を傷つけてしまうようであれば、それは私の単なる自己満足になってしまうからだ。
草刈さんが「美しいと感じてもらうために自分が何を発散すべきか。それを追うための芯はブレてはいけない」と話していた。
相手に心楽しく心休まる心踊る時間を提供するためには自分が何を発散すべきか、その芯を創るところから始めよう。
またひとつ、学んだ。
ダンシング・チャップリンの詳細はこちらで。
この映画は「バレエ」を映画化したものであり、映画の「題材がバレエ」ではないとのこと。つまり、普通の映画であれば、監督は俳優に細かく指示を出し、ベストのカメラアングルを考え、自分が納得できるまで何テイクでも取り直しができる。しかし、この映画では、
1.バレエの芸術的・技術的完成度について、口出しできない。(バレエのプロではないから)
2.バレエダンサーが同じ演目を繰り返し踊れるのは精神的・肉体的な面から2度まで。
という辛さがあったという。素人目にも大変そうであることは想像できるから、プロたちは、相当の緊張だっただろう。
そうまでしても、今回の映画に敢えて挑んだのは「単純にバレエを踊る妻を観て美しいと思った。その美しいものを映画にしたかった」からだそうである。ちょっと「ごちそうさま」と言いたくなる場面であったが、美しい妻を見てデヘデヘするイメージではなく、もっと素朴に美しいと思ったそうだ。話を聞いているうちに「妻」という言葉を使うときは客観的に見た関係性を重視していると分かった。草刈さんを自分の妻として認識し、人格を持たせたときの言い方は「奥さん」となるのだ。例えば、「うちの奥さんは肉を食べないので・・」という風に。そして、仕事に関係する話になると「草刈」となる。バレエを見始めたのは草刈さんと結婚したからであり、そうでなければこんな美しいものに出合わなかったという感謝と、踊る妻を観て「美しい」と思う心、そんなものがあるにもかかわらず、その3つの言葉の使い分けは鮮やかの一言に尽きた。三色パンのように、きちんと分かれていながら、周防さんは草刈さんをパンのように大きく包んでいる(いえ、別に今、おなかが空いているわけではありません)、そんな雰囲気を感じた。
そして、もうひとつ、周防監督が払うバレエへの敬意の高さと理解の深さに胸を打たれた。先に書いたとおり、やろうと思えばカメラはどのアングルからでも撮れる。この場面はこのアングルがベストだ!と感じることもあったそうだ。でも、監督はそれをしなかった。なぜか。
バレエは、ナマの舞台で披露するものであり、したがって、正面に居る観客が一番感動してくれるように、ダンサーが観客に対し一番美しい姿に写るように構成されているからだそうだ。その本質を歪曲させて、例えば後ろから・上からとアングルを決めるのはNG、いわばクラシックバレエに対する冒涜になるというスタンスなのだ。自分の感性を、撮る対象の本質のために譲るというのは、簡単そうでなかなかできることではないように思う。芸術を扱うプロとして、感性は表現したいと思っていることの源ではないか。
そんな話を聴いていて、いつもの「発展させ癖」が出てしまった。
物事や関わる人を、深く理解したいと思う。だから、様々な角度から見たり、何かと比較してみたりする。もがくうちに理解が深まるのを感じて、ある一定で「これはこういうもの」「この人はこんな人」とある程度のところで着地点を見つけたくなる。降りるとそれ以上、掘り下げなくても良くなってラクだからである。
問題はそこからだ。
着地してから考えなくてはいけないのは、
言葉で伝えるべきこと。
言葉で伝えるべきではないこと。
感じなければならないこと。
感じたけれど伝えなくてよいこと。
感じなくてよいこと。
のバランスであり、それに対する自分の機微を磨くことだと思う。
この人を理解したと思って、こちらが掴んだことを何でも言葉にするだけが良いとは限らない。理解しているからこそ、目を向けない優しさもあろう。こちらが感じていることを伝える手段として言葉が最良ではない場合もある。会話の間であったり、表情であったり、何かの行動で示すほうが相手の心に届くケースを体験したことはないだろうか。
私の言葉を含めたどんな「機微」が相手の心を癒し、元気づけるのか、これからよく考えなくてはいけない。なぜなら、どんな人にもその人の「正面」があるからだ。私が良かれと思って掛けた言葉も、した行動も、正面を傷つけてしまうようであれば、それは私の単なる自己満足になってしまうからだ。
草刈さんが「美しいと感じてもらうために自分が何を発散すべきか。それを追うための芯はブレてはいけない」と話していた。
相手に心楽しく心休まる心踊る時間を提供するためには自分が何を発散すべきか、その芯を創るところから始めよう。
またひとつ、学んだ。