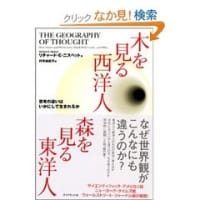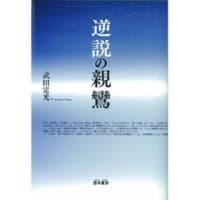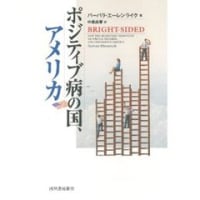●逆説の親鸞 武田定光 著
著者は因速寺というお寺の住職である。「逆説」とついていても、その世界にいらっしゃるのだから、基本スタンスは「親鸞賛辞」であろうとタカをくくっていたところがある。
見事に裏切られた。読み出してすぐ、「アイドルとしての親鸞」というフレーズが出てくる。私たちは親鸞といういわば「人となり」を知っているのか?という問いが、その前にある。無論、知ろうはずもない。だから、私たちは彫刻や絵画や著作を通して、自分たちの内面に「親鸞像」を作り上げている。それを「アイドルとしての親鸞」と呼んでいる、と。・・・まぁ、確かにおっしゃるとおり、と、いきなり出鼻をくじかれた感があった。
そして、現在まで受け継がれてきている親鸞の教えは、録音などをして忠実に残されたものではなく、弟子から弟子へと口伝えで残ってきたものも多い。伝える弟子の解釈が入り、微妙に変化してきても当然だ、本当に、ストレートに親鸞の教えかどうかは・・・とアイドル熱をあげている人間にとっては少々興ざめなことが書いてあったりもする。
この本のキーワードは「南無阿弥陀仏」と「無量」であると、私は思う。
「南無阿弥陀仏」の直訳は「ひとの思いでは量ることのできないことに、すべてを任せなさい」となるそうだ。これは、「生きる意味」など人間が量ることはできないという絶対否定を表している。むしろ、生きることが私に問うていると。
「無量」の量は今で言う「意味」に近しい。そうすると、「無意味」。もうひとつは「量ることができない」、つまり「自力無効」=自力の知恵では、永遠に量ることができない、となるそうだ。「不可知」「非知」とも表される。
こう書くと、どちらも一見前向きではなくて脱力感に襲われそうだが、この「そもそも、できない」といわば開き直ってしまうところが親鸞の真髄ではないかと、この本を読んで思った。禅宗は血を吐くような修行に耐え、戒律を厳守してこそ救われる。法然はお経を唱えれば救われる。それは、裏を返せば「それをしないと救われない」ということではないか、と親鸞は思い、そうではない、浄土はもっと自由なものなのだ、と考えた。著者は「親鸞は、自由に、浄土をメタファーとして表現しているように思える」と書いている。そして、「そのメタファーの世界を自由に遊べるようになるためには、必ず「非知」が根底になければならない。非知が根底に成り立つことで、浄土がメタファーとして再生されてくる。決して、この世の知を延長したところに浄土はないと知ったところからの再生だ」とも。
自然に思考が向かうのは、先日読んだ「ポジティブ病の国、アメリカ」である。常にポジティブであること求められ、ポジティブであることが社会的個人的価値に繋がるというアメリカ。そんな国民性からすれば、無量などは、何が何でも近寄りたくもない、絶対に避けたいネガティブとして映ることだろう。しかし、そのアメリカ人もポジティブであるべきという強迫観念に悩んでいるのだ。ネガティブに考えてしまう自分を恐れて、さらなるポジティブを求めると言う。日本人だって、ポジティブシンキングで乗り切ろう!などと落ち込んでいる人への励みの言葉にポジティブを挿んだりする。ある程度の力が残っているときには、そう言われて前向きになれる気もする。でも、すべてに疲れきっているときに言われて、よしっと方向転換するのは、ムリである。力がないと言っているのに、よしっと思う力など、どこにあるはずもない。少なくとも私は。ならば、絶対否定を一旦引き受けるという試みをしてみてはどうだろうと思う。「自分の力ではどうにもできない」というところをスタート地点にしてみるのだ。プール中でもがいていて不安でたまらないときに、底に足がつくと安心する。あとは、水面へと向かえば良いだけだ。その足がつくところに絶対否定を置いてみる。そこには、もがきつつ上へ上へとばたばたするより、遥かに落ち着いて静寂な力に満ち溢れた空間があると、私は感じる。前へ進むのに何のコワさもない、父のような力強さと母のような優しさを持った絶対否定が、私を見守ってくれている。そんな気がしてならない。
反面、親鸞の考える浄土は、優しいけれど厳しいとも感じている。先述したように他宗のようにああせよ、こうせよと迫ることもない。肉を食べようが、酒を飲もうが、自由である。でも、こうすればよいという決定的な解、導きもないのだ。浄土はオルタナティブ的ではない。浄土はどこかにあるものではない。我々の中にある。「私はこんなに苦しいのですが、どうすれば救われるでしょうか」と問うてみたところで答えはきっと「非知」なのだろう。それもこれもすべては、個人の心根にかかっている。しかし、その心根は絶対否定に護られ、そして底抜けに「解放」されている。だから、例えばある人にとっては「苦しまずに畳の上で死ぬこと」が浄土かもしれない。ある人にとっては「愛する人と穏やかで濃密な時間を過ごすこと」が浄土かもしれない。各々違い、そして死ぬときに感じても生きている間に感じてもよい。筆者の言うとおり浄土はメタファーなのだから。そう私なりに解釈したとき、あらゆることの「本質」を、何より己の本質を見よ、と突きつけられた気がした。それは、空からと言うよりは地中深くから。腹の底にドスンと一本、杭を打ち込まれたような胸苦しさがあった。
すべてのものが浄土となりうる、だからこそ己の本質を見て、「「量ることはできない」という絶望」という「希望」」を感じたところから、新たな世界が開けるような気が、今はしている。
二度読んでも、また読みたい。そんな一冊である。