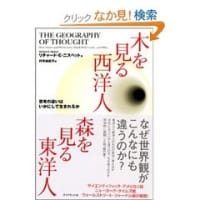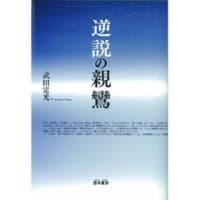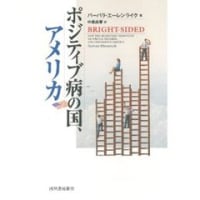●木を見る西洋人 森を見る東洋人 リチャード・E・ニスベット 著
自分が常々、半無意識的に興味を抱いていることについての本を読み、ふむふむと新たな思考の「皺」を刺激されたのち、私はどうやらその後ろにあと一冊(か何冊か?!)「数珠」を繋げたいと思う性格らしい・・・。と回りくどい言い方をしてしまった。先日読んだ「ポジティブ病の国、アメリカ」。確かにそういう表現をすれば日本人は「ネガティブ病」かもしれない。どうして、そんな違いが生まれるのか・・・。そんな疑問を読後にちょこっと抱いていたら、本屋さんでこのタイトルを目にした。「本は本を呼ぶ」んだねぇ・・・。
文化の違いはずぅっと昔から脈々と培われ、受け継がれてきたものなので、「ここのポイントでこうだから今の違いがある!」とは言えない。筆者は、古代ギリシアと古代中国まで遡っている。
当時のギリシア人は他に類を見ない強烈な「個人の主体性の観念」を持っていたと言う。つまり、自分の人生を自分で選択したままに生きるという考え方で、それは現代人よりも明確であったと言う。ギリシア人の幸福の定義は、制約から解き放たれた人生を謳歌することだったと言うから、相当なものだ。そして、ギリシア人のもうひとつの特徴は「世の中に対する好奇心の強さ」であった。自分たちが生きる世界の本質に思いをめぐらし、根本原理を探究することは、ギリシア人の楽しみの源だった。「school」はもちろん学校と言う意味だが、その語源はギリシア語で「余暇」を表す「schoe(スコレー)」だそうだ。ギリシア人にとっての余暇は、知識を追い求める自由だった。・・・絶句。
これに対し、古代中国における主体性に対応する概念は「調和」だった。例はたくさん書いてあって紹介しきれないが、例えば中国人は単旋律の音楽を好んだ。歌い手たちは全員同じメロディーを歌い、楽器は揃って同じ旋律を奏でた。ギリシア人は楽器や声がみな別のパートを担当するような交響楽を生み出したことからも、両者の違いが明らかだろう。
この後は、色々な角度から西洋人と東洋人に課題を与え、その実験結果の違いを記述している。それをつらつらと読んでいると・・・寝てしまった!!実験結果って耳で聞いて視覚で実感すると面白いのだけれど、文字で追うと脱落してしまうのは私だけかしら・・・。
そんな中でも面白いと思う「違い」があった。
①「個人主義」「相互独立」的な西洋人は、子育て中、子どもに対して自分自身で選択するように促す。「今すぐベッドに行く?それとも先にお菓子を食べてからにしたい?」というふうに。「相互強調」的な東洋人は、子どものための選択を親が行なう。昨今は就職先も親が行なったり・・・。あ、それは日本だけか。
②物事の認知についても違いがある。西洋人は「個人」の集まりで成り立っているため「個ー集合」で認知し、東洋人は「協調」を重んじたため「部分ー全体」で認知する。だから、「にわとり・牛・草」が一枚の紙に書かれていて、それをカテゴリングせよと課題を与えると西洋人は「にわとりと牛が仲間だ」と答え、東洋人は「牛と草が仲間だ」と答える。私はもちろん「牛と草」派だ。「にわとりと牛」と言われて一瞬「??」「あ、動物つながり!あ~、そう考えるか!」という感じである。
③西洋人は「個人」を重視するため、そのバックボーンとして「信念を正当化する原理」を追い求めた。だから、極力矛盾を避けようとする。東洋人は「調和」を重視するため、折衷的な解決や包括的な主張を好み、一見矛盾するふたつの議論を両方とも是認しようとする。だから、「相反する感情の同居」はない。喜んでいるか、悲しんでいるか、怒っているか、怯えているか、どれか「ひとつ」なのだ。これに対し、東洋人はその「同居」が起こり得る。「うれし泣き」「泣き笑い」は日本ではよくあることだが、西洋人にとっては理解できないという。「優勝したのになんで泣くの?」といった具合である。
さて、この本。結論がいささか単純すぎた・・・「どちらが良い悪いもない。われわれが目指すべきは両者の融合である」・・・いや、そりゃそれが出来ればいっちばん良いでしょうよ。個々人レベルで、文化レベルで、国家レベルで、違いを求めて融合させてゆくには、どんな方法があるのか、こんなに多くの実験レポートがあるならそこまでツッコんでほしいと切に思った。「あの人とこの人、性格が正反対。足して二で割れば良いのに」と言っているのと同じ。それが出来ない中で、上手に二人を生かしていくにはどうするか、読者としてはそこのところのヒントが欲しかったな。。