若者は欲しいものがたくさんあるけど、お金がない。高齢者はお金はたくさんあるけど、もう欲しいものはほとんどない(既に手に入れているから)。
その結果、高齢者の数が増えれば増えるほど、消費が振るわなくなるのは当たり前のことです。高齢者の蓄財は将来の不安への備えであって「モノ」に対してではありません。
政府が4月28日発表した経済統計からは、そんな実態が色濃く浮彫となりました。
消費者物価は0.2%上昇しましたが、これは原油高など、エネルギー価格の上昇の影響が大きく、エネルギーを除くベースではマイナスに転じました。
また、1世帯(2人以上世帯)の月単位の消費支出は29万7,942円。
実質消費支出で1.3%減です。
つまり、為替変動やエネルギーの価格変動などの影響を除いてみれば、物価も下がり、消費も下がっていることになります。
モノが売れないから企業はモノの価格を下げざるを得ないという状況に陥っていることがわかります。大胆な金融緩和を開始した頃の日銀、黒田総裁の自信はどこへ行ってしまったのでしょうか。
消費に水を差しているのは、税や社会保障の負担が増え、家計の節約志向が強いためだと言われています。年金保険料や健康保険料、介護保険料は少しずつ増え、高額療養費や介護医療費の自己負担額も増えています。
雇用は改善しており、3月の有効求人倍率は1.45倍。これはバブル期の1990年11月以来、約26年ぶりの高水準となっていますが、表の数字だけで単純に判断はできません。
最近の雇用における求人倍率の上昇は、人口の自然減少に伴う人手不足が原因です。また、倍率を引き上げている企業の求める人材は非正規雇用者です。
リクルートが調べた来春の大卒者の求人倍率は1.78倍でした。しかし、この数値を引き上げているのは従業員数300人未満の中小企業です。その求人倍率は6.4倍。
一方、従業員数5,000人以上の一流大企業の求人倍率はというと、0.39倍しかありません。希望者の3分の1強しか就職できません。非常に狭き門であることは変わりません。
官製春闘などと呼ばれ、毎年、大手企業の賃金アップが話題になりますが、中小企業勤務者の賃金は新聞でクローズアップされているような大企業ほど改善されていないのが実態です。
そして、近年は大学卒業生の約2分の1が、有利子の奨学金返済を負っています。
若者はお金がないから欲しいものが買えない→増加する高齢者は欲しいものが無いからものを買わない→モノが売れなくなるから企業は価格を下げる。
その結果、消費者物価も消費支出も下がることになります。










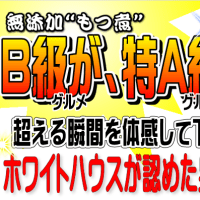
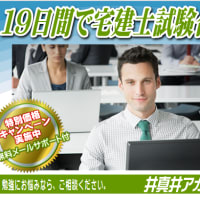
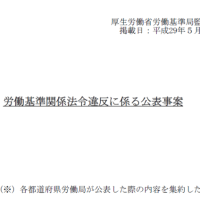





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます