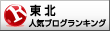本日はここ黒川で2月1日2日に行われる王祇祭で演じられる能の申し合わせでした。
黒川的に言うと、”され”といいます。たぶん「おさらい」のなまった形なのかとおもいます。
昨日からテンパリつづけ、今日の午前中もどっぷり練習(ひとり家の座敷で)
ホントは朝からすべての演目の申し合わせをしていて、普通は朝から参加するんですよね。
私は、自分の出る演目の前に参加し、それが終わったら保育園へ迎えと協調性がない参加となりました。
日々公民館でやっている練習にはたったの1回のみの参加。それでうまくできるはずはありません。
この申し合わせで全体的な流れや謡い方、動きを確認し、残りの1週間で調整修正し本番に向かうのことが
実は近年のパターンとなってました。
そのおかげで、師匠や回りの方には随分迷惑をおかけしております。

今年の黒川の下座の演目は
高砂、知章、杜若、小鍛冶、弓八幡、岩船だったかと思います
写真は、杜若の申し合わせ風景となります。
ちょうど、前シテが帰っていくところです。
このあと、座長によって謡がなってない


と、大激怒されました。私以外の方も謡いこみ不足のようです。
といっている私は、今日はじめてこの演目の本を開き、初めて謡いましたので、
稽古不足以前の問題です。

これは、小鍛冶の後シテです。この演目は、刀鍛冶の宗近と後シテが刀を打つ話です。
動きがあってやってるほうも楽しいですね。
動きがある能は、謡のノリ もよく、聞いてるほうも楽しいと思います。
もよく、聞いてるほうも楽しいと思います。
ただ、能の謡を聞きなれている方でないと何をいってるのか聞き取れないかもしれませんが。。。
しかも訛ってるし。
能には、5流があるんですが、黒川能はそれのドレにも属さないんですよ。
5流の方からも、黒川流といわれるぐらいなんです。
長い歴史の中で、黒川独自に変化しながら伝承されてきたからではないかと思います。
さて、私はいったい何に出るのでしょう?
正解は、
2月1日の下座当屋 大滝喜左衛門で。