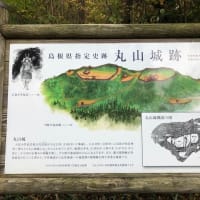63.戦国の石見−6(続き−3)
福屋を滅亡させた毛利元就にとって、今最大気にかかる存在は山吹城に居る本城常光であった。
元就は本城常光を味方に引き入れようとしていたが、武力で攻めても簡単ではないと考えた元就は、懐柔策にでるのである。
本城常光(陰徳太平記では本庄常光と記述)
本城氏は、安芸・石見の国人高橋氏の一門である。
高橋久光の時、出羽の本城に移居し本城と称した。
<高橋氏系 石見誌より>

常光は武勇に優れており、忍原崩れ、降露坂などの戦いなどで、毛利を撃退していた。
尼子晴久はその武勇を見込み、当時、高櫓城(出雲市佐田町)の城主であった本城常光を銀山の防衛拠点である山吹城代に任じた。
63.6.本城常光(別名:経光)、毛利に寝返りする
<注釈>
この本城常光の寝返りに関する物語を「陰徳太平記」から見ていくが、次の事を先ず言っておく。
この頃の陰徳太平記に記述されている時期は、史実とされる時期より2年遅れている。
つまり、本城常光が毛利に寝返ったのは永禄5年(1562年)であるが、陰徳太平記では永禄3年の事として扱っている。
そのため、永禄3年に死んだとされる尼子晴久が、本城常光の裏切りに激怒する記述が陰徳太平記にある(第34巻 晴久被搦宍道左馬助事)。
これは、尼子晴久の後を継いだ、尼子義久の間違いだと思う。
陰徳太平記は約150年後の享保2年(1717年)に出版されたものであり年代の混同や思い違いがあったのかもしれない。
63.6.1.毛利の懐柔策
福屋を滅亡させた毛利元就にとって、今最大気にかかる存在は山吹城に居る本城常光であった。
元就は本城常光を味方に引き入れようとしていたが、武力で攻めても簡単ではないと考えた元就は、懐柔策にでた。
この頃、吉川元春は、祖式の城に居て、山吹城の本城常光を牽制していた。
元就は元春に使いをだして「本庄常光は勇は世に傑出すと雖も、智は之に比するに懸隔なり。
殊に欲深き者なれば、所領多く与えんと謀りなば、終には味方に降るであろう」と伝えた。
元春は、常光の機嫌をとり味方に引きいれることを考えた。
そこで、本城常光の弟で、周防山口の法泉寺にいる「松かわ」という僧侶を仲介の使者にするために呼び寄せた。
元春は、僧松かわと対談し常光のことを褒め上げ、仲間になるように誘った。
本城常光の戦さぶりは大したもので、中国路で彼に勝る勇者は見当たらない。
味方の犠牲をかまわず押しこめば落城させることができるかもしれないが、乱世にこのような勇将を殺してしまうことは惜しいことである。
本城のような勇将と手を組んで中国統一の悲願を達成したい。
そして、松かわは間もなく山吹城を訪ね、元就や元春の言葉を伝えた。
常光は、「名将に褒められ、敵とはいえうれしい」と語ったという。
その後、邑智郡川本で元春の部将、粟屋元俊、山県康政と常光の家老服部若狭守、井戸二郎左衛門、椿雅樂助とが会見した。
そこで、毛利側は常光が毛利方になれば、石州の銀山に雲州の原手郡を与えると言って投降を誘った。
常光は一族を集めて如何にすべきかと詮議した。
皆は同じように言った。
今、毛利家と尼子両家の勢いを比較すると、智も勇も雲壌懸絶である。
尼子は既に備後一国、石州半国を毛利家へ切りとられ、戦力は年々衰えており、一方毛利家は威光月々に強盛と成っている。
そして尼子とて相伝の主人にもあらず、また毛利家とて従来の仇にもあらず、唯弓矢の盛衰に依り、何処に属するか決まるものである。
大将の賢否を考えて向背することは武士の習いである。
なのに、こちらから冑を脱いでさへ降参すべきなのに、幸いに元就より厚意あるある申し出があったいまこそ渡りに舟を得たるが如くである。
本城常光は出雲国での知行給与を条件に毛利氏に降りた。
永禄5年(1562年)6月のことであった。
63.6.2.常光、嫡男太郎兵衛を取り返す
だがこの頃本城 常光は、嫡男太郎兵衛を人質として尼子氏に差し出しており、太郎兵衛は尼子氏の本拠地である出雲国月山富田城に住んでいた。
尼子の敵方である毛利の配下になることは、尼子に対する裏切りである。
そうすると、遅かれ早かれ太郎兵衛の命はないものとなる。
そこで、常光は裏切りを知られる前に、この嫡男を取り返そうと謀を巡らせた。
常光は密かに太郎兵衛に連絡し、脱出する計画を伝えた。
数日後、三十頭ほどの馬をひいた青山某という博労(牛や馬の仲買商人)が、「九州からやってきました」という触れ込みで月山城にやってきた。
そして、青山は馬は数百匹おり、それらは分かれて向かって来ており、数日後にはもっと数多く集まる、と言った。
青山博労は常光の腹心の家来であった。
月山城の八幡の馬場にずらりと並んだ 馬の見物に出た太郎兵衛は、示し合わせたとおり、青山と押し問答を始めた。
太郎兵衛は父、常光が秘蔵 していた”名月"を指さし「これに乗ってみたい」と頼むふりをした。
「これはいけません、疳の強い馬で、もしこれに乗られお怪我があってはいけません」
「何を失敬な、馬と名のつくものなら、鬼だろうが、 蛇であろうが乗りこなすわい」
押しとどめる博労の手を振り払って、太郎兵衛はヒラリと馬にまたがった。
馬場を二、三回まわったかと思うと、手綱に手心を加えたから、馬は急に走り出した。
さっと手綱を引くと馬場を駆け抜け、 柵を飛んで馬も 人も忽ちのうちに黒い点となって姿が見えなくなっ た。
馬場に出ていた武士たちは、
「広言をはいていたが、太郎兵衛のやつは馬に誘拐されたわい、いまごろはどっかで振り落とされているだろ う」
と嘲った。
顔色を変えた青山は一散に走って太郎兵衛の後を追った。
太郎兵衛は途中の要所要所の川水に、足を冷やしてつないであった馬に乗り替えなが 山吹城をひたむきにめざし、三日かかる道のりを、たった半日で山吹城へ走りこんだ、という。
<月山富田城模型>

63.6.3.尼子晴久の怒り
太郎兵衛の帰城と共に、本城常光は尼子に対して、はっきりと反旗を翻した。
尼子晴久が太郎兵衛の逃亡を聞くと、本城常光の裏切りをはっきり悟ると、怒りが湧いてきた。
晴久は怒髪衝天という勢いで富田城の大広間を歩き回って喚いた。
本城は豪勇な武士なれば二心など抱くことはないと思い、さらに本城を惹きつけておくために種々の重宝珍器など与え、領地も倍してやった。
さらに、儂が最も好きだった”目黒の娘”を嫁がせたのは、本城が我が婿なりと示すためだったのだ。
その目黒の娘は容色間雅(態度がしとやかでみやびやかなこと)端正(行儀や姿などが整っていて立派なこと)なるのみか心様賢々しき者だった。
と、目黒の娘を褒め、懐かしんだ。
そして、其の昔の目黒の娘に関する逸話を話しだした。
宍道左馬助という者が晴久への恨みがあり、刺し違えようと、夜中に家に入ってきた。
そこで、格闘となり、晴久は宍道左馬助を押さえつけて、何か縛るものを持って来いと、周りのものに言った。
しかし、宿直していたのは全て女性であり、慌て騒ぎ立てるだけだった。
その時、目黒が娘は、小鼓の調子の緒を解いて、晴久に手渡した。
そのため宍道を搦め縛ることができた。
このような賢しき女を、儂は殊に寵愛しており、名残も惜しかったが、常光が心を掴むために、嫁に与えてしまった。
また、奴も武力に抽んでており、戦功を励んでいたため、深く信頼して、最前線の山吹城を守らさせたのだ。
それなのに、この儂を裏切るとは、なんと腹立たしいことよ、と高声に喚きまわった。
<尼子晴久>

63.6.4.毛利の勢力拡大
毛利元就は、本城常光を味方につけてから、石見の殆どを傘下にしていった。
その勢いは「龍の水を得、虎の山に靠(より)たるが如く」と噂された。
毛利は本城常光父子を先鋒として雲州へ攻めようとしていた。
すると、この噂を聞いて、敵わないと思った、三澤三郎左衛門為清、三刀屋弾正左衛門久扶、赤穴右京亮幸清等が我先にと使者を出し、人質を送って各々降旗を建てて崇敬の念を表わした、と云う。
このような中、元就父子四人(隆元、元春、隆景)は永禄5年(1562年)年10月上旬に雲州赤穴に着陣した。
そうすると出雲国の武士は、我も我もと軍門に参加しに来て、その勢は既に二万を越えていた。
63.6.5.陰徳太平記 第34巻 晴久被搦宍道左馬助事
太郎兵衛方便て落ちたり、常光敵に与しすと聞こえしかば、晴久大いに驚き給う。
常光敵に下りなば、石州の味方共かた落し気後れ、或いは敵に降り、又は攻め滅ぼされなん事の無念さよ。
本城はさる勇士なれば二心あらじと深く頼み思、予(われ)彼が心を執らん為に種々の重宝珍器など与え、采地おも本領に倍して遣わしぬ。
その上殊恩也しは、予(われ)目黒が娘を妾にせし遣わして、我が婿なりと名付けたり。
彼の目黒が娘は容色間雅端正なるのみか心様賢々しき者也。
その昔宍道左馬助(尼子氏の一族)我を恨むる事有って、刺し違えんとと思い、唯一人、ある宵の間に、我が燕居(家にくつろいでいること)の座敷へ来りけるを、当番の面々も、彼我と従兄弟共なれば、常に睦ましきに習いて、咎むる者もなかりし故、思う図に忍び入隠れ居て、我前後不覚に寝ぬべき夜半に外より戸を押し破らんとす。
予其の夜は更に寝られずして居たれば、かっぱと起き上がり、戸押し破られじと押さえたり。
宍道は聞こゆる大力なれば、己が腕に任せて押すほどに、叶いがたかりける故、余して倒れん所を取って縛すべきと思い、一張はつて余しければ、案のごとく宍道戸板の上に乗って俯せに倒れたり。
得たりと取って押さえたりければ、宍道相撲て上を下へと組合うたり。
予も壮年頃は微力にも無かりし故、終に上になり、縛るべきもの得させよと云いたりけれど、宿直した者、皆女計り也ければ、慌てて騒ぎたるのみにて、縄を取り合いせくるる者なし。
其の中に目黒が娘、小鼓の調子の緒を解いてくれたりしを以て、搦め縛り、其の夜頭を刎ねたりき。
かかる賢しき女なれば、我殊に寵愛せし程に、名残も惜しかりつれ共、常光が心を獲るべきために与え嫁せしめたり。
さる故彼も他に抽んでて戦功を励ましかば、深く依頼にして、山吹の城に入れ置き、敵の境目の城を守らせたりし所に、反心を抱きけることの腹立たしさよ、と高声に叱り躍り上がり躍り上がりせらけるも理也とぞ聞こえし。
<続く>