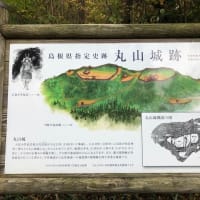30.3.元弘の乱
30.3.11. 後醍醐帝隠岐脱出
幕府軍が千早城に大軍を貼り付けにしながら落とせずにいる、との報は全国に伝わり、各地の倒幕の機運を触発することとなった。
正慶2年/元弘3年(1333年)1月21日、後醍醐天皇の皇子・護良親王の令旨を受けて、播磨国の赤松則村(円心)が挙兵した。
また伊予でも閏2月4日、土居二郎、得能弥三郎らが蜂起した。
こういう情報は出雲の鰐淵寺の頼源などから後醍醐帝にもたらされていた。
そして、隠岐脱出の手筈も整えられていく。
後醍醐帝が隠岐から脱出する前後の様子を「太平記」、「私本太平記」、「隠岐国 口承伝説」から見ていく。
30.3.11.1. 太平記
後醍醐帝が隠岐から脱出する前後の様子を「太平記」では、次のように述べている。
閏二月下旬は、佐々木富士名判官義綱の当番で、中門の警護に当たっていた。
佐々木富士名義綱は宮方に心変わりしていた。
義綱は、官女を通じて後醍醐帝に
①楠木正成が金剛山に城を構えて立て籠って奮戦している。
②備前では、伊東大和二郎が三石という所に城を構えて山陽道を塞いでいる。
③播磨では赤松入道円心が大塔宮の令旨をいただいて摂津国まで攻め上り、兵庫の摩耶と申すところに陣を取っている。
④四国では河野の一族で土居二郎と得能弥三郎がお味方に参じて挙兵し、四国勢は全て土居と得能に従うようになった。
ことを伝えた。
そして、隠岐脱出を進言する。
「義綱が警固の当番の間に忍んで出て、千波(ちぶり)の湊より船に乗りになり、出雲か伯耆のどこの港にでも着いてしかるべき武士を頼りに、しばらく待って頂きたい。
私が恐れながら追いかけ申し上げるために出かける振りをして、そのままお味方に参上いたしましょう」
と申し上げた。
すると、後醍醐帝は義綱に「出雲に渡り、協力するであろう一族を味方に付けて迎えに参れ」と言った。
義綱はすぐに出雲国に渡って、出雲の守護塩冶判官高貞に話を掛けた。
しかし、義綱は高貞に幽閉されたため、隠岐に戻ることができなくなった。
後醍醐帝はしばらく義綱を待った。
しかし、機を逃すまいと考えたのか、運を天に任せて島を出る決心をする。
ある夜の闇に紛れて三位の局殿の出産が近づいたからと、六条少将忠顕朝臣だけを連れて、ひそかに御在所を出た。
後醍醐帝も草鞋を履いて歩いて行った。
夜が大変更けて、忠顕朝臣が一軒の家の門を叩くと、男が出てきた。
「千波(ちぶり)の湊へはどう行くのか」と忠顕朝臣が尋ねると、
「千波(ちぶり)の湊へは、ここからわずかに50町(約5Km)であるが、きっと迷うことになるだろうと思うので、案内申しよう」と言って、後醍醐帝を軽々と背負い千波の湊に着いた。
ここで時を知らせる鼓の音を聞くと、夜はまだ三時過ぎである。
この道案内をした男はかいがいしく港の中を走りまわって、伯耆国へ戻る商人の船を見つけて、帝を屋形の中に入れ、別れのご挨拶をした。
島根懸史
「島根懸史」では、この後醍醐帝の隠岐脱出について、次のように説明している。
懸史の編者が往年東郷村役場で調査した処によれば「千波」は東郷村の東南方外海に面する海岸の一小港にして今「チエバ」と称する。

30.3.11.2. 私本太平記
吉川英治著の「私本太平記」八荒帖 一穂の灯 の項で、正慶2年/元弘3年(1333年)正月、後醍醐帝が国分寺から島前美田郷別府(黒木御所)に行宮遷しがあった、としている。
以下その辺りを要約して以下に記述する。
私本太平記から(その1)一穂の灯
国分寺を行在所としていた時は、隠岐の守護代である佐々木清高が監視していた。
それを、島前の地頭である能登ノ介清秋(佐々木清高の叔父)の監視に移した。
これは、幕府の命によるものである。
地方では、反幕府勢力による蜂起が色々な所で起こっていた。
北条高時は後醍醐帝が隠岐で自由に振る舞っており、鰐淵寺の頼源や、土着の武士と合っていることを、内報を受け知っていた。
北条高時は、このままでは後醍醐帝を擁して再び大反乱が起こることを心配した。
そこで、高時は後醍醐帝をもっと厳しく見張り、時によっては亡き者にしてもよいと考えた。
高時はその指示を佐々木清高にだす。
佐々木清高は、島後の国分寺では人の往来も多く、外部との接触を完全に断つのは難しいと考え、もっと孤立した警固しやすい場所に後醍醐帝を移すことにした。
そこで、人目のすくない島前美田郷別府に移し、いざという時に備えたということである。
また、国分寺の警固の武士は本土からも大勢きていたが、其の武士たちをそれぞれの国に帰国させ、宮方の武士をことごとく島外においやったのである。
その宮方の武士の中に成田小三郎、名和悪四郎、富士名義綱など、日ごろからたれにもそれと分っていた宮方色の警士十幾人の名がほとんど洩れなくあげられていた。
その中の富士名義綱は、出雲簸川城の塩冶高貞に、後醍醐帝の隠岐脱出を援助するように説得しに行くから、と密かに伝えていた。
また、後醍醐帝は四国阿波の海賊岩松の使者に会い綸旨を授けた。
それから数日後に後醍醐帝は、島前美田郷別府に移動させられた。
というように、後醍醐帝は宮方の勢力との接触を断つこと、そしていざとなったら帝を亡き者にするために、国分寺から人けの少ない島前美田郷別府(黒木御所)に遷されたのである。
後醍醐帝は、この年の閏2月24日に隠岐の島を脱出する。
ということは、ここ黒木御所で過ごしたのはおよそ1ヶ月間くらいであろう。
吉川英治がどんな根拠でこのような話を展開したのかは不明であるが、隠岐の地元に伝わる口承を参考にして物語を作り上げたのかもしれない。
あるいは、国分寺説と黒木御所説があるなら、両方とも正しいことにして小説を書いたのかもしれない。
黒木御所に移った後醍醐帝は、隠岐脱出の意思を固める。
<続く>