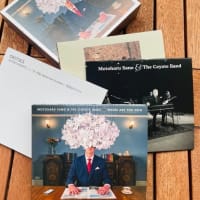それは、「縄文時代」、「弥生時代」っていう名称をつけたことです。
 たとえば縄文時代は、「新石器時代」や「貝塚時代」でも、なんの問題もないわけですが、明治の先人たちが「縄文時代」を選択してくれたおかげで、「縄文」って文字をみるだけで、あの縄文土器のレリジアスな縄目の文様や形容が、いきいきとうかんできます。
たとえば縄文時代は、「新石器時代」や「貝塚時代」でも、なんの問題もないわけですが、明治の先人たちが「縄文時代」を選択してくれたおかげで、「縄文」って文字をみるだけで、あの縄文土器のレリジアスな縄目の文様や形容が、いきいきとうかんできます。「縄文」っていう名前を発明した?のは、アメリカの動物学者モース( Edward Sylvester Morse )で、1877年(明治10)6月、腕足類研究のために来日し、横浜から東京(新橋)にむかう途中の大森村で、汽車の窓から、貝塚とおぼしきもの(大森貝塚)を偶然発見しました。
モースは調査の成果を『 Shell Mounds of Omori 』にまとめて刊行し、その報告書なのかで、この貝塚から出土した土器を「 cord marked pottery 」と表記したことが、「縄文時代」っていう風韻のいい名前を生むきっかけになったそうです。
ながくなったので、「弥生時代」っていう名称については、また明日。