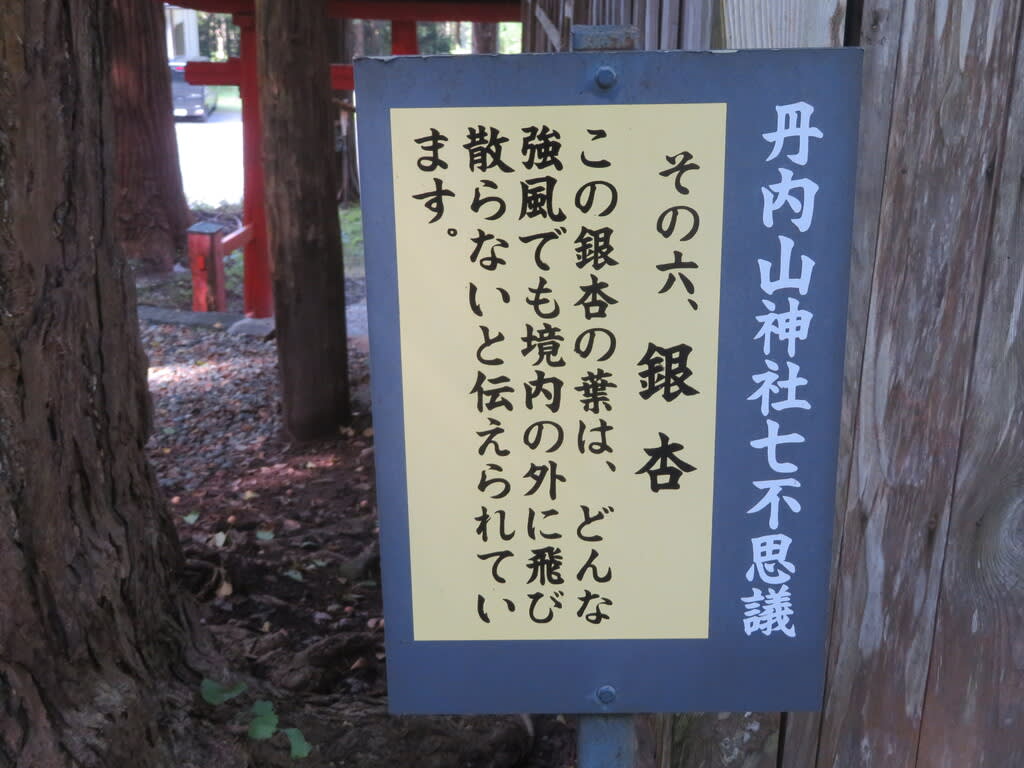弁理士近藤充紀のちまちま中間手続44
拒絶理由 進歩性
引用文献2には、角膜上皮細胞に suramin 感受性のP2受容体が多く存在すること、当該受容体を介してATP誘起のカルシウム流入が活性化されて角膜上皮細胞の増殖が促進されることが記載されている。そして、引用文献3の要約等に記載されているとおり、suramin感受性のP2受容体とは、P2Y受容体を意味するものである。
そうしてみると、引用文献2,4-6等に記載の、角膜損傷状態において、角膜上皮細胞を増殖させて当該状態を緩解するために、引用文献4-6等に記載されるP2Y受容体アゴニストを用いるものとし、その角膜上皮伸展促進効果を確認して、本願の請求項1-3に係る発明とすることは、当業者の容易になし得るものと認められる。
なお、発明の詳細な説明中の記載を検討しても、本願の請求項1-3に係る発明は、引用文献2-6に記載された事項から予測しえない顕著な効果を奏するものとみとめることはできない。
意見書
拒絶理由通知には、「引用文献2には、角膜「上皮」細胞にsuramin感受性のP2受容体が多く存在すること、・・・(中略)・・・角膜「上皮」細胞の増殖が促進されることが記載されている」と指摘されており、この指摘内容に基づいて本願発明の進歩性が否定されている。
しかしながら、この指摘によって本願発明の進歩性を否定することは誤りである。なぜならば、引用文献2は、角膜「内皮」細胞(corneal endothelial cell)の増殖を記載しているだけであり、本願発明に関する、角膜「上皮」細胞(corneal epithelial cell)への作用効果については一切記載も示唆もしていないからである。
また、引用文献2で記載されている作用効果は細胞の「増殖」促進であり、細胞の「伸展」促進ではない。細胞の「増殖」とは細胞が分裂して細胞数が増加することであり、細胞の「伸展」とは角膜上皮において細胞が接着・伸長することであり、これらは、明らかに異なる作用効果である。
さらに、角膜上皮の修復(創傷治癒)において、増殖と伸展は異なる意義を有している。すなわち、角膜上皮の創傷治癒は、受傷後、まず欠損部周辺の上皮細胞が伸展・移動して一層の細胞で欠損部を被覆し、続いて、上皮細胞(上皮基底細胞)の分裂が始まり、分裂増殖した細胞が分化して欠損部に供給されることにより欠損部が再生・回復する。このように、角膜上皮の創傷治癒は、(1)上皮細胞の伸展・移動、(2)上皮細胞の増殖、(3)上皮細胞の分化の3相からなり、角膜上皮の伸展と増殖は異なる意義を有するものである。
したがって、本願発明は、引用文献2の記載から決して容易に想到することができないものである。
引用文献3~6には、P2Y受容体アゴニストとしてATPやUTP等が記載されている。しかし、引用文献3~6には、P2Y受容体アゴニストの角膜上皮伸展促進作用については一切記載も示唆もなされていない。
以上より、本願発明は、引用文献2~6の記載に基づいても、当業者が容易になし得る ものであるとはいえないものである。
特許査定
意見書の主要部分は、出願人作成のものであるので、こちらとしては、エラーになるようなことをしないように、、ということに終始した。
そもそもとして、
引用文献2は、事実を記載しているのみであって、発明ではない。引用文献3も同様。備考欄にも・・「請求項1~3の発明とする」とあり、「発明に基づいて」ではないので、進歩性の拒絶理由として成立するのか?