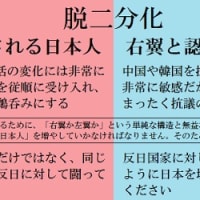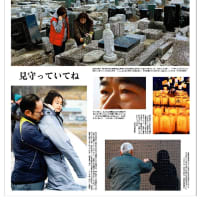▼http://www.nrbj.info/?p=902

だから、あすのことを思いわずらうな。
あすのことは、あす自身が
思いわずらうであろう。一日の苦労は、
その日一日だけで十分である。
「マタイによる福音書」 6章34節
新約聖書 口語訳
ほんとうに愛したいと願うなら
人をゆるすことを知らなければなりません。
マザーテレサ
(マザーテレサ『愛のことば』より)
★ロシアの名前の知られざる事実
◆ロシアNOW 2014年10月9日 タラス・レピン
http://jp.rbth.com/arts/2014/10/09/50553.html
いつから人に名前をつけるようになったのか。
昔の名前はどのようなものだったのか。
ロシアの名前の歴史を探る。
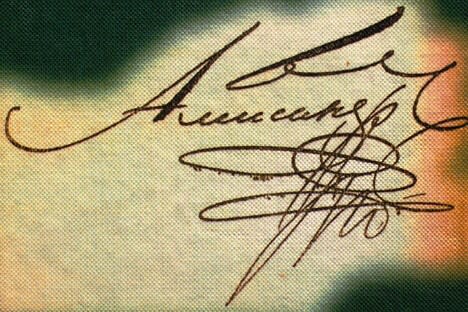
写真提供:ロシア7
▼初期の名前
名前をつけるという伝統がルーシで始まったのは、キリスト教以前の時代。習慣、外見、環境に関連するあらゆる言葉が名前になった。
ペルヴイ(第1)、フトラク(第2)、トレチャク(第3)などの生まれた順番、チェルニャワ(浅黒)、ベリャク(色白)、マリュタ(背が低い)などの外見、モルチャン(寡黙)、スメヤナ(笑い上戸)、イストマ(倦怠)などの性格や特徴が名前になったりしていた。
他には自然からブィク(オウシ)、シチュカ(カワカマス)、ドゥブ(オーク)、手工業からロシュカ(スプーン)、クズネツ(鍛冶屋)、シュバ(毛皮)など。年齢とともに、より適切な名前に変わることもあった。
悪魔や他の人から悪影響をおよぼされることのないようにと、ネクラス(見てくれの悪い)やズロバ(意地悪)など、事実や架空の欠点を名前にすることも多かった。このような名前をつけると、邪視や堕落から守られると信じられていた。
ルーシでキリスト教の名前がつけられるようになった後でも、偉大なる将軍アレクサンドル・ネフスキー、啓蒙家で詩人のシメオン・ポロツキー、モスクワ大公イヴァン1世などを含め、階級の高低にかかわらず、異なる社会で追加的な名前として通称が残った。ピョートル大帝(在位17世紀末~)によって禁止されるまで、通称は使われていた。だが15世紀からすでに、通称は姓に変わっていた。
▼2つの名前
14世紀から16世紀まで、新生児が誕生すると、その日の聖人にちなんだ直接名がつけられるようになった。公のキリスト教の名前とは異なり、直接名は親族の間でしか使われなかった。皇帝ヴァシリー3世の直接名はガヴリイル、その息子のイヴァン雷帝はチト。時に兄弟の2つの名前が同じになってしまうこともあった。イヴァン雷帝の息子2人の公の名前はドミトリー、直接名はウラムだった。
直接名の伝統の発祥はリューリク家。この時代の大公は異教の名前とキリスト教の名前を持っていた。ヤロスラフ・ゲオルギー(ムドルイ)やウラジーミル・ヴァシリー(モノマフ)など(前者が異教の名前で、後者がキリスト教の名前)。
▼リューリク朝の名前
リューリク朝の名前には2つのカテゴリーがあった。ヤロポルク、スヴャトスラフなどの2つの語幹からなるスラヴ名と、オリガ、グレブ、イーゴリなどのスカンジナビア名。これらは高位者の名前であったが、14世紀からは一般的に使われるようになった。祖父が死亡すると、新生児の孫にその名前をつけることができたが、生存中の兄弟が同じ名前を持つことは許されていなかった。
▼キリスト教の名前
ルーシではキリスト教の強化とともに、スラヴ名が過去のものとなっていき、ヤリロやラダといった異教に関連する名前など、禁止名一覧もつくられた。キリスト教名の普及により、リューリク家の人々の名前も徐々に変化。キリスト教の洗礼の際にウラジーミル1世にはヴァシリー、キエフ大公妃のオリガにはエレーナという名前が与えられた。
▼ロマノフ朝の名前
ロマノフ家の名前が変化したのはエカチェリーナ2世の時代。孫をニコライ(奇蹟者聖ニコライから)、コンスタンチン(亜使徒聖大帝コンスタンティンから)、アレクサンドル(聖アレクサンドル・ネフスキーから)と名付けた。ロマノフ家の子孫が増えると、ニキータ、オリガなどの昔の名前や、ロスチスラフといったスラヴ名もあらわれた。
ロマノフ家では先祖の名前がつけられ、また先祖の習慣に従っていた。そのため、ニコライ、アレクサンドル、ピョートルが多い。ただし、ピョートル3世(1728~1762)、その息子のパーヴェル1世(1754~1801)が殺害されてから、ロマノフ家ではピョートルとパーヴェルが禁止された。
▼君もイヴァン、僕もイヴァン
イヴァン(イワン)という名前は広く普及。ロシア帝国では農民の4人に1人がイヴァンだった。浮浪者は警察につかまると、自分のことをイヴァンと名乗っていたため、「親族を覚えていないイヴァン」という表現まで生まれた。
古代ヘブライ名のイヴァンはほとんど普及していなかったが、イヴァン1世以降、リューリク家では4人がイヴァンと名付けられた。そしてロマノフ家でも使われていたが、1764年にイヴァン6世が非業の死を遂げた後、禁止された。
▼父称
ルーシでは父称が出生名の一部として使われていた。これはその人と父とのつながりの証明であった。貴族も普通の人も、「ミハイル、ペトロフ・スィン」(ピョートルの息子のミハイル)と自分を名乗っていた。
語末が「イチ」の父称は特権であり、高位者だけが所有していた。スヴャトポルク・イジャスラヴィチなどのようにリューリク家でも使われていた。
19世紀からは、新しいインテリゲンツィヤが父称を使うようになった。1861年に農奴制が廃止されると、農民の父称の使用も許されるようになった。
現代ロシア人の生活に父称は欠かせない。これは相手に対する尊敬の念を込めた呼び方であり、同じ名前と姓と持った人を区別するためにも必要だ。
(ロシアNOW 2014年10月9日)

▲http://daikonpapa.cocolog-nifty.com/daikonpapa/2013/04/post-11e8.html
★島根県代表団
モスクワの女子修道院に牡丹の木 贈呈
◆The Voice of Russia 2014年9月16日 04:55
http://japanese.ruvr.ru/news/2014_09_16/277335029/

▲Photo: RIA Novosti
モスクワ中心部にあるマルフォ・ マリインスキイ女子修道院に、日本のシンボルがお目見えする。リア-ノーヴォスチ通信がロシア正教会宗務局報道部の情報として伝えた。
それによれば「16日、マルフォ・マリインスキイ女子修道院で祝賀セレモニーが執り行われ、その中で、島根県代表団が友好のしるしに、モスクワ総主教管区に日本のシンボルの一つ、ユニークな牡丹の木を贈る。」
正教会報道部はまた「植樹式は、2007年に極東でスタートした『花咲く日ロの道』プロジェクトの枠内で行われる。これまですでに、ウラジオストーク、ハバロフスク、サンクトペテルブルグに、牡丹を含め、美しい花を咲かせる日本産の様々な木々が植えられてきた」と指摘した。
マルフォ・マリインスキイ女子修道院は、1909年、モスクワ大公セルゲイの妻、エリザヴェータ・フォードロヴナ(ニコライ2世の妻アレクサンドラの姉、ボリシェヴィキによりウラルで惨殺された)によって設立された。革命後閉鎖され、ソ連時代はイコン修復所などとなったが、1990年から修道院を甦らせる作業が始まった。
現在、修道院には25人のシスターがおり、敷地内に障害児のリハビリ施設を設けたり、重度の遺伝病患者の支援に取り組むなど、エリザヴェータ・フョードロヴナの志を継ぎ、幅広い慈善プログラムを展開している。
又修道院では、援助を必要とする人々を常に受け入れており、食糧品・医薬品支給のほか、生活及び人生相談に応じている。
なお敷地内に建つ、美しいポクロフスキイ聖堂は、建築家シューセフの傑作の一つである。
リア-ノーヴォスチ
(The Voice of Russia 2014年9月16日)
★モスクワで第19回「日本の秋」
◆The Voice of Russia 2014年9月17日 02:16

▲Photo: RIA Novosti
モスクワで恒例の「日本の秋」フェスティバルが始まった。日本の伝統音楽のコンサートや各種の展示、レクチャーその他イベントが行われる。
イタル・タス通信は在ロシア日本大使館のクサカベ・ヨウスケさんに特別インタヴューを行った。「モスクワにおける「日本の秋」祭は日本大使館が95年に始めたもの。多くのロシア人、モスクワ市民に愛されている。今年もイベントが盛り沢山だ。現代日本文化を紹介するJ-FESTや、日本映画
祭、また日本の舞台芸術を代表するものとしてアンサンブル「京都創生座」および劇団「チェルフィッシュ」の公演が行われる。また、今年は日露武道交流年ということで、11月には日本武道館の代表が武術のデモンストレーションを行う。モスクワ以外でも、たとえば各地で映画祭や、サンクトペテルブルグの「折り紙の味」展など、様々なイベントが行われる」
日本文化を知るのに欠かせない日本語そのものの学習熱もロシアでは高まりを見せている。クサカベさんによれば、1990年に550人だったロシアにおける日本語学習者は、2012年には1万1400人にまで増えている。
イタル・タス
(The Voice of Russia 2014年9月17日 )

★牡丹なら「松江産」
吉村慎司, 「ロシアNOW」への特別寄稿
■ロシアNOW 2012年12月12日
生産量上回る注文
ロシアの花市場に、日本産の牡丹(ぼたん)が広がり始めた。山陰の古都・島根県松江市から苗木の試験輸出が始まって4年目。最初の年に200本だった出荷量は順調に増え、今年は過去最高の1500本に達した。
「マツエの牡丹は今年はいつ買えるの」。この夏、ウラジオストクやハバロフスクの花屋に、一般客からのこんな問い合わせが相次いだ。
松江の牡丹輸出の仕組みはこうだ。生産者団体のJAくにびきが、松江に隣接する鳥取県の境港から、ウラジオストク行きの定期フェリーに乗せて苗木を出荷。パートナーであるウラジオストクの花業者が受け取り、極東地域に流通させる。
苗木を運び込むだけではない。松江市や島根県、日本貿易振興機構(ジェトロ)なども協力して、ウラジオストク、ハバロフスクの2都市で毎秋PRイベントを開いて知名度アップに努めてきた。
今年は9月下旬から10月中旬にかけて、一般消費者向けの展示即売会を3回開催。どの回も大入りで、数百本の苗木が即日完売となった。特に、「松江ブランド展」として催したイベントにはウラジオストク市内の会場に2000人が詰めかける盛況ぶりだった。
なぜ人気が出ているのか。理由は、少なくとも価格ではなさそうだ。今年の苗木の販売価格は1本1100ルーブル(約2800円)で、日本での相場の約3倍だ。輸送などの経費がかかるためで、安価な中国産の牡丹と比べれば5~10倍の開きがある。
JAくにびき特産課の佐川真二係長は、好調の理由をこう説明する。「ロシア市場の牡丹は、花が下向きに咲く中国産が主流。この中で、上を向いて花開く松江の牡丹は美しさで競争力があります。また、中国産に比べて枯れにくいとの評価もいただくようになりました」。実際、リピート客が目立つという。前年試しに買ってみた牡丹が予想以上にきれいに咲き、別の色・種類を集めたくなった客も多いようだ。
実は今年、ロシアから2000本近い注文が来ていた。生産量が追いつかないため1500本に抑えざるを得なかったという。
JAくにびきは今、ロシア市場向けの牡丹栽培を始めることを計画中だ。来春にもウラジオストクからパートナー業者を招いて、品種や量の詳細を詰める。
牡丹はこれまで極東に限った展開だったが、2013年にはサンクトペテルブルクなどヨーロッパ側の大都市での販売も実現しそうだ。JAの佐川係長は、「ロシアは花を好む国民性もあり、我々にとって有望な市場。まずは年間出荷量を早期に1万本レベルに引き上げたい」と意気込みを語っている。
(http://m.jp.rbth.com/articles/2012/12/12/40375.html)
(ロシアNOW 2012年12月12日)

だから、あすのことを思いわずらうな。
あすのことは、あす自身が
思いわずらうであろう。一日の苦労は、
その日一日だけで十分である。
「マタイによる福音書」 6章34節
新約聖書 口語訳
ほんとうに愛したいと願うなら
人をゆるすことを知らなければなりません。
マザーテレサ
(マザーテレサ『愛のことば』より)
★ロシアの名前の知られざる事実
◆ロシアNOW 2014年10月9日 タラス・レピン
http://jp.rbth.com/arts/2014/10/09/50553.html
いつから人に名前をつけるようになったのか。
昔の名前はどのようなものだったのか。
ロシアの名前の歴史を探る。
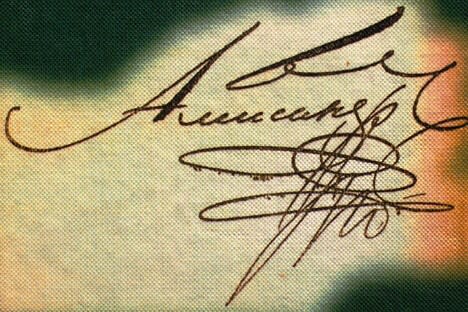
写真提供:ロシア7
▼初期の名前
名前をつけるという伝統がルーシで始まったのは、キリスト教以前の時代。習慣、外見、環境に関連するあらゆる言葉が名前になった。
ペルヴイ(第1)、フトラク(第2)、トレチャク(第3)などの生まれた順番、チェルニャワ(浅黒)、ベリャク(色白)、マリュタ(背が低い)などの外見、モルチャン(寡黙)、スメヤナ(笑い上戸)、イストマ(倦怠)などの性格や特徴が名前になったりしていた。
他には自然からブィク(オウシ)、シチュカ(カワカマス)、ドゥブ(オーク)、手工業からロシュカ(スプーン)、クズネツ(鍛冶屋)、シュバ(毛皮)など。年齢とともに、より適切な名前に変わることもあった。
悪魔や他の人から悪影響をおよぼされることのないようにと、ネクラス(見てくれの悪い)やズロバ(意地悪)など、事実や架空の欠点を名前にすることも多かった。このような名前をつけると、邪視や堕落から守られると信じられていた。
ルーシでキリスト教の名前がつけられるようになった後でも、偉大なる将軍アレクサンドル・ネフスキー、啓蒙家で詩人のシメオン・ポロツキー、モスクワ大公イヴァン1世などを含め、階級の高低にかかわらず、異なる社会で追加的な名前として通称が残った。ピョートル大帝(在位17世紀末~)によって禁止されるまで、通称は使われていた。だが15世紀からすでに、通称は姓に変わっていた。
▼2つの名前
14世紀から16世紀まで、新生児が誕生すると、その日の聖人にちなんだ直接名がつけられるようになった。公のキリスト教の名前とは異なり、直接名は親族の間でしか使われなかった。皇帝ヴァシリー3世の直接名はガヴリイル、その息子のイヴァン雷帝はチト。時に兄弟の2つの名前が同じになってしまうこともあった。イヴァン雷帝の息子2人の公の名前はドミトリー、直接名はウラムだった。
直接名の伝統の発祥はリューリク家。この時代の大公は異教の名前とキリスト教の名前を持っていた。ヤロスラフ・ゲオルギー(ムドルイ)やウラジーミル・ヴァシリー(モノマフ)など(前者が異教の名前で、後者がキリスト教の名前)。
▼リューリク朝の名前
リューリク朝の名前には2つのカテゴリーがあった。ヤロポルク、スヴャトスラフなどの2つの語幹からなるスラヴ名と、オリガ、グレブ、イーゴリなどのスカンジナビア名。これらは高位者の名前であったが、14世紀からは一般的に使われるようになった。祖父が死亡すると、新生児の孫にその名前をつけることができたが、生存中の兄弟が同じ名前を持つことは許されていなかった。
▼キリスト教の名前
ルーシではキリスト教の強化とともに、スラヴ名が過去のものとなっていき、ヤリロやラダといった異教に関連する名前など、禁止名一覧もつくられた。キリスト教名の普及により、リューリク家の人々の名前も徐々に変化。キリスト教の洗礼の際にウラジーミル1世にはヴァシリー、キエフ大公妃のオリガにはエレーナという名前が与えられた。
▼ロマノフ朝の名前
ロマノフ家の名前が変化したのはエカチェリーナ2世の時代。孫をニコライ(奇蹟者聖ニコライから)、コンスタンチン(亜使徒聖大帝コンスタンティンから)、アレクサンドル(聖アレクサンドル・ネフスキーから)と名付けた。ロマノフ家の子孫が増えると、ニキータ、オリガなどの昔の名前や、ロスチスラフといったスラヴ名もあらわれた。
ロマノフ家では先祖の名前がつけられ、また先祖の習慣に従っていた。そのため、ニコライ、アレクサンドル、ピョートルが多い。ただし、ピョートル3世(1728~1762)、その息子のパーヴェル1世(1754~1801)が殺害されてから、ロマノフ家ではピョートルとパーヴェルが禁止された。
▼君もイヴァン、僕もイヴァン
イヴァン(イワン)という名前は広く普及。ロシア帝国では農民の4人に1人がイヴァンだった。浮浪者は警察につかまると、自分のことをイヴァンと名乗っていたため、「親族を覚えていないイヴァン」という表現まで生まれた。
古代ヘブライ名のイヴァンはほとんど普及していなかったが、イヴァン1世以降、リューリク家では4人がイヴァンと名付けられた。そしてロマノフ家でも使われていたが、1764年にイヴァン6世が非業の死を遂げた後、禁止された。
▼父称
ルーシでは父称が出生名の一部として使われていた。これはその人と父とのつながりの証明であった。貴族も普通の人も、「ミハイル、ペトロフ・スィン」(ピョートルの息子のミハイル)と自分を名乗っていた。
語末が「イチ」の父称は特権であり、高位者だけが所有していた。スヴャトポルク・イジャスラヴィチなどのようにリューリク家でも使われていた。
19世紀からは、新しいインテリゲンツィヤが父称を使うようになった。1861年に農奴制が廃止されると、農民の父称の使用も許されるようになった。
現代ロシア人の生活に父称は欠かせない。これは相手に対する尊敬の念を込めた呼び方であり、同じ名前と姓と持った人を区別するためにも必要だ。
(ロシアNOW 2014年10月9日)

▲http://daikonpapa.cocolog-nifty.com/daikonpapa/2013/04/post-11e8.html
★島根県代表団
モスクワの女子修道院に牡丹の木 贈呈
◆The Voice of Russia 2014年9月16日 04:55
http://japanese.ruvr.ru/news/2014_09_16/277335029/

▲Photo: RIA Novosti
モスクワ中心部にあるマルフォ・ マリインスキイ女子修道院に、日本のシンボルがお目見えする。リア-ノーヴォスチ通信がロシア正教会宗務局報道部の情報として伝えた。
それによれば「16日、マルフォ・マリインスキイ女子修道院で祝賀セレモニーが執り行われ、その中で、島根県代表団が友好のしるしに、モスクワ総主教管区に日本のシンボルの一つ、ユニークな牡丹の木を贈る。」
正教会報道部はまた「植樹式は、2007年に極東でスタートした『花咲く日ロの道』プロジェクトの枠内で行われる。これまですでに、ウラジオストーク、ハバロフスク、サンクトペテルブルグに、牡丹を含め、美しい花を咲かせる日本産の様々な木々が植えられてきた」と指摘した。
マルフォ・マリインスキイ女子修道院は、1909年、モスクワ大公セルゲイの妻、エリザヴェータ・フォードロヴナ(ニコライ2世の妻アレクサンドラの姉、ボリシェヴィキによりウラルで惨殺された)によって設立された。革命後閉鎖され、ソ連時代はイコン修復所などとなったが、1990年から修道院を甦らせる作業が始まった。
現在、修道院には25人のシスターがおり、敷地内に障害児のリハビリ施設を設けたり、重度の遺伝病患者の支援に取り組むなど、エリザヴェータ・フョードロヴナの志を継ぎ、幅広い慈善プログラムを展開している。
又修道院では、援助を必要とする人々を常に受け入れており、食糧品・医薬品支給のほか、生活及び人生相談に応じている。
なお敷地内に建つ、美しいポクロフスキイ聖堂は、建築家シューセフの傑作の一つである。
リア-ノーヴォスチ
(The Voice of Russia 2014年9月16日)
★モスクワで第19回「日本の秋」
◆The Voice of Russia 2014年9月17日 02:16

▲Photo: RIA Novosti
モスクワで恒例の「日本の秋」フェスティバルが始まった。日本の伝統音楽のコンサートや各種の展示、レクチャーその他イベントが行われる。
イタル・タス通信は在ロシア日本大使館のクサカベ・ヨウスケさんに特別インタヴューを行った。「モスクワにおける「日本の秋」祭は日本大使館が95年に始めたもの。多くのロシア人、モスクワ市民に愛されている。今年もイベントが盛り沢山だ。現代日本文化を紹介するJ-FESTや、日本映画
祭、また日本の舞台芸術を代表するものとしてアンサンブル「京都創生座」および劇団「チェルフィッシュ」の公演が行われる。また、今年は日露武道交流年ということで、11月には日本武道館の代表が武術のデモンストレーションを行う。モスクワ以外でも、たとえば各地で映画祭や、サンクトペテルブルグの「折り紙の味」展など、様々なイベントが行われる」
日本文化を知るのに欠かせない日本語そのものの学習熱もロシアでは高まりを見せている。クサカベさんによれば、1990年に550人だったロシアにおける日本語学習者は、2012年には1万1400人にまで増えている。
イタル・タス
(The Voice of Russia 2014年9月17日 )

★牡丹なら「松江産」
吉村慎司, 「ロシアNOW」への特別寄稿
■ロシアNOW 2012年12月12日
生産量上回る注文
ロシアの花市場に、日本産の牡丹(ぼたん)が広がり始めた。山陰の古都・島根県松江市から苗木の試験輸出が始まって4年目。最初の年に200本だった出荷量は順調に増え、今年は過去最高の1500本に達した。
「マツエの牡丹は今年はいつ買えるの」。この夏、ウラジオストクやハバロフスクの花屋に、一般客からのこんな問い合わせが相次いだ。
松江の牡丹輸出の仕組みはこうだ。生産者団体のJAくにびきが、松江に隣接する鳥取県の境港から、ウラジオストク行きの定期フェリーに乗せて苗木を出荷。パートナーであるウラジオストクの花業者が受け取り、極東地域に流通させる。
苗木を運び込むだけではない。松江市や島根県、日本貿易振興機構(ジェトロ)なども協力して、ウラジオストク、ハバロフスクの2都市で毎秋PRイベントを開いて知名度アップに努めてきた。
今年は9月下旬から10月中旬にかけて、一般消費者向けの展示即売会を3回開催。どの回も大入りで、数百本の苗木が即日完売となった。特に、「松江ブランド展」として催したイベントにはウラジオストク市内の会場に2000人が詰めかける盛況ぶりだった。
なぜ人気が出ているのか。理由は、少なくとも価格ではなさそうだ。今年の苗木の販売価格は1本1100ルーブル(約2800円)で、日本での相場の約3倍だ。輸送などの経費がかかるためで、安価な中国産の牡丹と比べれば5~10倍の開きがある。
JAくにびき特産課の佐川真二係長は、好調の理由をこう説明する。「ロシア市場の牡丹は、花が下向きに咲く中国産が主流。この中で、上を向いて花開く松江の牡丹は美しさで競争力があります。また、中国産に比べて枯れにくいとの評価もいただくようになりました」。実際、リピート客が目立つという。前年試しに買ってみた牡丹が予想以上にきれいに咲き、別の色・種類を集めたくなった客も多いようだ。
実は今年、ロシアから2000本近い注文が来ていた。生産量が追いつかないため1500本に抑えざるを得なかったという。
JAくにびきは今、ロシア市場向けの牡丹栽培を始めることを計画中だ。来春にもウラジオストクからパートナー業者を招いて、品種や量の詳細を詰める。
牡丹はこれまで極東に限った展開だったが、2013年にはサンクトペテルブルクなどヨーロッパ側の大都市での販売も実現しそうだ。JAの佐川係長は、「ロシアは花を好む国民性もあり、我々にとって有望な市場。まずは年間出荷量を早期に1万本レベルに引き上げたい」と意気込みを語っている。
(http://m.jp.rbth.com/articles/2012/12/12/40375.html)
(ロシアNOW 2012年12月12日)