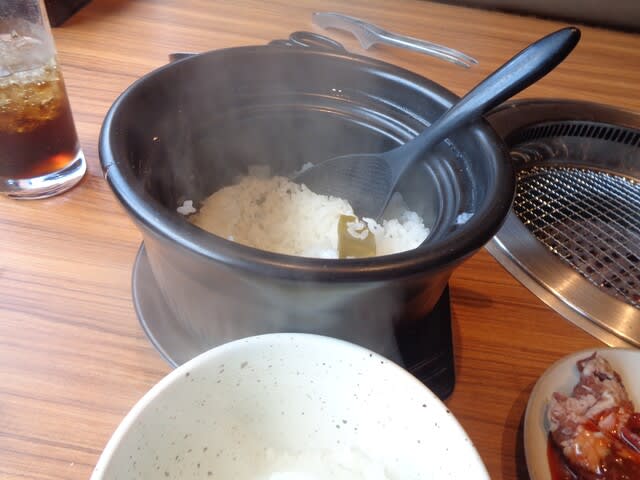[映画紹介]

2011年11月19日早朝5時22分、
双極性障害(躁うつ病)を患う黒人の元海兵隊員ケネス・チェンバレンは
就寝中に医療用通報装置を誤作動させてしまう。
ライフガードの安否確認要請により、
まもなく、白人の警官3名が到着。
ケネスは間違いであると伝えたにも関わらず、
家のドアを開けるのを頑なに拒むケネスの態度に、
不審感を抱いた警官は、
中で犯罪が行われているのではないかと疑い、
無理やりドアを開けようとする。

そして、7時過ぎ、
ドアを壊して入ってきた警官にケネスは撃たれ、死亡する。
ニューヨーク州の町で実際に起きた事件。
何の罪も犯していない70歳の老黒人が、
なぜ警官に射殺されなければならなかったのか。
その真実を描くのがこの映画。
実際の事件の経過とほとんど同じ83分間、
リアルタイム進行形で、
老人の室内と部屋の前の階段だけを舞台に
緊迫感に満ちた映像が続く。

何の問題もない、機械の誤作動だ、
と告げたにもかかわらず、
警官隊が硬化したのは、
その地域が貧困層の住む住宅で、
犯罪のおそれあり、とする先入観と、
相手が黒人であったことが要因となっている。
もし地域が高級住宅地で、
老人が白人なら、警官は潔く退いただろう。
しかも、ライフガードが安否確認要請を取り下げたのに、
現場には伝わらず、
消防の応援まで頼んで、
礼状もなしに、
斧とカッターでドアを無理やり開けるのは、
明らかに違法行為。

警官隊の中には、
それを指摘する者もいたが、
興奮した隊長はそれを無視。
部屋に乱入後も、
武器を持っていない老人を押さえつけた上、
発砲するなど言語道断。
繰り返すが、
犯罪多発地域と黒人であるという
先入観によって犯された警官の犯罪。
老人は頑なに見えるが、
白人警官が3人来て、
高圧的な態度で無理やり部屋に入ろうとされたら、
恐怖心が高まったことだろう。
過去に警官との間での恐怖体験があったのかもしれない。
モーガン・フリーマンが、製作総指揮を担い、
監督はデヴィッド・ミデル(脚本も)。
映画批評サイト「ロッテントマト」では
批評家97%、観客85%と最高の評価を獲得。主演のフランキー・フェイソンは
アカデミー賞の前哨戦であるゴッサム賞で最優秀主演男優賞を受賞。

エンドクレジットで、
事件に関わった警官が誰も起訴されず、
有罪にもなっていない、と告げられて、驚いた。
訴訟社会のアメリカで、弁護士は何をしていたのか、
遺族は訴えなかったのか。
と思ったら、
映画公開時までは、市は過失を認めてはいなかったが、
今年8月に和解金を支払って、
遺族との和解が成立したとのこと。
それにしても遅い。
この映画の影響が少なからずあったのか。
5段階評価の「4」。
ヒューマントラストシネマ渋谷で上映中。