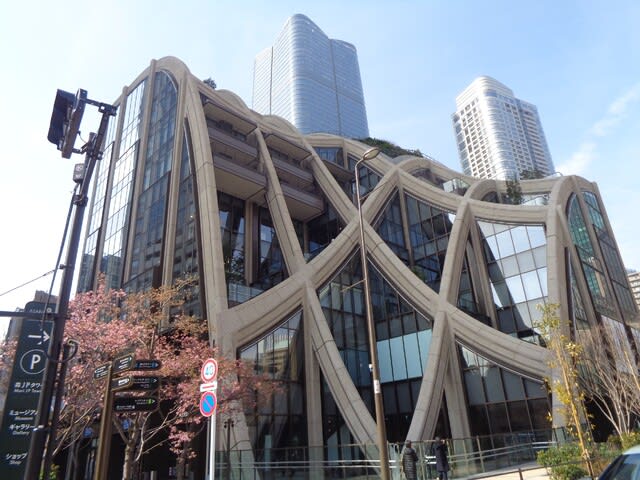[書籍紹介]

昨年、「木挽町のあだ討ち」で直木賞を受賞した
永井紗耶子の受賞第1作。
産経新聞に連載された。
「きらん」とは、
栗杖亭鬼卵(りつじょうていきらん 1744 -1823年)のこと。
江戸時代の浮世絵師、戯作者。
江戸幕府の老中職を退いた松平定信が
旅先の掛川で雨のため大井川で足止めをされた際、
側近から「東海道人物志」の筆者が、

近隣の日坂宿(にっさかしゅく)で煙草屋を営んでいる、
ときいて、興味を持ち、
お忍びで出かけて、
鬼卵の16、7の頃から75歳までの
生涯を聞く、という形を取っている。
陣屋の手代であった父から
「楽しいことをせい」と薫陶を受けた伊那文吾(後の鬼卵)は、
狂歌作者である栗柯亭木端(たっかていぼくたん)の弟子になり、
研鑽中、狭山の北条家の御家騒動を目撃し、
若い暗愚の主君のせいで
忠臣が腹を切らされる理不尽に怒りを覚える。
その顛末を書いた「失政録」が鬼卵の最初の著作となった。
この事件が鬼卵の反骨精神を育んだものと思われる。
ある日、師匠から筆を握れと命じられ、
「筆は卵や。
ここからは武者も美女も神仏も出る。
それが人の心を躍らせ、救いもする。
せやけどここからは、鬼も蛇も出る。
それは思いがけない形で暴れ、人を食らいもする」
と言われる。
これが「鬼卵」の命名のいわれ。
この言葉は生涯鬼卵を縛り、
「自分は卵を孵らせていないのではないか」と悩む。
夜燕(やえん=蝙蝠の意味)という妻をめとり、
三河吉田で一緒に過ごし、
妻を病死で失い、悲嘆の日々が続く。
飢饉にも出会い、民衆の悲惨な姿に心を砕く。
そんな時、ある女性から与えられた言葉。
「物を思い、考え、書き、歌う。
それは人が人である証。
食うことのためだけに生きるわけではない。
そのことが、己を支える誇りにうなります。
荒地にあってこそ、
歌も絵も書も、
潤いの滴となりましょう」
木村蒹葭(けんか)堂、上田秋成や円山応挙らとの親交も描かれる。
また、伊豆韮山の代官、江川英毅との深い交流も。
そこで描いた三嶋大社の祭りの絵は、
「東海道名所図会」にも収録される。

鬼卵が求めたものは、
自由自在の境地。
その行き着くところが、
辺鄙な宿場での煙草屋だった。
「生まれた地にも、
親兄弟にも縛られず、
自らが仕えたい者に仕え、
志のままに生きる」
寛政の改革で天下人となった
元老中・松平定信と鬼卵の会話が味わい深い。
身分も考えも正反対な二人の問答は、
読み手の人生をも問いかける。
「忠義」ということを言われ、鬼卵は、こう言う。
「何分、仕官しておりました折にも、
主の顔なぞ見たことがございません。
さすれば、有難いのは禄のみ。
それもさほどのものではございませぬ故、
さて、何に忠義を尽くしましょうや」
また、こうも言う。
「君臣としてではなく、人として信ずる。
それは忠義より強いとは思われませんか」
定信は、鬼卵に
「その方、余が何者か知っているのか」と問うと、
鬼卵は、こう言う。
「いいえ、お忍びでいらしているからには、
気づいても気づかず、
見ても見ずが粋人でございましょう」
鬼卵の話は、定信のなした政(まつりごと)への批判にも及ぶ。
それは、老中退任後も、
後継者の息子の政に口出しし、
疎んじられている定信の心に刺さるものだった。
ついに定信は、
「その方は、老中であった松平定信という者をどう思う」
と訊いてしまう。
それに対して鬼卵は、障子に書かれた歌を示す。
「世の中の 人と多葉粉(たばこ)の よしあしは
煙となりて 後にこそ知れ」
別れの時、定信は、
こんな小さな店の老爺の言葉に、
天下人であった己が耳を傾けるとは、
つい数日前までは思いもしなかった、
という感慨を抱く。
最後に定信は鬼卵に言う。
「そうさな。
共に風月を愛で、人生を楽しむとしよう。
煙となって後に会おうぞ」
小説の最後は、こう結ぶ。
文化十五年の春の終わり、
花びらの舞う日坂宿の街道で、
戯作者栗杖亭鬼卵と風月翁松平定信は、
ひとときの邂逅の後、
静かにすれ違って行った。
戯作者と権力者の邂逅を通じて、
人の生き方を問う、
なかなか味わい深い本だった。