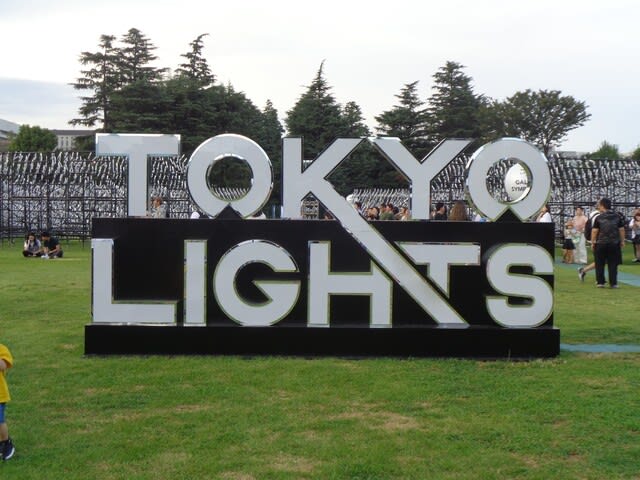[映画紹介]

題名で分かるように、
侍がタイムスリップする話。
どこからタイムスリップするかというと、
幕末の京都から
現代の京都、しかも、時代劇撮影所というのがミソ。
会津藩士の高坂新左衛門は
長州藩士を討つよう密命を受け、
同志と共に待ち伏せする。
寺から出て来た相手は
一撃で一人を失神させるほどの豪の者。
二人が刃を交えた瞬間、
雷が落ち、気を失ってしまう。
目を覚ますと、そこは現代の時代劇撮影所だった。
江戸時代の扮装の人々に交じり、
洋装で妙な機械(撮影カメラ)を操作する人たち。

そこで展開する時代劇に介入して叱られた新左衛門は、
頭をぶつけて病院に担ぎ込まれ、
混乱の中、現代の町を彷徨い、

あの武士と一騎討ちをした寺の門前にたどり着く。
寺に居候しながら、
江戸幕府が140年前に滅んだことを知り、愕然とする。
(ということは、この映画の舞台は、2008年ということになる)

動く絵(テレビ)や現代人の食べ物に驚きながら、
やがて磨き上げた剣の腕を発揮して、
撮影所の中で、斬られ役として生きていく。
時代劇の侍の役を、本物の侍が演ずるのだ。
評価が定着した頃、
往年の時代劇スターが、10年ぶりに時代劇に復帰する、
という話が伝わって来て、
新左衛門は、そのスターから
準主役で出演してほしいとオファーを受けるが・・・
ここで物語は急展開を迎える。
タイムスリップものとしては、見たことのある設定だが、
この時間差タイプは初めてで、ちょっと驚いた。
そして、新左衛門がタイムスリップした意味や、
斬られ役として生きる存在が問われてくる。
幕末時、新左衛門がいた会津藩の滅亡も語られる。
俄然、物語は
歴史ドラマ、人間ドラマになって来るのだ。
しかも、熱い。
時代劇への愛が溢れる。
最後の対決シーンは熱気があふれる。

映画の最後にあるオチは秀逸。
実は、この映画、自主映画。
低予算で、有名俳優やスタッフを起用しているわけではない。
スタッフは全部で10人しかおらず、
人手不足のため、準主役級の女優(沙倉ゆうの)が助監督を兼務。

製作費は監督の安田淳一が、車を売り、貯金をはたいて工面。
安田は、脚本・撮影・編集を兼任し、
チラシ作成・パンフレット制作まで11役以上を1人でこなしたという。

8月17日に池袋シネマ・ロサという小さな映画館一館のみで封切られたが、
評判が評判を呼び、上映館が増え、
ついには、ギャガが配給に乗り出し、
新宿ピカデリー、TOHOシネマズほか
全国100館以上で上映と、全国展開した。

第2の「カメラを止めるな! 」と言われている。
エンドクレジットで出て来た俳優名は誰一人として知らない。
しかし、後で調べてみたら、
山口馬木也(やまぐちまきや)も、

冨家ノリマサ(ふけのりまさ)も、
こちらが知らないだけで、
時代劇の脇役としてのキャリアは十分な人達だった。
東映京都撮影所の特別協力によって完成。
脚本に感銘を受けた撮影所が
「自主制作で時代劇をつくるなどと言ったら
いつもなら全力で止めるが、
これは本(脚本)が面白いから、是非やりたい」
と、全面協力したというのも泣かせる。
丁度「SHOGUN 将軍」のエミー賞受賞のニュースが報じられ、
「これまで時代劇を継承して支えて下さった全ての方々に
心より御礼申し上げます。
あなた方から受け継いだ情熱と夢は
海を渡り国境を越えました」
という真田広之の日本語でのスピーチが出されたばかりなのは、
何かの符号だろうか。
テレビ局の支援がなくても、
メジャーの映画会社の製作でなくても、
アイドルが出ていなくても、
コミックが原作でなくても、
良い映画を作れば、
観客が発見してくれる、
という典型。
5段階評価の「4」。
TOHOシネマズ日比谷他で上映中。