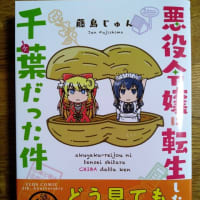まず、川崎市の郷土史を語る上で、角田さんのことを知らなかったら、「おいおいっ」と突っ込みたくなるくらい、とても有名な在野の研究者です。
私は角田さんに何度かお会いしたことがあります。
多分角田さんは私のことは覚えていないと思いますが。
郷土史にかける情熱から高校で歴史を教えていたのかしら?と思いつつ、学校の先生特有の雰囲気を感じず、一体この方はどんな仕事をなさっていたのかしら?と思ったモノでした。
さて、川崎市で紙漉をしていたのはかなり昔で、昭和になる頃には衰退した…と思っていました。
私は農間余業(のうかんよぎょう)や、農間渡世(のうかんとせい)と呼ばれる、農家が農閑期に行う副収入になる仕事について興味があります。
川崎市内の江戸末期から明治初めの頃の資料はそれなりに調べたことがありますが、紙漉を行うことは少なかった、という結論でした。
ところが、この本によると多摩区あたりでは昭和になってもそこそこ紙漉を業として成立していたようです。
例えば、着物の芯に使った綿を材料にした綿紙を製造していたとか。
それは八王子辺りに出荷していたとか。
なぜ、八王子かと言えば、養蚕が盛んで織物もたくさん作るし、その一環で着物を仕立てることも多いので、需要があるのです。
また、養蚕では紙に卵を産み付ける「蚕卵紙」の原料になる和紙が必要になります。
そう言った養蚕にまつわる紙漉が盛んだったのです。
そして1番ビックリした記述がありました。
陸軍登戸研究所をご存じでしょうか?
川崎市多摩区登戸にあった、研究所で731部隊関連の施設でもあります。
以前読んだ武内孝夫さんの「こんにゃくの中の日本史」という新書で、登戸研究所ではこんにゃく粉と和紙で風船を作って爆弾を飛ばす研究をしていた、と知りました。
この本によると、その風船に使う和紙を調達するため、登戸周辺で紙漉の機械類を調査したそうです。
結局は、登戸周辺では、需要に応じるだけの機材か揃わなかったそうですが、軍需とは様々な物資に至るものだと感じました。
また、登戸周辺で使われた道具は、埼玉県の小川町辺りから仕入れたものとも書かれています。
小川町の紙漉道具…あれ?ユネスコ無形文化遺産の細川紙の産地ですね。
同じ道具で作っていたのか、と驚くばかりです。
この本は、1,000部限定で製本されたので市販はされていません。
個人的には手元に置いて熟読したいのですが、図書館で借りるしかありません。
川崎市内の図書館なら18冊ありますし、国立国会図書館にも収蔵されています。