
見上げると横浜中華街の空に満月が灯っていた。
去る2月17日は、元宵節の日だ。
正しくは、元宵節が2月17日だった。
旧暦の話しをすると、解説しているメタ坊も混乱してしまう。
どうしても、現在の暦の都合で節分の豆まきが立春(2月4日)の前日にあるから、ついつい混同してしまうのだ。
旧正月は、太陽の運行を基準にした二十四節気の雨水(2月19日)の前の、月齢の朔日(今年は、2月3日)を元日、はじめて迎える望月(満月)の日を元宵(げんしょう)節として祝う。
ただ、国立天文台の満月が18日の午後5時30分となっているから、元宵節は中国暦を採用しているのかもしれない。
春節の最終日。この間を日本でいうところの「ここまでが松の内」に相当すると考えるとわかり易いかな?
元宵節の由来は、中国三大悪女とされる、漢の高祖(劉邦)の皇后・呂后の死後、専横を極めた外戚呂氏が一掃されて、文帝(劉恒)が即位し、乱の平定を正月15日に祝い、元宵節と名付けたものといわれている。
道教でも、上元節として、ランタン (提灯)を灯して祭祀を行っていたこともあり、それが習合したことから民間に流布し、盛大に祝うようになったようだ。
関帝廟では、大きなランタンが吊されたほか、階段には願い事の書かれたメッセージ燈籠がともされた。
天女の舞も奉納されたというが、見に行こうといいながら、一杯、いや二杯・・・何杯?飲んでいるうちに終わってしまった。
NTTの前には、鳳凰の飾りランタンがあった。
立体駐車場にも、イルミネーションと飾りランタンがあった。
山下町公園の会芳亭にもランタンが下げられ、ケヤキの木にはイルミネーションが飾られた。
ふと、その下を見ると、どこの酔っぱらいかわからないが、「俺はここにいるよ~~」とか言って、ゴロゴロ寝ながらケータイしていた。
酔っぱらいには、なりたくない。
さて、天女の舞を見損なった原因の甕出し紹興酒、6年ものと3年もの。
そして、元宵とも湯円ともいわれる白玉のデザート。
湯の中で踊る白玉を天の満月に見立て、一家団欒で過ごす春節(お正月)のように今後も円満(団円=湯円と同じ音)であることを願って食べる。
白玉の中身は、擂り黒ごまと砂糖を混ぜたもので、シロップではなくただのお湯に3個入っていた。
ちなみに、ランタンといえば、長崎のランタン祭りも年々盛大になってきたが、中国古来の旧正月を過ごす台湾の平渓郷の天灯イベントは有名だ。
天灯は、三国志で有名な諸葛孔明が発明した熱気球の一種といわれている。
軍事用の通信手段として用いられたもので、映画「墨攻」や「赤壁(レッドクリフ)」の中でも、象徴的に用いられている。
玉皇大帝(道教の最高神・天帝)が飼っていた天鷺が人間界に舞い降りた際、猟師に矢で射られたために傷ついた。
そのことに怒った天帝は、正月15日に天兵を地上に向かわせて人間界を焼き払うことにした。
それを知った仙人の一人が地上に降り、正月15日に家々で松明を燃やし、ランタンを灯せば厄災を免れると伝えてまわった。
その日、仙人は「人間界をすでに焼き払った」と天帝に報告すると、天帝は南天門から地上を見下ろして、その言葉を信じ、天兵を向かわせるのをやめた。
以来、元宵節にランタンを灯すようになったのだという。
この言い伝えが、レッドクリフの中の曹操軍が焼き払われるシーンとオーバーラップしている。
日本で行われる左義長やどんど焼き、柴灯祭りといわれるものも、陰陽道の宮廷行事が起源とされているから、中国のどこの風習を導入したのかわからないけれど、ルーツはここにありそうだ。
天灯は、書き初めが天高く舞い上がることに、団円は、繭玉団子や三つ又の木に刺した団子に姿を変えている。
天帝が閻魔王になってしまうのは仏教の影響が大きいようだ。
そういえば、赤壁の戦いが始まる日が冬至にあたり、やはり風習として、一家団欒で湯円(白玉)を食べるということを軍団結束を確かめるシーンとして象徴的に描かれているのも見逃せない。
夜も遅くなると、中華街大通りはタクシーの車列が延々と続く。
これもまた、ランタン行列だと思えばまた一興だ・・・とりあえず、久しぶりに酔った。
途中、酔っぱらいになりそうになった。
日本大通りと富士山を被写体として、定点観測中です。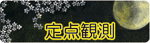
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます