江戸川乱歩編の世界推理短編傑作集の新版全5巻を買ったのは発売されてさほど経っていない2019年のことだったと思いますが、2020年1月~3月にかけて1巻を読んで以降、2~5巻は積読本化していたのですが、年末年始で仕事の隙間ができたので2巻をようやく手に取ってみました。
収録作品は次の9編:
- ロバート・バー『放心家組合』
- バルドゥイン・グロラー『奇妙な跡』
- G.K.チェスタトン『奇妙な足音』
- モーリス・ルブラン『赤い絹の肩かけ』
- オースチン・フリーマン『オスカー・ブロズキー事件』
- V.L.ホワイトチャーチ『ギルバート・マレル卿の絵』
- アーネスト・ブラマ『ブルックベンド荘の悲劇』
- M.D.ポースト『ズームドルフ事件』
- F.W.クロフツ『急行列車内の謎』
1.『放心家組合(The Absent-Minded Coterie)』(1905)
Robert Barrはスコットランド系カナダ人で1881年にロンドンに移住して作家活動を精力的に行ったため、「イギリスの大衆作家」とされることが多い。
推理小説はロンドン在住フランス人探偵のユウゼーヌ(またはユジェーヌ)・ヴァルモンを主人公とするシリーズで、『放心家組合』はそのうちの1作。
ロンドン在住のフランス人探偵というとアガサクリスティーのポワロを彷彿とさせますが、ポワロシリーズは1920年から始まっているので、1904年に始まったヴァルモンシリーズの方が先ですね。
『放心家組合』ではロンドンに濃霧が垂れ込める11月のある日に初めて聞いた「サマトリーズ事件」の回想という形で話が始まります。アメリカ有数の富豪であるブライアン氏が大統領選に落選したことと銀価格問題を新聞で読んでいるところにスコットランドヤードのスペンサー・ヘイルが訪ねてきて銀貨贋造団の話と怪しい人物であるラルフ・サマトリーズについての話をして、ヴァルモンに協力を要請します。
刑事と探偵のタッグはいかにも古典的推理小説という設定ですが、結末は「え、そういうオチ?」という意外なものでした。探偵小説自体のパロディーのような味わいがあります。
2. バルドゥイン・グロラー『奇妙な跡 (Die Seltsame Fährte)』(1909?)
Balduin Grollerは旧オーストリア=ハンガリー帝国の作家で、探偵ダゴベルトを主人公にした推理小説で知られています。「オーストリアのコナン・ドイル」と評されているらしいです。
『奇妙な跡』では産業クラブの会長アンドレアス・グルムバッハの森林管理人であるマティーアス・ディーヴァルトが森の外れで殺された事件を扱っています。ディーヴァルトは前日の金曜日に猟場番人や樵たちの週給を会計事務所で受け取ったあと酒場で一杯やった後に強盗殺人にあったようで、持っていたはずのお金が無くなっており、殺人現場には足跡ではなく奇妙な跡が残っていたことがテーマになっています。
ただ、どんな跡だったのか詳しく説明されないままダゴベルトが独自捜査をして犯人を捕まえてしまうので、読者が推理する余地は残されていません。
残されていた跡の説明をしてしまうと犯人がすぐにばれてしまうため、ぼかさざるを得なかったという印象を受けます。
3. G.K.チェスタトン『奇妙な足音 (The Queer Feet)』(1910)
『奇妙な足音』は「真正十二漁師クラブ」という謎のクラブに属する12人のイギリス貴族の会員が年一度のクラブの晩餐会を行うヴァーノン・ホテルで起こった事件をブラウン神父からの又聞きという形で語ります。
文体がややもったいぶってまだるっこしいのですが、一周回って面白いと言えるかもしれません。
ヴァーノン・ホテルの給仕の1人が急死したためにブラウン神父が呼ばれ、ホテルの事務所の横の私室を一時借りて書類の作成をしていると廊下を1人の人間が足早に歩いたり、ゆったりと歩いたりしているような足音を聞き、奇異に思ってその正体を突き止めようとしたという話です。
ストーリー自体よりも、イギリス貴族に対する皮肉な風刺の方が面白いですね。
4. モーリス・ルブラン『赤い絹の肩かけ (L'Écharpe de Soie Rouge)』(1911)
『赤い絹の肩掛け』はかの有名なアルセーニュ・リュパンと宿敵のガニマール警部のお話の1つです。
ある日リュパンが手の込んだやり方でガニマール警部をおびき出し、とある殺人事件の証拠品を預け、彼なりの殺人の経緯の推理を聞かせ、警部にその事件を解決するように依頼します。
その証拠品の1つである赤い絹の肩掛けの片割れだけはリュパンが手元に残し、それが必要になったら12月28日に警察の手に入るであろうもう一方の片割れを持って来るように言い残して消えてしまいます。
警部がむかむかしながら警察へ戻るとちょうどリュパンの言っていた殺人事件が警察の知るところとなり、警部が捜査を担当することになります。
リュパンの入れ知恵があったために早急に犯人逮捕に至り、ガニマール警部の名声も上がったのですが、公判の維持には決定的な証拠が欠けており、その証拠こそがリュパンが握っている肩掛けの片割れだったので、言われたとおりに12月28日に前回おびき寄せられた館へ向かいます。
リュパンが何のためにガニマール警部にそんなことをさせたのか?
もちろん警部はリュパンをあわよくば逮捕しようと準備していたのですが、案の定するりと逃げられてしまいます。
5. オースチン・フリーマン『オスカー・ブロズキー事件 (The Case of Oscar Brodski)』(1911)
この作品は科学者探偵であるソーンダイク博士が活躍するシリーズの1つで、フリーマンの提唱する倒叙推理小説という形式が最も成功していると言われています。
つまり、犯人視点の犯罪の過程がまず描写され、その後に探偵視点で残された手掛かりからその犯罪行為を推理し特定する過程が描写されるというものです。
サイラス・ヒックラーはその温厚な見かけによらず根っからの犯罪者で、計画的に犯罪を犯し、慎ましやかに暮らしていたのでそれまで捕まることがなかったのですが、ある日、ダイヤモンド商のオスカー・ブロズキーが偶然ヒックラー宅のそばを通りかかり、彼に駅までの道を訪ねます。ヒックラーは自分も次の列車でアムステルダムに出かける予定なので、それまでの間彼の家に上がって待ち、時間が来たら一緒に駅まで行きましょうとブロズキーを自宅に招き入れます。ヒックラーはダイヤモンド関係の商売にも携わったことがあるので、ブロズキーのことも知っていましたが、ブロズキーの方はヒックラーと多少の面識があることを思い出せないまま、何の警戒もせずに招きに応じて家に上がり、供されたウイスキーとオートミールのビスケットを夢中になって食べます。
そうしているうちにヒックラーがブロズキーが持っているだろうダイヤモンドの誘惑とそのための殺人の衝動に駆られ、ついに殺人に至ります。こうしてまんまとダイヤモンドを手に入れ、証拠隠滅を図り、列車に乗って出発するところで第一部が終了します。
第二部で携帯用実験室と呼べる様々な器具や薬品の入った緑のトランクを携えたソーンダイク博士が登場して、捜査が始まります。
探偵の推理する先のゴールが先に提示されているので、謎が次々に明かされていく楽しみがありません。必然的に推理の過程そのものに焦点が当たることになります。科学の力で微細な断片的物証からどんなことが類推可能になるのか、その一点にフォーカスされていると言っても過言ではないでしょう。
このような倒叙形式は、科学的捜査方法が最先端のものである場合に最も面白味があるのではないかと思います。ソーンダイク博士が使う検証のための道具は1911年時点では最先端だったのでしょうが、110年後の現在読んでも残念ながら真新しいものは何もありません。
6. V.L.ホワイトチャーチ『ギルバート・マレル卿の絵 (Sir Gilbert Murell's Picture)』(1912)
この作品は『ソープ・ヘイズルの事件簿』という短編集の中の1つ。
進行中の列車の中央部から貨車が一台抜き取られ、その貨車に積まれていた絵マレル卿の絵が贋作とすり替えられるという事件を扱います。
かなり大掛かりなトリックですが、本当に描写されている方法でそれが可能なのかどうか私には分かりかねます。
私は推理小説好きではあってもあまりトリッキーなものは好まないので、この短編はいまいちでした。
7. アーネスト・ブラマ『ブルックベンド荘の悲劇 (The Tragedy at Brookbend Cottage)』(1913)
この作品はマックス・カラドスという盲人探偵が活躍するシリーズの代表作です。「盲人探偵」と言うからには安楽椅子探偵の類だろうと思いきや、友人のルイス・カーライルの助けを借りてかなり外に出かけてます。
ある日ホリヤー大尉というクライアントがカラドスを訪ねてくるところから話が始まります。ホリヤーはブルックベンド荘に住む姉夫婦の様子がおかしく、夫のクリークにそのうち何かされるのではないかと心配でカーライルに相談し、カラドスに頼ることになります。
こうしてカラドスが捜査に乗り出し、クリークの企みを徐々に暴いていき、最終的には警察の協力の下、クリークの工作をギリギリまで実行させて殺人未遂の角で逮捕に至るのですが、オチがなんとも釈然としない、題名の通り「悲劇」で終わってしまいます。
全体的にさほど面白くないと感じました。どこら辺が「傑作」なのかよく分かりません。翻訳がところどころ分かりにくいのも玉に瑕ですね。
8. M.D.ポースト『ズームドルフ事件 (The Doomdorf Mystery)』 (1914)
この作品はアンクル・アプナー探偵シリーズの1つで、密室殺人事件を扱います。
傭兵上がりらしいズームドルフはヴァージニア州の岩山に居を構えて桃を植え、収穫した桃で酒を醸造して販売し、村人たちを堕落させ、逃走に明け暮れさせたと政府に目をつけられます。彼に酒の醸造販売を止めさせようとランドルフ治安官がアプナーを伴ってズームドルフを訪ねると、彼は外から閂のかかった寝室で猟銃に胸を撃たれて死んでいました。誰が彼を殺したのか?
すると、彼らよりも先に来ていたメソジスト派巡回僧のブロンソンが自分が彼を殺したと言い、また、ズームドルフの家政婦も「やっと殺してやった」などと口走ります。
しかし、話を聞いてみるとブロンソンは「天の火」の仕業だと言い、家政婦は呪いの蝋人形を使ったと言います。
では、誰が猟銃を撃ったのか?その謎はアプナーがあっさりと解き明かします。
アルコールが禁制だった開拓時代のアメリカの話ですから、酒醸造販売をしていたズームドルフは天罰が下って当然の悪人という扱いです。非常に宗教色も濃厚な作品で、推理小説というよりは風俗小説の一種のようです。
9. F.W.クロフツ『急行列車内の謎 (The Mystery of the Sleeping Car Express)』(1921)
この作品はタイトルからも察せられるように列車という大きな密室の殺人事件を扱います。事件自体は1909年の秋にノース・ウェスタン急行列車がプレストンとカーライルの中間に差し掛かった際に起き、英国全土を騒がせたものの、結局未解決のままお蔵入りとなったのですが、著者はつい最近とある偶然から事件の詳細を知るに至ったので、その仔細を書き留めることにした、という感じに物語が始まります。
そして列車の構造の描写やどこにどんな乗客がいて、車掌がどのように動き、事件が発見された経緯や発見後に車掌の取った行動や警察の調べなどが淡々と語れられ、様々な推論の検証などが行われますが、結局、犯人がどうやって列車から出たのかという謎が解けずにお蔵入りになるところで前半部が終了し、後半部は事故で死にかけている犯人が著者である医者にそのすべての経緯を告白します。探偵ではなく下手人本人の告白による謎解きというパターンの典型ですね。










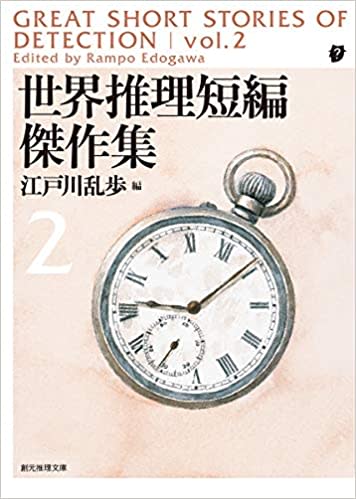
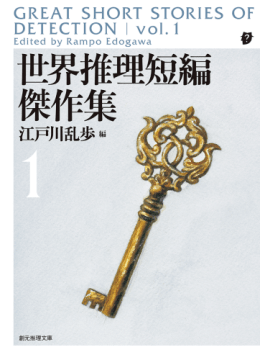 『世界推理短編傑作集 新版1』を
『世界推理短編傑作集 新版1』を